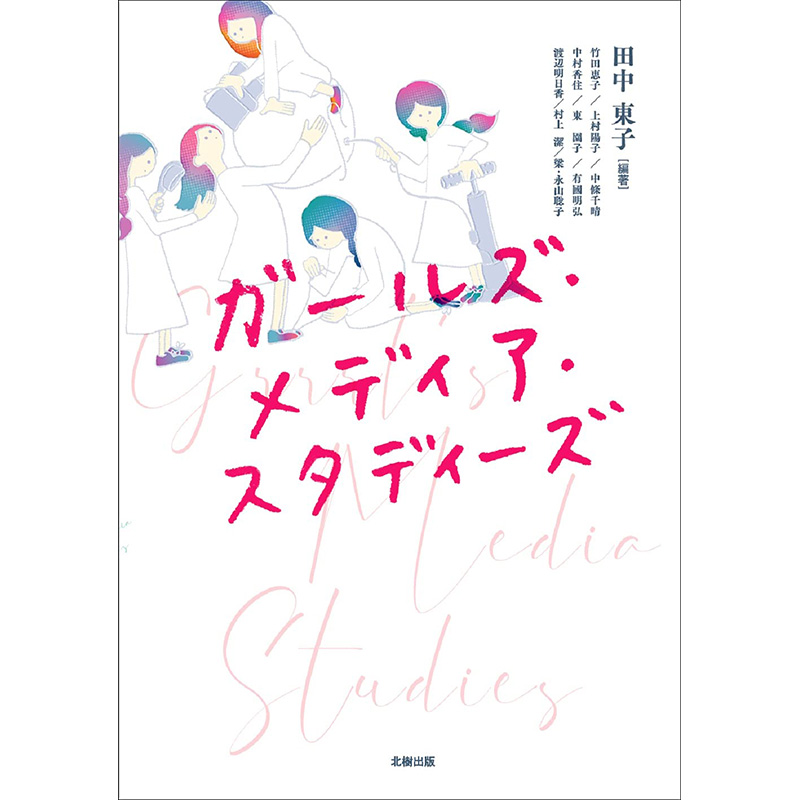MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > ガールズ・メディア・スタディーズ- 田中東子(編著)
「まず自分でやってみる」なんて余計なお世話。他人に言うことじゃない。やりたいのに、なぜだかちょっと踏み出せないでいる自分に対して、そっとつぶやいてみればいいんだと思う。
それでも、どこへむかって踏み出せばいいのか、さっぱりわからないということもある。そういうときに役に立つ教科書があってもいい。この本は「女性たちがどのようにメディアの中で描かれているか、もしくは女性たちがどのようにメディア文化をいきいきと創っているのか、という点に関心のある学生たちにむけての教科書」だという。「表彰と解釈」と括られた前半では映画や広告、音楽からメイド喫茶や援助交際まで、若い女性たちがメディア空間でどのように表象されるかが分析される。メイド喫茶のメイドがツイッターなどのSNSを使ってどのようにセルフ・ブランディングをしているか、それはどのような「労働」なのか。あるいは90年代の女子高生ブームとはなんだったのか。援交する美少女像は誰が必要としたのかなど、メディアを利用しながら、実際には翻弄もされる女の子たちが見えてくる。「考えてみよう」「調べてみよう」「話し合ってみよう」などと、研究の指針が示されているのも親切じゃないか。
「ワンダーウーマン」「キャプテンマーベル」などの映画から、表彰としての女性とフェミニズムとの関係を分析したり、ビヨンセやレディ・ガガなどを上げながらポピュラー・ミュージックにおけるジェンダー表象の読み解き方が解説されたり、90年代に起きた女子高生ブームの男性研究者による調査や分析をさらに分析する。
好きなのは後半の「交渉と実践」のパートだ。アート、ダンス、ファッション、ジンの製作、社会運動を取り上げ、それぞれ、実践の場所の現状や先人の試みが紹介されている。たとえば美術展では女性客が圧倒的に多く、美大でも女子学生が多いにもかかわらず、日本の美術界ではジェンダー不平等がまかり通っている現状や、それでも表現としてはフェミニズム的な発想が増えていたりすることや、「ジン」と呼ばれるようなミニコミ出版物を作るときのたくさんのヒント、あるいは社会運動のはじめ方など、現実に役立てられそうな知識が詰まっている。
じつは私も学生のころ、女子学生だけでミニコミペーパーを作っていた。ウーマンリブが「怖いもの」と言われていたポストフェミニズム的な80年代初頭の気分をそのまま写しとった、つまり「大卒女子が子供を産んだ後も雇われ続けるために、“女には” 何が必要か」「企業は社員を能力で評価してほしい」「雇われるためには女も意識を高くしなきゃ」みたいな、まさしくその後の新自由主義経済を待望するかのような内容だったが、(短大ではなく)4年制大学に行くことでかえって就職しにくくなると言われていた時代には切実なテーマだった。で、そのミニコミには当時できたばかりの人材派遣会社や、育児休暇制度を作ったばかりの百貨店などがけっこうな額の広告費を出してくれていた。女子学生が企業社会での性差別解消を訴えるミニコミに、企業が広告を出すのだ。企業と「交渉」しているような気持ちでいたが、どうだったんだか。──「ポストフェミニズムにおいて「女」はネオリベラリズム時代の労働者の特権的なシンボルとして立ち現れているためである。たとえば、今ではネオリベラリズムとそれに基づく市場原理主義によって、全ての労働者が柔軟な自己管理、つまり自身の身体を他者化・対象化・商品化することを求められるようになってきたが、これは「女らしさ」においては歴史的に今までもずっと求められてきたことである」。まったくだ。
テーマとしては馴染めないながらもおもしろいと思ったのは「メディアをまとい闘うBガール」という章で、男性的な空間である「ストリート」の考察だ。確かに映画「スケート・キッチン」を観ると、アメリカでもストリートは圧倒的に男子のものだった。80年代のたけのこ族では女の子もたくさん見かけたのだけどなあ。スポーツとジェンダーやフェミニズムの問題は五輪を機に話題も増えていたが、女子が学校などの管理下にいて、男子がそこから押し出されてストリートに出ている可能性が考察されている。そのことと、ダンスという文化の根幹にある「まなざし」による権力関係との関わりをはじめ、Bガールたちのファッションや音楽との関係など、興味深い。
メディア文化とはいえ、しばしば、心ならずもいつのまにか、若い女は見られる存在となっている。自分は見る側だと、主体的に活動しているつもりでいるのに、気がつくとどこかから、誰かから見られる側になっている。90年代の「女子高生」も80年代の「女子大生」も、勝手な視線で勝手にまとめられていて、どちらも「まとめて語るな」と怒っていた。
この本からは、たとえば「見られること」を対象化する方法、見る/見られる関係を更新する考え方なんかを体得するツールがなにか見つかるだろう。加えてもう一息の自粛生活で、しばしご無沙汰だった「外」が拡がるかも。
水越真紀
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE