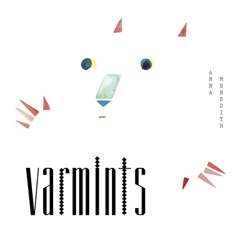MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Drums- The Drums
シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界』......20世紀初頭の富裕なユダヤ系批評家が、その晩年に記した回想録だ。そこには戦前のヨーロッパの、香しく華やかにして洗練を極めた文化への追憶が、無量の感激、そして絶望とともに綴られている。大戦とそれが生み出した新しい秩序によって損なわれ、もはや二度と戻ってはこない"昨日の世界"。振り返られるものがことごとく美しいように、彼の筆になる"昨日の世界"も甘美だ。いや、彼らの時代の彼らの文化がもっとも美しいのだという気にさえなる。しかし過去の描写が冴えれば冴えるほど、彼自身が現実に対して抱いていた絶望の深さに思い当たって慄然とする。
というのはいささか大げさな前置きではあるが、ザ・ドラムスは"昨日の世界"を生きるバンドだ。それは昨今の安易なレトロ・ブームとは一線を画する。リヴィング・シスターズのようなモータウンのコスプレとも、モーニング・ベンダースの無邪気な懐古趣味とも違う。もっと徹底した"いま"への嫌悪がある。かといってお家芸的にヘヴィ・サイケを追求するデッド・メドウズその他のように、現実の向こう側へ突き抜けてしまった人たちでもない。そして、心からこの世に居場所のない、さまよい傷ついた魂を抱えてレイド・バックした詩人たち......アリエル・ピンクやガールズとも画然と異なる。
彼らは一級の役者だ。徹底的に"昨日の世界"を構築し、生き、魅せる。音にもヴィジュアルにも隙がない。彼らのアーティスト写真を見て誰がいまのバンドだと思うだろう? ネオサイケの耽美な憂鬱を溶かし込んだ、鈍いモノクローム。あるいはポスト・パンクのぎらぎらとしたモノクローム。カラー写真も、ネオ・アコースティックへのオマージュあふれる構図を持ちながら、どこかテクニカラー・フィルムを思わせたり、トイカメラ風の濃厚な発色を強調したものが多い。かのエディ・スリマンも彼らに惚れ込み、ホモソーシャルな視線が織り込まれた美しいモノクロ写真を撮っている。これは彼の公式ホーム・ページで見ることができる。
音もしかりだ。50年代のサーフ・ポップ的なモチーフを湛える一方には、〈ファクトリー〉初期の諸バンドにまたがるような......マーティン・ハネットのプロデュース・ワーク、あるいは同時期のグラスゴーにおける最重要バンドのひとつ、オレンジ・ジュースを彷彿させるヴィンテージなブリティッシュ・サウンドが鳴っている。それでいて曲自体はなんら屈折のない、いや、でき過ぎなくらいシンプルな2ミニット・ポップ。「起きて、ハニー。素敵な朝だよ。ビーチへ駆け出そう」
以前ミニ・アルバム『サマー・タイム』のレヴューでも書かせていただいたが、とにかく彼らは"いま"という問題設定や、等身大のリアリティを歌い上げるというポップ・ミュージックのひとつの使命を、そんなものは無粋とばかりにことごとくキャンセルしてしまう。そして颯爽と黄金律のソング・ライティングを開陳する。フックの効きまくったメロディはいつまでも耳に残る。中途半端なもの、ダサくて格好の悪いものは排除され、徹底した美意識によってトータルなバンド・イメージがコントロールされる。彼らはほんとに頭がいい。
いや、だからこそ「なんて嫌味なバンドなんだろう」と煙たく感じたものだった。もっとリスキーな音で未来を切り拓こうとしているバンドがいくらもいる。しかし、私が根負けしたということでいい。やっとフル・アルバムのリリースとなったわけだが、このあいだにザ・ドラムスの存在感がさらに大きなものとなってしまって驚いている。『NME』などUKのメディアから火がついたことも大きな要因だろうが、国内盤の帯には「2010年最大の話題」と謳われ、久しぶりにテレビをつければプジョーのコマーシャルに使用されているという具合だ。使用曲はベースの軽快なリフに口笛が印象的なミニ・アルバムの顔、"レッツ・ゴー・サーフィン"。フル・アルバムでもこの曲がハイライトになるだろうと思ったが、さらに強力なシングル曲がきっちりと1曲目に据えられていて、唸るしかなくなってしまった。バンドの核であるジョナサン・ピアース、そして相棒ジェイコブ・グラハム(実質的にザ・ドラムスとはこのふたりのバンドだ)の名がクレジットされた"ベスト・フレンド"は、朝聴けば1日中頭を回りつづけるだろう。この曲もまた、小躍りするようなベースとドラム・ビートを持っている。ピアースのクセのあるヴォーカル。メロディは彼らしいアディクショナルなリフレインを伴って耳に絡みつく。
だが、どんなにたわいもないことを歌っているのかと思えば、この曲のテーマは友人の死だ。もっとも大切な親友を失い、毎日思いつづけ、待ちつづける......「ぼくはどうやって生きていったらいいんだろうか」――詞には"アイ"の他は二人称"ユー"しか用いられず、相手が男性か女性かも判然とはしないが、曲調が度外れに明るいことが、詞の悲痛さを際立たせる。結びはこうだ。「ぼくは、ぼくがそれでも生きていくだろうということを知っている」
ザ・ドラムスにいまと未来への諦念があることは、私には間違いのないことのように思われる。ネオ・アコースティックなときめき感たっぷりの、甘美で胸躍るポップ・ソングというのは完璧な構築物だ。なぜならこの世界は「きみ」がいない世界だから。特定の人物でなくてもいい。彼らにとって大事ななにかを欠いた世界。だからこそ"昨日の世界"が歌われる。むしろそのような負の力がなければ、これほどブリリアントな曲は生まれないかもしれない。では、どうして世界を忌避しながらも歌うのか。「ぼくは、ぼくがそれでも生きていくだろうということを知っている」からだ。答えは"ベスト・フレンド"、冒頭曲にすでに記されている。
フル・アルバムは、ミニ・アルバムに比べればエッジが取れている印象だ。その分聴きやすいかもしれない。ジャケットも比較すればメジャー感が増している。フロリダの小さなマンションから生み出された、この哀しくも完璧なパントマイムが、世界という大きな舞台で試されようとしているのだ。見届けよう。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE