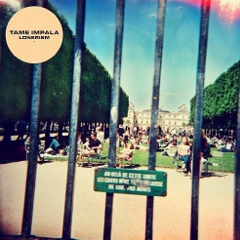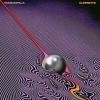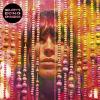MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Tame Impala- Lonerism
彼らのはじめてのEPが出たころ、クリスタル・アントラーズやオール・ザ・セインツなど〈タッチ・アンド・ゴー〉の最後を飾ったアーティストたちも同じようなヴィンテージ・サイケを展開し、ウッデン・シップスのデビュー作のリリースによってドゥンエンらへの関心も再度高まりつつあったところへ、南アフリカからブラック・ジャックスが出てきてカオッシーなエネルギーを吹き込むなど、スペーシーなジャム・バンドやガレージ・サイケの系統は、ちょっとした盛り上がりをみせていた。
エレクトロなイメージが定着していた〈モジュラー〉が、テイム・インパラのような音をリリースするというめぐりあわせにも時代の見えざる手を感じ、すくなからずときめきもした。あのEP『テイム・インパラ』の薄いスリーヴを手にしながら「キタな」とか「零サイケと呼ぼう」とか「13thリヴァイヴァルとかもこい」などと思っていたのが懐かしい......もはやくるもこないもない、5年を経て、いよいよあらゆる音楽が横一列に並んで享受されるようになり、リヴァイヴァルの意味など漂白されてしまったように見える。特定のものが蒸し返される背景には、時代を支える無意識ではなくて個人的な動機が存在するだけだ。「古いモノから新しいモノを創り出すのは僕らの世代にとって重要な要素だよ」と言うのはマシューデイヴィッドだが、リヴァイヴァルの連鎖で終わった先の10年を考えるときにこの言葉は重い。「どの」ムーヴメントを蒸し返すかは本質的な問題ではなく、そこから新しいものを引き出すことに焦点を当てた発言である。あとは空気を読まずに好きなものをやりつづけるか、読みに読んで流行ゲームを組織するか、どちらを好むかという選択の問題が残るだけだ。前者に与えられるチャンスが相対的に肥大した現在は、もしかすると音楽にとってはいい時代なのかもしれない。
ともあれ、べつにわざわざ彼らを「ガレージサイケ・リヴァイヴァリスト」と呼ぶでもないなという状況の出来において、ようやく彼らの「セイム・インパラ(いつも同じじゃん? という彼らの楽曲への揶揄)」は、その一貫したフィーリングをあるがまま楽しみ、評価できるものになった。冒頭では13thフロア・エレベーターズやウッデン・シップスを引き合いに出したものの、そうした際限なきジャムの酩酊感よりは、ゾンビーズや『サージェント・ペパーズ~』などの英国的な翳りやソフトなサウンド・センス、またポップスとしての洗練に彼らの妙味があることが、いまではより見えやすくなっている。サイケデリックな音楽性を減速せずにポップスへと落とし込むことに長けたデイヴ・フリッドマンが前作に引き続きミックスを担当、あのにぶく爆ぜるような生々しすぎないローファイ感は、"アポカリプス・ドリームス"や"キープ・オン・ライイング"などの物憂げでしっとりとした、いかにも彼ららしい歌メロをクールに引き立てている。"エンドアズ・トワ"のヴァニラ・ファッジ的なオルガンの展開も現代性を帯びて聴こえる。"デザイア・ビー・デザイア・ゴー"を長らく愛してきた筆者にとって、そして多くのファンにとって、こうした曲はいずれもあらたな愛聴トラックとして記憶されることになるだろう。彼の音作りは、ダイナミックにファズを聴かせる"マインド・ミスチーフ"においても生きてくる。ラフすぎない、なんともシックなファズ(という形容矛盾をスマートに成立させるところもにくい)が、ベースのファンキーなグルーヴを個性的にドライヴさせていく。
一方で、発展形としてはぜひとも"ナッシング・ザット・ハズ・ハプンド""サンズ・カミング・アップ"を挙げたい。前者で聴かれるアナログ・シンセには彼らなりの冒険があったはずだ。ケトルの、あるいはエイフェックス・ツインの叙情性とヴァニラ・ファッジやドアーズのハモンド・オルガンが交差するような、スリルある1曲。彼らの引き気味なスウィングもばっちりときまっている。酩酊ではなく叙情へとサイケデリアを操作する、本作のなかでももっとも果敢な姿勢を感じさせる名曲である。そして終曲のワルツにおいて強調されるアップライト・ピアノの質感、そしてジョン・レノンを彷彿させる節回し、ラフに挿入されたフィールド・レコーディング、ぐるぐると左右の耳を巡回するようなリヴァーブには、あきらかにノスタルジーとは異質の過去への飛翔がある。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE