MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Akron/Family- Sub Verces
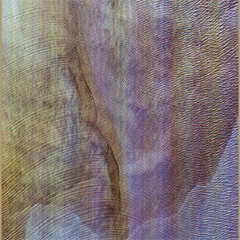
自由になれ......でも、何から? その質問を、バンドはいったん無効にする。アクロン/ファミリーといえば、『セッテム・ワイルド、セッテム・フリー』のときに掲げられたデタラメな星条旗だ。それは彼らの雑食的にデタラメな音楽の表象であり、そして、デタラメに生きることの提案を暗示しているように思える。デタラメに生きること......そう口にしてみたところで、それを具体的にイメージできる人間は日本には少ないだろう。アクロン/ファミリーが日本でも人気が出たきっかけはあの祭のようなライヴで、僕もその熱狂に浮かされた人間のひとりだが、そのとき強烈に感じたのは彼らが誰よりもデタラメに生きることを実践し謳歌しているように見えたからだ。『ピッチフォーク』はそんな彼らがまとうものを「アーバン・ヒッピー・オーラ」だと書いているが、なかなか気の効いた表現だと思う。アーバン・ヒッピー。都会でボヘミアンとして漂泊する人びと......ライヴで彼らは、じつに能天気なやり方でそのコミュニティに勧誘しているようであった。厳密さに欠いていてもいい、というか、むしろそんな大雑把さでこそ得られる奔放さというものがあるのだろう。それは伝聞での60年代の記憶によるものかもしれないし、彼らのアンダーグラウンドへの思慕によるものなのかもしれない。
トライバルというよりは呪術的なイントロではじまる"ホーリー・ボアダム"(聖なる退屈)、あるいはアッパーで大らかなノイズ・ミュージック"サンド・タイム"などによく表れているが、アクロン/ファミリーの通算7枚目となる『サブ・ヴァーシズ』は、彼らがアンダーグラウンド・シーンに置くシンパシーを素朴に抽出したアルバムだ。情報としては、プロデューサーがサンO)))やアース、ボリスらを手がけたランダル・ダンであり、ジャケットのデザインを担当しているのがサンO)))のスティーヴン・オマリーだということで、なるほどたしかにドゥーム・メタル人脈の影響がそこここに出現しているとも言える。ただ、ここにはそれ以上に雑多なジャンルが相変わらず渦巻いており、サイケデリック・ロック、フリージャズ、フォークにブルーズ、アフロにファンク......そういったものが整頓されずに、しかし熱をこめて投入されている。ただ言えるのは、ノイズ・ミュージックからの影響がこれまでよりも強く出ており、彼らの出自である〈ヤング・ゴッド〉のオーナーのマイケル・ジラの名前を連想させる。スワンズの昨年のアルバム『ザ・シア』と並べて聴いてみると見えてくるものがあるだろう。アクロン/ファミリーがかつて分類されていたフリー・フォークやブルックリンといった記号はもはや完全に過去のものになりつつ、同時に彼らのいち部となりその血に流れている。
いっぽうで"アンティル・モーニング"や"ウェン・アイ・ワズ・ヤング"では、彼ららしい朴訥で美しいメロディやハーモニーが聴ける。僕が思うに、アクロン/ファミリーの音楽では野外のキャンプで演奏されるようなコミューナルでスウィートな瞬間というものが絶対に欠かせない要素になっていて、そこがハードコアな実験主義者たちとアティテュードを緩やかに画するところである。本作でもスピリチュアリティを思わせる言葉は随所に並び、そしてそれこそが一貫して彼らの表現のコアとなっている。"サムライ・ソング"でアルバムはドリーミーに、サイケデリックに終わっていくが、そこで歌われる精神世界は持たざる者が抱くポリシーのようなものだ。「財産がなければ 僕の運命が財産となった/何も持っていなければ 死が僕の運命となった」......何も彼らはモノを全部捨ててヒッピーになれと言っているわけではない、が、お前の精神が自由になれる場所を探せとずっと言い続けている。そしてそれを、分かち合うことを忘れない。
だから"ホーリー・ボアダム"はライヴでめいっぱいアンセミックに演奏されるだろう。「怒りさえすれば 僕らは叫ぶことができる/大きな声で もっと大きな声で/好き勝手にやるために!」......それは、アクロン/ファミリーの音楽において押しつけがましい教条ではなく、純粋に僕たちの快哉である。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE


