MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ryoji Ikeda- Supercodex
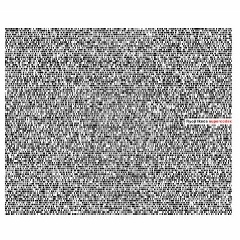
「レコード盤、楽曲の思考、楽譜、音波、これらは互いに、言語と世界の間に成立する内的な写像関係にある」(ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』野矢茂樹・訳)
耳を貫くような高音のパルス音が鳴りはじめる。強烈な電子音響が炸裂する。タイプライターのような細やかなリズム。モールス信号の微かな音の断続と持続。音響が震動し分裂する。加速し、炸裂し、震動する。音は意味を剥ぎ取られ、データの素粒子へと還元していく。光のレントゲンのなかで極限まで剥ぎ取られた電子音が身体に注入される。0と1。そんなデータに還元された極限の音響が鼓膜や脳を揺らす。その圧倒的な音響の快楽。あらゆる意味を超越して、ただただ快楽的な電子音饗の群れが、耳を、鼓膜を、脳にアディクトする。刺激・律動・数・美。第二次世界大戦末期、国防軍最高司令官の最後の戦況レポートを記したタイプライターの文書が焼け焦げていたように、言葉など、もうすでに消失してしまった。
そう、池田亮司の新作アルバムのことである。
池田亮司の新作CDが〈ラスター・ノートン〉からリリースされた。前作のCDアルバム『テストパターン』の発表が2008年だから、約5年後ぶりの新作アルバムということになる。この作品は、〈ラスター・ノートン〉からリリースされた『データプレックス』(2005)と『テストパターン』に続くシリーズ完結編というが、聴いた印象はそれらとは全く「違う」。『データプレックス』と『テストパターン』のスタティックな反復とは違う、2011年のcyclo.『id』の音響を受け継ぐような、ノイジーでありながらもクリスタルな響きとロック的とも形容したい刺激と律動が横溢している。まさに2013年の池田亮司作品である。
特に注目したいのはアルバムの中盤に突入してからだ。音響は次第に具体性を確保し、ミニマル/ストイックな音響から次第にノイジーに変貌する(特に12曲目と14曲目がすごい)。そしてそれは15曲目において決定的になる。1曲目の音響を変奏するように、モールス信号が流れ始める。あの初期の池田作品にも横溢していたあの信号音だ。そこにランダムなリズムが重なり、さらに高音のパルスへと変貌する。16曲目では、そのサウンドが低音に融解したような印象である。信号はより抽象的になる。
そして本アルバムでもっとも驚愕すべき17曲目に突入する。クラッシュするような電子音が何度か繰り返され、まるで戦闘機の爆撃音のような音響が驚異的にグリッチ=打撃されていく。途轍もないサウンドだ。冷凍されたノイズの拡張のような、クールにして限界を超越するような音響。デジタル化した地響きが現実に解凍されていく感覚。18曲目ではまた、低い音響のモールス信号。19曲目ではその低い音が維持したまま、何がクラッシュするような音に、細かな一定のリズムが刻まれる。そしてその低い響きが次第に蠢き方を強め、突如、ミュートされる。その音響運動のなか、小さな音でリズムは刻まれ、透明な音もまた微かにリズムを刻むだろう。そしてラスト20曲目。サウンドは地を這うような音響の蠢きへと突如、変貌する。まるで人間の終わりのような音響。もしくはテクノロジーのエラーから不意に表出した現実のような音響。私には、本作を近作2作の完結編というよりも、むしろ『1000フラグメンツ』(1995)、『+/-』(1997)、『0℃』(1998)までの変化の過程へと拡張的に円環し、そしてさらに大きな外部へと接続していくような印象を持った。では何に円環し接続したのか。それは20世紀の世界を覆った膨大な通信と情報の層に、ではないか。
音楽そのものをゼロ地点への響きへと導いた弦楽作品『op.』(2003)以降、00年代の池田亮司は、20世紀の世界を覆う膨大な情報網、つまり通信から情報へ、そしてデータへと圧縮/拡張していく世界を、インスタレーション、ライブ、CDと多角的に作品化してきた。それは圧倒的な体験の生成であり、同時に、ある種のメディア論のような論理的で論文のようであり、世界のすべてをスキャンし、指令を下す戦争の音響=イメージのようでもあった。
モールス信号、電話、放送などの通信から、インターネットのデータ回線への情報へ。20世紀と21世紀の世界を覆った膨大な通信と情報。その拡張し続ける回線のなかに行き交うのは、人の言葉である。それらは通信の回線のさなかにおいて行き先すらわからない単なるデータの群れであり、言葉の残骸ですらあるだろう。だが、もともとは人間が発した「声」なのだ。ある人間に向けて発せられた「言葉」である(先日京都で公開された最新作『スーパーポジション』において池田亮司は、ふたりの人間を舞台に登場させたという。ふたりは楽器を演奏することなく、モールス信号のようなものを打つ。このふたりは何かメッセージを送っているのか。それとも全く別の何かに向けて通信しているのか)。その無数の「声」にはその送り主である「人」がいるはずだが、しかし、私たちにはその「人」の存在を知ることはできない。人間はその情報の加速度的な層の拡張の中で、まるで波打ち際の砂のように、その存在を消し去っていく。数値化された膨大な情報/データの向こうに、確かに、ひとりの(つまり無数の)人間たちがいた。人間の消滅。人間の終わり。
人間の終わり? 量子力学の概念を援用した数学的な音響の向こうで、確かに、確実にそんな響きの痕跡や残響が微かに鳴っている。聴こえてくる。このアルバムはまるで、戦闘機の通信士に送ってくる「本部」からの「サイン」のようだ。言葉はモールス信号のように変換され、タイプの音がリズムに拡張され、それら全体がひとつの信号=音響となる。そこにおいて言葉、つまり意味は徹底的に剥ぎ取られ、記号と音素が交錯するレントゲンのごとき電子音響が鳴り響くだろう。いわば人間の終わりからの言葉。情報へと変換された言葉たち。それは世界を覆う情報システムとそのデータの群れ。池田亮司はそんな通信/情報のデータの速度を、徹底的に数学的/物質的音響作品として一気に圧縮/解凍させていくのだ。
2013年の池田亮司は、その20年もの創作活動で得た方法論を全て駆使し、圧縮し、解凍し、炸裂させ、まるで電子音楽における無言のレクイエムのごとき作品を作り出した。本アルバムラスト20曲目の音響は、まさに人間の終焉、その音響であり、予言である。その意味で池田亮司の作品は「神」の音楽に限りなく近い。こんな途轍もない作品を生み出した池田亮司はいったいどんな地平へと行き着くだろうか。凡人の思考など遥かに超える地平がそこにあるに違いない。
いま、ここに池田亮司の創作と思索の結晶がCDとしてある。その名は『スーパーコーデックス』。超越的アーカイブ。このCDは情報と記憶と音響のモノリスだ。いうまでもない。「世界」は、ここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE


