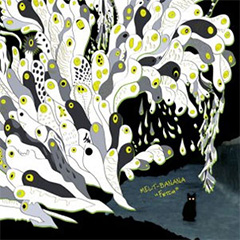MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Melt-Banana- Fetch
本作のリリース前からニュースなどでこのバンドに対して使われている「ノイズコア」という形容にどうもひっかるものがあるのは理由がいろいろあるのだが、まず第一には彼らの演奏はノイジーではあるけども、極めてコントローラブルで再現可能なものなので、「ノイズ」という形容が適切とは思えないという点がある。彼らの演奏は初期のころから一貫してインプロヴィゼーションの要素はかなり少ないはずだ。
もう一点としては、彼らの出自がハードコアではないという点にある。ハードコア系の企画に出演することは多いが、決してハードコアシーンに属しているわけではない(あるんですよ、シーンっていうのは厳然と)。
もともと、彼らのルーツはポストパンクやニューウェイヴにあり、初期からのトレードマークであるスライド・ギターは『ノー・ニューヨーク』収録のティーンネイジ・ジーザス&ジャークスにヒントを得ているし、前身バンドを見たことのある人によれば当時はセックス・ギャング・チルドレンやバースデー・パーティなどのニューウェイヴ/ポジティヴ・パンクの影響を感じさせるサウンドだったという。
94年にリリースされたゼニゲバのK.K.Nullのプロデュース、スティーヴ・アルビニの録音によるファースト『Speak Squeak Creak』で聴けるのはたしかにそうしたポストパンクを高速化したようなサウンドで、スライドギターの多用によりグニャグニャなのに金属的、という独特の感触がある(ところで彼らがずっと精力的に海外ツアーをおこなってきたのは、初期の時点でゼニゲバの姿を見ていたことも影響しているのではないかと思う)。
当時のドラマーの須藤俊明は自身のドラムスタイルについて、ロバート・ワイアットの影響を受けていると発言している。たしかにいま聴いてみると、ハードコアのドラムとはまた違った、手数の多いドラミングである。
95年のセカンド『Scratch or Stitch』(前作に続きアルビニのプロデュース、録音はジム・オルーク)も前作の延長にあるサウンドである。この時期にMr.Bungleのオープニングアクトとしてアメリカツアーを行ったことで一気に海外での知名度が上がったと思う。あと、須藤が現在ジムのバンドのメンバーになっているのはこの頃からのつながりなんでしょうね。
90年代中頃のハードコア・シーンではファストコアとかパワーヴァイオレンスと呼ばれる「速さ」を重視したスタイルが盛り上がっており、メルト・バナナも内外でそうしたバンドと共演する機会が増えてくる。そんななか、須藤が脱退し、元サタニック・ヘルスローターのオオシマが加入(現在はWatchman名義のエレクトロニカ・ユニットで活躍している)。サウンド面では一気にハードコアに接近する。ジョン・ゾーンのレーベル〈Tzadik〉からリリースされたライヴ・アルバムは1〜3枚目までのベスト的な選曲になっているので、ノリの違いを聴き比べても面白いと思う。
そんなオオシマも4枚目のアルバム『Teeny Shiny』を最後に脱退。以後、固定ドラマーを持たないまま彼らは活動を続けることになる。日本国内と海外でドラマーを分けて活動するというスタイルには何らかの苦労がうかがえるというか、「これからのバンドは海外活動に目を向けるべきだ」みたいなことはよく言われてるけども、ツアー中心の生活ってのはなかなか誰にでもできるってもんでもないんだろうな、という気にさせられる。
2003年の5枚目『Cell-Scape』で急激にサウンドがエレクトロニックな印象になるのは、固定ドラマーがいなくなったことも関係あるのではないかな、という気はする(まあ単純にギターのエフェクターとかが大きいんだけど)。
その後、サンプラーを使った打ち込み版メルト・バナナともいうべき「Melt-Banana Lite」というユニットでの活動を平行して行うようになり(Liteによるライヴ・アルバムもリリースされている)、ついにはオリジナル・メンバーのベーシスト、Rikaが脱退。以後、ヴォーカルのYakoとギターのAgataのふたりとなったメルト・バナナは、ベースもドラムもすべて打ち込みという形での継続を選択した。
とまあいろんなことがあって、ふたりとなったメルト・バナナの初めてのアルバムとなった『Fetch』がリリースされるには、実に8年というブランクがあった。そんなブランクにも関わらず、先行無料ダウンロード・トラックが『Tiny Mix Tapes』での配信だったのをはじめ、発売に際しては多くの海外メディアで取り上げられているのは、その間も毎年精力的なツアーを怠らなかったことによるものが大きいだろう。
打ち込みになったとはいえ急にEDMとかダブステップになったりするわけもなく、基本的にはバンドサウンドを再現することに注力されているのだが、やはりここ数年来のサウンドの延長で極めてエレクトロニックな感触である。冒頭の話題に戻るけども、メルト・バナナがノイズ的と言われるのはおそらくはギター・サウンドが極めてギターっぽくないからなんじゃないかと思うのだが、むしろエレクトロニック・ミュージックの攻撃的な電子音を聴き慣れた耳には普通に「楽音」として捉えることが可能なんじゃないかと思う。エレキギターの可能性を縦横に拡張し続けているAgataの尽きることないアイデアにはいつも感服する。
あと、ハイトーンのシャウトを基調とした女性ヴォーカルってなんとなくヒステリックな印象を与えがちなのだけど、Yakoのヴォーカルは常にどこか情念みたいなものを排した感じがあるので、(録音のせいもあるけど)わりとプラスティックな印象をあたえる。この辺も、エレクトロニック・ミュージックと近い感触のもとになっていると思う。
個人的には何より驚いたのはふたりになってからのライヴである。ステージ後方にずらりとアンプが並び、確認したわけではないがおそらくドラムとベースと、それぞれ別系統でスピーカーから音を出している。ステージそでにラップトップが置かれているが単にトラックを流すのではなく、Yakoが片手にコントローラーみたいなのを持って操作している模様。リズムトラックにギターと歌を乗せた演奏って録音はまだしもライヴだと音色面や「ライヴ感」みたいな部分でどうしても不満が残りがちなんだけど、彼らの演奏に限ってはそういったことはほとんどなかった。
こうして振り返ってみると、中心になるふたりは不動ながらもメンバーチェンジがしっかりサウンドの変化に結びついていることがわかる。今作は『Cell−Scape』以降の集大成のようなアルバムになったと思うが、今後ふたりになったメルト・バナナが今後さらにエレクトロニックになっていくのか、はたまた新たにベーシストやドラマーを迎えるのか。いずれにしてもとても楽しみだし、彼らを見ているとロックにはまだまだできることがあるんだなあと思えて、とても嬉しい。
大久保潤
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE