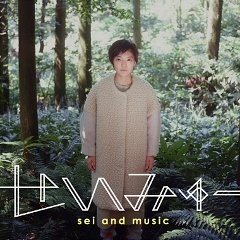MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > sei and music- せいみゅー
サイレント映画で役者の声を音もなく聴くように、音盤を前にした聴取者が目にするのは歌声が喚起する身体性、つまり肉声を通してたち現れる歌い手の姿である。レコードという「聴くこと」がそのまま「居ること」であるような環境から脱して音を日常的に持ち歩くことができるようになったわたしたちは、しばしば物質的なイメージに囚われることなくそうした姿と出くわすことになる。だから機械仕掛けの「声」でさえ生身の肉体と同じだけの強度をもって現前するのだ。しかしながら歌い手と作り手という親密でミニマムな関係の上に構築される身体のことを考えるとき、ひとつの声がひとつの楽曲と撚り合せられることで他者性を確保しながら極限まで純化されたひとつの身体が生まれることを考えるとき、合成音声装置が跳梁跋扈する現代社会において肉声がなし得ることのひとつには、この純化された身体の唯一無二性を示すこと、同一人物であっても再現不可能な身体性を喚起し続けることがあるのではないだろうか。その意味でこの二者関係とはシンプルな形態でありつつもすぐれて現代的なものなのだと言えるだろう。
sei and musicはヴォーカリストseiのソロプロジェクトである。彼女は2003年に「のっぽのグーニー」としても知られるコンポーザー・田中淳一郎とju seiというユニットを結成し活動を行ってきた。そこで魅せる歌声は旋律的なものから声と音の境界をゆくものまでさまざまであり、先の考えを踏まえて言えば複数の身体がひとつの肉体に同居しているかのようでもある。しかしこのユニットが生まれるきっかけとなったのは「のっぽのグーニー」の音源があったからだとsei自身が述べるように、ここでわたしたちの眼前に現れるのはひとりの女性が田中淳一郎の才能によって彩られた姿、ある肉体がみせる種々の素振りなのではなかろうか。それは肉声というよりも音声を操作することによって形づくられた楽曲のありようであり、いわば声というものを道具として用いることで編みあげられたアンサンブルなのだ。ある人物に固有な歌声を音楽の要素として駆使すること、それは電子的な「声」と同じ土俵の上に立って楽曲を創出するすぐれた試みではあるものの、歌い手が作り手と溶け合うようなこの場所において聴こえてくるのは音声の清々しさなのであって肉声の生々しさではない。
このように考えたときソロとして最初にリリースされた本作品とju seiのあいだに横たわる断絶を、前者が徹底的に旋律的であること、どこまでもポップな歌モノとして構成されていることにこそ見いださねばならない。肉体そのものが楽曲という完結した入れ物に押し込まれることによって生まれるのは客体化しえないひとつの歌声であり、そこから紡ぎ出されるひとつの身体であるからだ。聴かれるように本作品に収められているのは辺境の音楽ファンを唸らせる11人の作曲家の各々がseiと取り結んだ濃密な関係性である。楽曲はそのどれもが趣を異にしており、往年の歌謡曲を思わせるものもあれば昨今のポップ・ソングを模したようなものもある。それらに寄り添うようにして吹き込まれたseiの歌声はひとつとして同じものがなく、まるで複数の歌い手が参加しているようでもある。しかしながらすべての楽曲はあくまで歌唱として構成されており、ju seiにおいてみられたような歌い手の固有性は、ここにおいては誰もが繰り返すことが可能な形式の中で際立つ歌い手の独自性となっている。
興味深いのはそうした多様な歌声がそれぞれどこか既聴感を伴ってあらわれているということだ。戦後日本に滔々と流れる女性ヴォーカリストの系譜を拾い上げるようにして表現された歌声の数々は、楽曲と共犯関係を取り結ぶことでより馴染み深い顔立ちをみせる。それに立ち会うとき、まず目にするのは私わたしたちの記憶を身に纏ったseiの佇まいであり、次に訪れるのはそれを剥ぎ取ることで明瞭となる彼女にしかあり得ない身体のありようなのだ。ここに生々しさがある。それをイミテーションと呼ぶにはあまりにも彼女の個性は強い。だからユーモアよりもさきに官能が訪れる。引用の美が異化効果にあるのだとすればここにあるのは圧倒的な純度の身体がもたらす美しさ、それも複数に分裂してみせるしなやかな肉体のあらわれなのである。わたしたちはこのアルバムでseiに潜在する能力の奥深さを知る。ならば幾年か経ったのちにこの稀有な歌い手の里程標として振り返ることができるように、この音楽を記憶にとどめておく必要があると思われる。
細田成嗣
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE