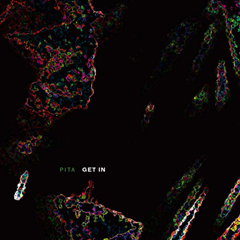MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > カフカ鼾- Okite
(1) ジム・オルークにとって音楽は、大きく3つのタームに分けられる。1.実験音楽、2.即興音楽、3.ポップ音楽である。オルークはこの3つの領域を横断しながら、ときにミックスするように、ときに全く別の次元で演奏するように作品を生みだしてきた。この3つはそれぞれオルークのアルターエゴを形成するものでありながら、同時に彼そのものであった。「ジム・オルークの考える音楽のすべて」だ。
(2) そして、ジム・オルークにとって音楽の歴史はすでに終わったものである。それが彼の強烈な批評性であり、音楽への愛の証といえよう。過去にこれほどまでに厖大で素晴らしい音楽がある以上、新しい音楽など作る意味はあるのか。ジョン・フェイヒーもデレク・ベイリーも、レッド・ツェッペリンもヴァン・ダイク・パークスも、高柳昌行も小杉武久も、武満徹もメルツバウもすでに存在するのに、いまさらどんな音楽を作れというのか。
(3) 同時にジム・オルークは音楽家である。彼は批評家ではない。新しい作品を作り、演奏をする人間だ。先の批評性は、強烈な自己批評性へと転化し、その矛盾を乗り越えようとする動きが彼に音楽を作らせる。どんな楽曲を作るべきか。どんな音を奏でるべきか。ソロ名義のアルバムが00年代以降、急速に減っていくのも、自己批評性・自己吟味の表れであり、00年代以降、インプロヴィゼーションやコラボレーションが増えてくるのも、即興や共闘こそが新しい音楽が生まれ出る可能のひとつとジム・オルークが認識しているからだろう。たしかに、出会いと即興は同じことを繰り返してはいけない。そこでは反復すら反復ではない。
2014年早々、カフカ鼾のアルバム『Okite』が発表された。カフカ鼾は、ジム・オルーク(シンセ・ギター)、石橋英子(ピアノ)、山本達久(ドラム)ら3人によるインプロヴィゼーション・バンドである。彼らはカフカ鼾結成以前から別バンドやユニットなどでレコーディングを繰り返していたが、その活動のなかで自然発生的にカフカ鼾として録音するようになったという。バンドキャンプに2012年頃の音源も上がっているので必聴である。また、オルークと石橋、山本に、須藤俊明、波多野敦子、千葉広樹を加えたマエバリ・ヴァレンタイン(!)も活動中だ。
本アルバム『Okite』は、2013年6月にジム・オルークが自身の音楽歴を総括する連続コンサート〈ジムO 六デイズ〉におけるカフカ鼾のライヴ録音である。同コンサートは初期の実験音楽から名作『ユリイカ』なども含めたオルークの音楽活動を総括したもの。そのコンサートのなかでカフカ鼾はオルークの新バンドとして登場し話題を呼んだ。オルーク自身も6日間に渡るコンサートのなかで最も思い入れが強い演奏と語っている。その後、彼自身がミックスを手がけ、アルバムとして完成した。
言うまでもなく本作は、先の3つのタームでいえば即興音楽の部類に入る。事実、石橋英子の硬質なピアノ、微分的にリズムを刻む山本達久のドラムに、ジム・オルークの微かなギターとシンセが絡み合う38分間の濃密なインプロ演奏を記録した盤である。石橋のミニマル/リリカルにして鋭利なピアノはその都度、新しい音楽を生成し、山本の常人には絶対不可能なリズムの分割感は、他にはない圧倒的なグルーヴを演奏に与えている。そんな超絶インプロヴィゼーションの横溢のなかで、まるでスティーヴ・ライヒとシャルルマーニュ・パレスタインが衝突しあうような驚異的な音楽が生まれているのだ。
そして、ジム・オルークの演奏は、彼らの演奏のあいだに、もしくは違う層に存在しているように思われる。だがそれは演奏に介入する異物というわけではない。そうではなく二人の圧倒的なプレイとは違う場所で、でもたしかに、同じ時間に鳴っている音という印象なのだ。これはどういうことか。これまでのオルークのインプロヴィゼーションにおいて、そのような音の質感や運動はあまりなかったと私は思う。
オルークは、即興と作曲を同時にしているように私には思えるのだ。即興と作曲の同時生成。実際、本盤でのジム・オルークのシンセやギターの音は、彼の初期の電子音楽を思わせる。たとえば傑作『ディスエンゲージ』(92)や、近年発掘リリースされた初期音源集『ロング・ナイト』、そしてクリストフ・ヒーマンとの発掘コラボレーション作品『プラスティック・パルス・ピープル』シリーズ(1991年)を思わせる響きと構成、電子音の緩やかで乾いた持続、まるで水の底に沈むような音の質感、次第に盛り上がっていく物語的な構成力など共通点は多い(オルーク作品には「水」のモチーフが出てくるのだが、本作のジャケットもまたそれを感じさせるものだ)。
先に上げたバンドキャンプの演奏よりも、その傾向は強まっているとも思う。もちろん自身の総括コンサート〈ジムO 六デイズ〉での演奏という作用もあるだろう。そして同じ人が演奏しているのだから、かつての作品と似たトーンがあるのは当然という意見もわかる。だが重要なのは、本作『Okite』において重要なのはジム・オルークの即興演奏と実験音楽の境界が少しずつ無化されてきた、という点ではないか。そもそも、コンポジションとインプロヴィゼーションはその根源においてじつは同じものではないか。
あるインタヴューで「あの人と即興をやると、新しい音楽が浮かんでくるっていうのが成功」とジム・オルークは語っていた。石橋英子と山本達久が生み出す音が、ジム・オルークにそのような変化を与えたのは明白だ。そしてそんな彼らが、この演奏を正式なアルバムとしてリリースしたのも、何か特別なものが宿っているからではないか。それは何か。私見だが、ここには実験音楽と即興音楽が安易な融合ではなく、その二つが同時に生成しているような、非常に高度な音楽のように思えてしまうのだ。オルークは次のようにも語っていた。「私たちが作ったのは即興音楽じゃなくて、カフカ鼾の音楽。別のドラマーやピアニストだとできない、この3人だけの音楽」と。3人によって作曲と即興の差異が高密度に無化されること。ジム・オルークの音楽の現在は、このような領域へと至っているのかもしれない。実験音楽と即興音楽の新たな領域への「移動」。ジム・オルークという稀有な音楽家は、昨年の〈ジムO 六デイズ〉以降、「総括と包括」から、それらの「超克の時代」へと移行しているのではないか(オルークがバンドキャンプで過去の発掘音源をリリースしはじめたのも示唆的だ。)。
そして、このカフカ鼾の最初のアルバムには、そんな「総括以降」の音楽がたしかに鳴っている。実験音楽・即興音楽、ポップ音楽の総括と超克。このカフカ鼾の最初のアルバムには、そんな空想すら確信に近いと思わせるだけの力があるのだ。微音から爆音まで、音楽が自在に生成し変化する。その自由さ、その豊穣さ。音楽の生成と即興と作曲。その音の気持ち良さ、演奏者のテンションの高さ。それらが高いレヴェルで絡み合うことで、誰も聴いたことのないようなインプロヴィゼーション/コンポジションが生まれているのだ。終盤、演奏はロック的かつダイナミックなミニマリズムへと至る。そう、ここからポップ音楽への距離は、そう遠くない。
いつの日か、ジム・オルークという厖大な音楽記憶装置という存在は、実験音楽と即興音楽とポップ音楽という3つのテーゼを包括し、音楽史そのものを超克するような作品を作るだろう。その最初の「鼾」のような兆候が本作とはいえないか(ちなみにフランツ・カフカには「掟の門前」という短編作品もある)。そして、そのような大切な音楽=演奏が、ジムひとりだけではなく、3人の才能に溢れた音楽家とのコンビネーションによって生まれたという事実を私は何より嬉しく思う。3人だからこそ生まれた音楽、そのジョイフルな共闘。本作もまたアワー・ミュージックなのだ。1から3へ……。つまりは3のOkite!
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE