MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Olafur Arnalds- Two Songs For Dance + Stare + Th…
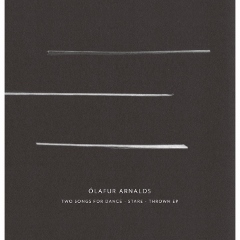
これはとても美しいアルバムである。もしもポスト・クラシカルという音楽ジャンルの中から、一枚だけアルバムを挙げよ、と問われたら、わたしはニルス・フラームの作品と悩んだ挙句、結局はこの作品を手に取るかもしれない。
しかし急いで付け加えておくが、本作はオリジナル・アルバムではない。オーラヴル・アルナルズが折々の機会にリリースされたシングル盤をまとめた来日記念の国内編集盤である。だが多くの音楽ファンは知っているはずだ。ささやかな編集盤にこそ、アーティストの本当の息遣いが聴こえるときがあるということを。そして、わたしたちの知らない意外な側面を聴き取ることができるということを。
本作はアルバム名からわかるように、「ツー・ソングス・フォー・ダンス」「ステア」「スローン EP」という3枚のシングル盤(7インチ/10インチ/12インチ)の楽曲をまとめた作品集である。
「ツー・ソングス・フォー・ダンス」はコンテンポラリー・ダンス・プロジェクトのために作曲された曲を収録した7インチ盤(“Endalaus II”は東日本大震災チャリティ・コンピレーション盤『フォー・ニホン』に収録された)。続く「ステア」は“レコード・ストア・デイ”リリースのためにニルス・フラームと競作された、ドローン/アンビエントな楽曲を収めた10インチ盤。そして最後の「スローン EP」は、ジェイナス・ラスムッセンとのユニットでKiasmos名義としてリリースされた12インチ盤。ミニマル・テクノの雰囲気が濃厚に漂うトラックが収録されている。
これらはそれぞれ別の機会に制作された曲である。だが、アルバムを一枚通して聴くと、楽曲と楽曲が互いに呼応しあっているのがわかってくるだろう。ミニマル、ドローン、アンビエント、テクノというエレメントが互い呼応し合うように鳴り響いているのだ。
とくにリズム/ビートは、「ツー・ソングス・フォー・ダンス」において楽曲を支え、ニルス・フラームとの「ステア」においてはピアノの反復的旋律と共に楽曲構造の中心となりスティーヴ・ライヒとポスト・クラシカルが出会ったような楽曲へと昇華され、そして「スローン EP」においては、透明感に満ちたミニマル・テクノ的なトラックへと見事に結実している。
また、「ツー・ソングス・フォー・ダンス」の“Endalaus II”のクリアな弦の響きは、「ステア」収録“a2”のシルキーなドローンへと通じ合っているし、「ツー・ソングス・フォー・ダンス」収録“For Teada”のセンチメンタルで浮遊感のあるエレピのメロディは「ステア」“a1”における点描的なピアノ&エレピを反転させたかのようでもある。さらに「ステア」“b1”の快活なミニマル・ミュージック・テイストは、「スローン EP」のテクノ・トラック“Wrecked”のポップな雰囲気を変奏しているようだ。
この音楽スタイル活用の巧みさ、旋律や和声に対する色彩感覚の一貫性、音響へのこだわりなどからもわかるように、オーラヴル・アルナルズは、ニルス・フラームと並び、ポスト・クラシカルの作曲家の中では頭ひとつ抜きん出た個性を持っているように思える。とくにオーラヴル・アルナルズの場合、(元)ドラマーということもあり、リズム/ビートに対するこだわりも感じられる。優しげな旋律と力強いビートのコンビネーションは彼の音楽の大きな特徴ともいえよう。そして本盤のリズムは、これまでの作品と比べて、リズム/ビートが、アンビエンスに溶け込むような質感もあった。わたしにはそれが嬉しかった。旋律とリズムが、ある一定のトーンの中で、やさしく、快活に鳴っていたのだ。
そしてこれこそがアンビエント/ドローン世代特有の感性ではないかとも思う。さまざまな音楽フォームを上品かつジョイフルに横断しながら、そのサウンドにはミニマル/アンビエントなヴェールがうっすらとかかっている。あらゆる音が溶けあっている感覚とでもいうべきか。
ポスト・クラシカルは新時代のアンビエント・ミュージックなのだ。たしかに旋律はある。リズムもある。だが、わたしたちリスナーはその旋律を、リズムを、美しい響きの結晶として聴く。オーラヴル・アルナルズのアルペジオは文節化されたドローンなのだ。わたしたちリスナーは、そんな彼の音の連なり、音の響きを愛してきた。だが、昨年リリースされたアルバム『フォー・ナウ・アイ・アム・ウィンター』において、オーラヴル・アルナルズは、これまでの音楽性をさらに深め、独自のヴォーカル・アルバムへと変化させていた。それは溶け合う響きの中から、ヴォーカルという具体的な音が表出してきたという意味でも、決定的な変化であった。いま、オーラヴル・アルナルズという若き音楽家は変化と成長のただなかにいるのだろう。そして、このミニアルバムには、そんな進化の上に咲いた美しい花のような楽曲が収められている。
そう、この作品には、若き音楽家の本質が、ささやかに、そして大胆に込められている。ミニマル、メロディ、響き、ドローン、アンビエント、リズム、テクノ、そしてクラシカル。それはポスト・クラシカルという音楽の魅力そのものでもある。
もう一度、この言葉を繰り返そう。この音楽は美しい。なぜか。この音楽は濁っていないからだ。旋律も、響きも、音楽を生み出した耳も、意志も、すべてがピュアである。そしてこの瞬間、この時期にしか生まれ得なかった儚さもある。美しさ、とはこのようなことを言うのではないか。わたしは、これからまるで親しい友人からの手紙のようなこのミニ・アルバムを、何度も何度も繰り返し聴きつづけるだろう。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE

