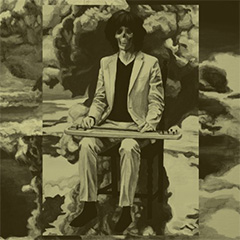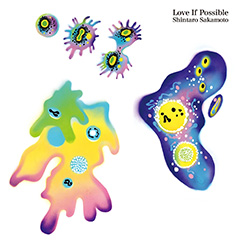MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 坂本慎太郎- ナマで踊ろう
いままでとは違う。“ソフトに死んでいる”、“空洞です”、“あえて抵抗しない”、“なんとなく夢を”、“つぎの夜へ”、“幻とのつきあい方”、“まともがわからない”、そして『ナマで踊ろう』……、こう来ると今回はいままでは違うぞ、と思わざるえない。極端な話、人生の虚無をただただ受け入れながら、深沢七郎的な「ぼーっとして生きる」人間の歌を歌ってきた坂本慎太郎にしては、ある意味ロマンティックな題名、と言えるだろう。
そして、そのタイトル曲には、こんな言葉がある。「昔の人間はきっと/音楽がかかる場所で/いきなり恋とかしていた/真剣に」……レーベルの資料によれば、人類滅亡後の地球が新作のコンセプトというが、つまり、未来から見た過去にあたる現在は、本当はもっとロマンティックなんだよと坂本慎太郎は諭しているように思える。まわりくどい表現だが、それが彼の持ち味だ。
とはいえ、実際のところ『ナマで踊ろう』は、“ソフトに死んでいる”の拡大版というか、いままで以上に、アイロニーというものが強く描かれている。アイロニーというからには、皮肉る対象があるわけで、それは今日の社会ということになろう。英国のメディアからは「scary」という言葉で形容されている安倍晋三のことだろうし、新自由主義ということだろう。ウクライナ情勢に見る世界秩序の崩壊かもしれない。何にせよ、それが、単純な嫌悪感の発露だとは思えない。坂本慎太郎は例によって言葉をぼやかしているものの、いや、リスナーの内面から醸成されるであろう言葉を促すように……、しかし、どう考えても今回は毒づいているのだ。ここには憤怒がある。つまり、らしくない。「決してこの世は地獄/なんて/確認しちゃだめだ」「見た目は日本人/同じ日本語/だけどなぜか/言葉が通じない」なんて、らしくない。
もちろん、何かを成し遂げたいとか、人生の勝負に出るとか、一発カマスとか、そうしたどや顔のギラついたものとは対極の、言わば勝っても負けても面白くないという坂本らしさは、言葉の随所にも、そしてサウンドにも見える。僕は最初の数回は、歌詞を気にせず、ただ音だけを聴いていた。ただ音だけを。この、ひたすら気持ち良い音だけを。ぼーっとしながら。気持ちよくなりながら。
オーヴァーダビングされた、70年代の、ゆるいトロピカルな歌謡曲もどき……、たとえば“スーパーカルト誕生”は、いかにも昭和ムード歌謡な曲調をジョー・ミークがミキシングしたかのような曲だ。場末の酒場的で、不自然なほどエキゾティックで、滑らかで、なおかつ巧妙なまでにサイケデリックだ。
デヴィッド・トゥープは、ミークについて「ブライアン・ウィルソンやリー・ペリーやフィル・スペクターのように、未知の領域からの音楽を具現化したいがゆえに、正気の外側においても音と奮闘したサイエンティストのうちのひとり」と説明しているそうだが、ミークといえば、かつてはチェリー・レッドから再発されたり、最近はジンタナ&エメラルズにカヴァーされたりと、近年とみに再評価されている音響加工の先達だ。
ウィルソンもペリーもミークも、たしかに錯乱したり、スタジオを燃やしたり、自殺したりした。が、坂本慎太郎がそんなエクストリームな事態になると思えないのは、彼にはヘゲモニー的なるものに翻弄されない、なかば禅的な心持ちがあるように思うからだ。食って寝ればいい、何もしないことが最善だと言わんばかりの、そんな心持ちが。
だが、今回は、違う。強いアイロニーをもって、何かを訴えている。ネガティヴな感性に居場所を与えない現代を「いびつに進化した大人たち」の社会として風刺する“義務のように”、それから、アイドルだろうと介護だろうと牢獄としての社会の一部だと厳しく描く“あなたもロボットになれる”で、アイロニーは乾いた笑いとともに最高潮を迎える。レトロを装った痛烈な批判者という意味において、忌野清志郎がタイマーズでやったことを坂本慎太郎は彼なりのやり方でやっている、と言えやしないだろうか(“争いの河”とかさ、ああいうのを思い出す)。
そして、“やめられないなぜか”~“この世はもっと素敵なはず”にかけて、坂本慎太郎は、あたかも世界の瀬戸際から、皮肉に満ち、ウィットに富んだ社会的コメントのオンパレードを展開する。「地震 水害 台風 大火災/見舞われるたんびにもうやめよう/と思った/でもやめられない俺は/あれを」、「そいつがこの危険な/この国の独裁者/歯向かった人間は/すべて消してしまう」、「お前正気か?(あいつらみんな人形だよ)」……。アルバムの最後に彼は、あけすけもなく、「ぶちこわせ(この世はもっと素敵なはず)」と繰り返す。ぶちこわせ。ぶちこわせ。これはパンクでもハードコアでも、ガレージ・ロックでもない。徹頭徹尾ひたすら心地よく、精巧に作られたゆるいポップスでありながら、リスナーを闘争に駆り立てているかのようだ。
いままでとは違う。坂本慎太郎は、いままで、間違った「あいつら」と正しい「僕たち」という単純な二分法を歌ってこなかった。だが、いま彼ははっきりと、間違った「あいつら」を指さしている。間違いは、死んだ目をした「俺」にも内在する。ともかく、“あえて抵抗しない”と歌った人が、いま、敢えて抵抗しているのだ。逆に言えば、それほどまでに、いま、「scary」な事態が進行している。本格的に。
最後に豆知識をひとつ。いまや日本の音楽は、欧米のコレクターにとって最後の秘境としてある。これだけインターネットが普及して、英米以外の先進国の大衆音楽があらゆる切り口からアーカイヴ化されても、日本の音楽は、ほとんどされていない。いま、まさにされようとしているが、その歴史の長さ、リリース量の多さ、そしてまた、欧米になろうと思ってもなりきれないことの独創性から言っても、いまだ整理されていない大いなる秘境としてある。マヒナスターズがコーネリアスよりも脚光を浴びることになるかもしれない。ま、何にしても、坂本慎太郎は、ここが秘境であることをわかっているひとりである。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE