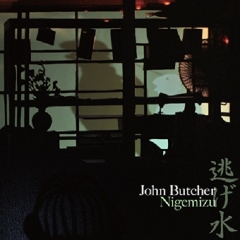MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > John Butcher- Nigemizu
ジョン・ブッチャーは英国のサックス奏者であり、フリー・インプロヴァイザーである。むろん、そんな説明など、まったく無用だろう。数々の奏法を生み出し、演奏と聴覚の拡張をする彼の名は、われわれ音楽ファンの記憶に深く刻まれているのだから。
彼こそデレク・ベイリー、エヴァン・パーカーなどのフリー・インプロヴィゼーションの第一世代と90年代以降の音響派シーンを結びつける最重要人物である。昨年にリリースされたロードリ・デイヴィスとの競演盤『ラウティング・リン』も記憶に新しい(クリス・ワトソンが録音を担当)。
本盤は、そんなジョン・ブッチャーのサックス・ソロ・アルバムである。リリースは日本の〈ウチミズ・レコード〉からで、ジョン・ブッチャーの2013年日本ソロ・ツアーから大阪島之内教会と埼玉・深谷エッグファームでの演奏を収録している。曲は全3曲。それぞれ“Enrai”、“Uchimizu”、“Hamon”という日本語が付けられている。本盤に封入された横井一江のライナーによると、レーベル・オーナーである寺内久が提出した日本の季語などの「夏」を連想させる言葉の中から選んだ曲名だという(このライナーもさすがとしか言いようがない素晴らしいテクスト。本作の空気感を落ち着いた文体で描いている)。アルバムを聴くとわかるが、言葉の響きがそのまま音/音楽に繋がっているような印象なのである。
録音はチューバ奏者である高岡大祐。高岡の録音は、ジョン・ブッチャーの音によって生まれるその場の空気の振動や空間性を見事に捉えている。フリー・インプロヴァイズの録音であり、同時に、民族音楽の現地録音を聴いているような生々しさや空間性を感じるのだ。
アルバムに耳を澄ます。音の肌理をなぞるように聴く。音の奔流と空間に没入する。そして、その「間」にある深い沈黙も聴く。すると、ジョン・ブッチャーの生成する音の変化が、少しずつ聴こえてくる。最初は彼の肉体性と演奏が直結しているように聴こるはずだ。呼吸器官から口腔がサックスという装置によって拡張していくさまが手にとるようにわかるとでもいうべきか。ブレスですらも生々しく捉えられた録音がじつに見事である。さらに聴き込んでいくと、その録音は、より広い空間の響きを捉えているように思えてくる。音が生まれ出る空間を感じられれば、今度は、ジョン・ブッチャーの肉体と音は不意に離れていくだろう。旋律が生成したかと思えば、次の瞬間、音の素数へと分解され、結晶のように宙にひらひらと舞う。そうかと思えば、その結晶が、さらに強い意志で明確な音へとトランス・フォームし、予想もつかない新しい「音楽」が生まれ出る……。
そう、このアルバムの聴取体験は、肉体/空間と音楽/音響の、ふたつの両極を「演奏」という音の線に乗って行き来する稀有な体験なのだ。私たち聴き手の「記憶」へと作用する音である。
1曲め“Enrai”は、記憶の襞を解きほぐすかのように、深く震動する音の持続からはじまる。サウンドは変化し、その響きは、ときにひとつであり、ときにふたつに変化する。またあるときは地を這うように響き、あるときは軽やかに空を舞う。ジョン・ブッチャーの息吹を生々しく感じたかと思えば、まったく予想できない天空の音を生成していく。26分に及ぶ演奏は一瞬たりとも集中力を欠くことはない。なんという演奏か。なんという音か。そして、演奏の終わり近く、あたかも遠雷のように響く音の衝撃。
アルバムの演奏に耳を澄ましていると、その音のタペストリーは、同時にサイレンスも深く際立たせていることにも気がつく。音と間。静寂と炸裂。息吹と咆哮。2曲め“Uchimizu”、3曲め“Hamon”と続けて聴くことで、われわれはジョン・ブッチャーがその瞬間に生み出す音と沈黙の連鎖を体感することになる。
音と沈黙。それはまるで夏の日の記憶に刻まれた、突然の雷のように、私たちのノスタルジアを強く刺激する。英国人であるジョン・ブッチャーのフリー・インプロヴィゼーションによるサウンドが、なぜ私たちの記憶=ノスタルジアを刺激するのか。まったく不思議であるが、同時に、まったく不思議ではない。なぜなら響きは記憶に作用するからだ。メロディよりもリズムよりも、もっと深く、より繊細に、深層に。私たちの音の記憶は、響きのテクスチャーの中に幾層にも折り畳まれているものだ。音の記憶とは鮮明である。同時に曖昧でもある。多様で複雑ですらある。それは芳香=空気の記憶に似ている。つまり本作の演奏は香りのように記憶に作用するのだ。
フリー・インプロヴィゼーションの技法のかぎりを尽くして、しかし、単なる技法を越え、天空を駆けるような、もしくは空気のような響きの「音楽」が奏でられている。彼のソロ・サックスの音もまた、ひとつの音であり、ふたつの音でもある。本盤においては、演奏者も聴き手も集中という軸を共有することで、より深い鎮静へと導かれるだろう。その響きの揺れと変化に聴覚を全開にすること。ジョン・ブッチャーの音響は、そのことを具体的に示す。そう、「ひとつ」の中に無限の千のプラトーが存在しているのだ。それはひとつの音の中(=複数の音の中に)に、繊細な多層性を聴き取る行為でもある。このサックス・ソロ・アルバムは、そんな豊かな音楽体験を約束してくれる素晴らしい作品だ。演奏、録音、アートワーク、ライナー、すべてにこだわりぬいた傑作である。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE