MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Automatics Group- Summer Mix JP
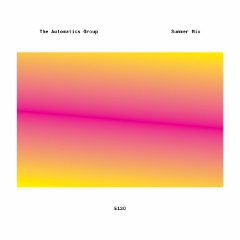
数々の有名EDMのトラックから低周波のみをサンプリングし抽出することで、まるでグルーヴの残滓を再生成するかのように快楽的なミニマル・ダブを生みだすこと。これが本作の目論見である。いわば「極限のサンプリング」によるサウンド生成。
ジ・オートマティックス・グループはヨーク大学の音楽研究所の一員、テオ・バートのプロジェクト。本作は〈アントラクト〉から200部限定で2011年にリリースされた『サマー・ミックス』(E130)の国内盤である。
〈アントラクト〉はエクスペリメンタルなサウンド・アート的な作品を送り出しているレーベルだが、音楽の形式性に束縛されない自由なリリースを継続しており、本作もレーベルにしては異質の(それゆえこのレーベルらしい)ミニマル・ダブ・アルバムとなっている。乾いた砂塵のような持続音と、偶然と構築のエラーから生まれたマイクロスコピックな電子音、再蘇生したようなキックなどからなるトラックは、とても快楽的だ。まさに2015年の夏に相応しいテクノといえる。ベーシック・チャンネルをオリジンとし、Gas(ウォルフガング・ヴォイト)、ヤン・イェリネック、ディープコードなどに連なる洗練されたミニマル・ダブの系譜にあるアルバムだ。
だがよく聴いてみると、いわゆるミニマル・ダブとは低域の作り方が異なっているようにも思える。端的にいって音が軽いのだ。その「軽さ」ゆえ、聴覚に直接的にアディクトする感覚もある(音量の増大によってトラックのコンポジションを起こっているように聴こえる)。となると、やはりEDMのサウンドを抽出し、そのサウンドによってトラックを組み上げていったことが、とても重要なことに思える。
つまり、「EDMのトラックから抽出したコンセプチュアルな音響生成によって生まれたこと」を考慮すると、〈アントラクト〉のレーベル・カラーどおりのサウンド・アート作品にも聴こえてくる/思えてくるわけだ。これは2010年代ならではの「音響彫刻」作品なのではないか。
すると砂丘の砂塵のように乾いた快楽的な音が、デジタルサウンドの残骸のようにも感じてくるから不思議だ。仮想の人工楽園で展開される開放的な死後の世界のような無常観が、ディスプレイのむこうに再現される、そんな同時代的なアイロニー感覚を感じるのだ。また、EDMのアーティストの名を羅列した「だけ」の曲名にも強いアイロニーを感じる。まさに「デス・オブ・レイヴ」!
このような独創的なアルバムを2011年にCD作品としてリリースした〈アントラクト〉の先駆性も驚きだが、それを2015年にアナログ再発した〈デス・オブ・レイヴ〉、さらに国内CD盤リリースに踏み切った〈メルティング・ボット〉の同時代的な嗅覚も素晴らしい(国内盤「JP」はボーナス・トラックが1曲追加され、計5曲収録の決定盤となっているのでお勧め)。アルバムのアートワークもこの国内盤に合わせ、〈アントラクト〉の近年のリリース作品のフォーマットにリメイクされている。
それにしてもベーシック・チャンネルといいGasといい、ミニマル・ダブのサウンドが、まったく古くならないのは何故なのか。テクノロジーの進化と直結している電子音楽が、数年でそのサウンドが古くなってしまうことが多いなか、ミニマル・ダブの耐久度の高さは異常なほどだ。単なるサンプリングではなく、原型をとどめないほどにサウンドを加工することから生まれる音の快楽性、低音重視という聴覚の普遍性を接近しているからか。
本作は、高度に完成されたサンプリング/エディットの美学であるミニマル・ダブに、EDM(の残骸)を利用するというアイロニーによって介入している点が重要なのだ。まさに2010年代敵な「デジタルの残骸」の活用。ここにヴェイパー以降、2010年代的な「新しいアイロニー/ニヒリズム」があるといえば、いい過ぎか……。
むろん、普通に聴いても最高のミニマル・ダブ/テクノであることは繰り返すまでもない。この夏、そんな「世界の終わりのダンス・ミュージック」を聴きまくりたいものだ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE
