MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Titus Andronicus- The Most Lamentable Tragedy
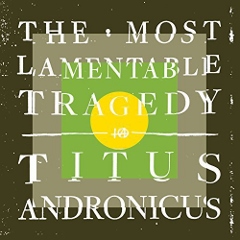
ノー・フューチャー――誰もが聞き飽きたその台詞を、もしくは若い世代にとってはたんにポップ・ミュージック史の教養として知っているその言葉を、いままたわめき散らすのがタイタス・アンドロニカスというバンドである……それも何度も。いちパンク・バンドが全29曲・93分2枚組のロック・オペラ・アルバムを作る力がいまも残っていたことに感嘆しつつ、しかしそのじつ、コンセプトはこの一枚に留まるものではない。ファースト・アルバムから繰り返してきた“ノー・フューチャー”のタイトルを引き継ぎつつ、この大作は幕を開ける。
タイタス・アンドロニカス――シェイクスピアのもっとも暴力的な戯曲から取られたバンド名だ――の名前が大きく浮上したのは、これもコンセプト・アルバムめいたセカンド『ザ・モニター』(2010)だった。ガレージ・バンドが復権するなか「ブギウギ・パンク」とも表現された彼らは登場時からひときわみずみずしい存在感を放っていたが、そこではっきりと異質さを示すことに成功したのだ。リンカーンの演説のサンプルから幕を開ける同作は南北戦争をモチーフとしており、スピルバーグの『リンカーン』よりも少しばかり早く、アメリカの歴史における「連帯」を回顧しながら現代においてパンク・コミュニティが持ちうる連帯感をほのめかしてみせた。が、そのいっぽうでアルバムに散らばっていたのは「お前はいつだって負け犬だ」「どこもかしこも敵だらけだ」といったような皮肉や恐怖、不安と諦観であり、それはおもにフロントマンのパトリック・スティックルズの内面の混乱と厭世感から発生している。雄々しいコーラスとパワー・コードで押し切るようなフレッシュさや若々しさ、ときに大陸的なニュアンスが加味された泥臭く逞しい音を持ちながら、それらはどうにか正気でいるためのアンセミックでやんちゃなパンク・チューンだった……タイタスは、そんな危うさを纏いながら走りつづけた。「ノー・フューチャー」はスティックルズとバンドにとってたんに引用ではなく、ヒリヒリとした実感として表現されていたのだ。
4枚めとなる本作もその続きで鳴っていて、バンドは疾走をやめることはない。これをよくできた知的なコンセプト・アルバム、あるいはロック・オペラとするのがやや躊躇われるのは、理路整然としたストーリーが綴られているわけではないからだ。神経が衰弱した男のパニックが、取りとめもなく語られていく……というか、叫ばれる。それらの多くはスティックルズ自身の切実かつ個人的な問題であり、たとえば前作『ローカル・ビジネス』(2012)でも取り上げられていた感電事故の体験がここでも繰り返されている。何度も同じ言葉や場面が繰り返したりその間を行ったり来たりする様は、リアルに精神疾患的だ。
が、それらはすべて電撃が迸るようなパンク・ソングに変換される。使用される楽器はより多様になり曲によって味付けを変えていくが、しかし汗が飛び散る熱は消えることはない。パブ・ロック色をやや増しつつ、同郷のスプリングスティーン & E・ストリート・バンドを思わせるソウル、ガイデッド・バイ・ヴォイシズの哀愁、ザ・ポーグスのような酒臭いトラッド感……先のパンク・バンドやガラージ・バンドを取り込み、知恵とエネルギーにしてみせる。「俺は狂っちまおうが気にしない/俺は狂っちまった/7、8、9回も」とピアノを弾きつつ軽快に歌われる“アイ・ロスト・マイ・マインド”はビリー・ジョエルのようだとさえ指摘されているほどだが、ときに冗談のようにお茶目にメロディアスに、語り手の憂うつと混乱は歌われる。1枚め、ドッペルゲンガーとの出会いについてまくしたてる1分に満たないガレージ・トラック“ルック・アライク”から2度めの“アイ・ロスト・マイ・マインド”、そしてピアノとストリングスがゴージャスな“ミスター:Eマン”へと至る、血管がブチ切れそうな怒涛の流れは勢いだけでも圧倒されるが、その後の“ダイムド・アウト”のヴァイオリンとギターの絶唱ですべてが昇華する。その高揚感、全能感、開放感……高らかに挙げられるパンク・キッズの拳が見える。フォークロアの引用やポーグスのカヴァーを挟んでくるトラッド色が強めの2枚めでも、狂気に落ちる不安が不意にどこからともなく現れて暴走する――「I’m going insane!!!」
どう考えても自分が負け犬に思える人間にとって、ほんとうはノー・フューチャーという言葉はいまもクリシェでもたんなる教養でもない、ギリギリと身に迫るものであるはずだ。タイタス・アンドロニカスはそのやけつくような痛みを忘れることができず、目を逸らすこともできず、だから狂いそうだと繰り返す。いまの世のなかでいったい何がまともなのか、このアルバムを繰り返し聴いている僕にはわからなくなってくる……だが、このパンク・ソングたちが胸を打つのは、それらが苦闘そのものだからだ。未来なんてまるで見えない場所で、もがき苦しむことをやめられないことこそがこの音楽の燃料となって、一瞬の炎が立ち上がっている。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE