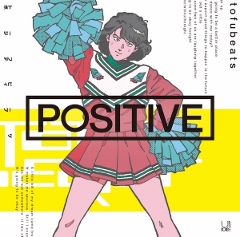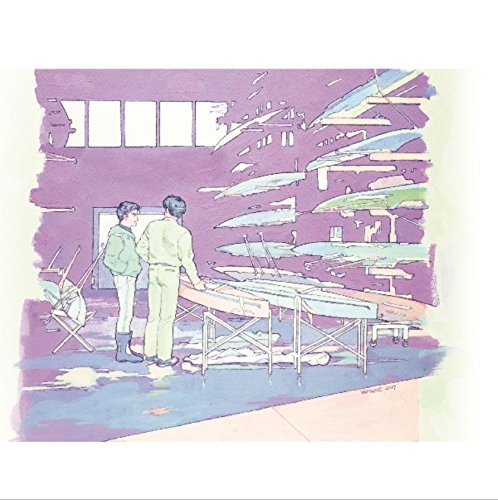MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > tofubeats- POSITIVE
トーフビーツの音楽を聴いていると、いつも思い浮かぶのは、音楽が鳴り終わったあとの満たされた静けさだったり、ほんの少しの寂しさであったりする。「パーティのあとに」とか「アフター・アワーズ」といってしまうのは簡単だが、音楽と日常を往復するように生活しているこの社会においては、誰しもが感じるものではないかと思う。
もちろん彼の音楽は、インターネット時代特有のエレクトロニックなサウンドであったり、CDが売れなくなった時代ならではの考えぬかれた戦略性であったり、そもそも最高のポップ・ミュージックであったりするのだが、しかしその音楽の本質には、ポップスとダンス・ミュージックだけが持っている高揚感と寂しさの感覚が共存しているように聴こえるのだ。
私はポップスとダンス・ミュージックは本質的には同じものだと思う。踊ること/歌うことへの悦び。同時にその享楽性が消えてしまうこと諦念もどこかにある。音楽は儚い夢だ。そしてトーフビーツの音楽にはそれがある。その「寂しさ」の感覚は、テン年代のアンセム“水星”から変わらないもので、当然、新作『ポジティブ』でも受け継がれている。
たしかに本作の楽曲の多くはパーティー・ソングであり、新世代のJ-POPともいえるほどメジャー感にあふれるものであり、『ポジティブ』というアルバム名が示すように、とても前向きな楽曲が多く収められている。ドリーム・アミを起用した“ポジティブ”などは、これまで以上に軽快な曲に仕上がっている。
しかし同時に、不意に醸し出される「寂しさ」の感情は、ダンス・トラックにおいて、より際立っているようにも感じられたのだ。“T.D.M”や、EPでリリースされた“ステークホルダー“、トーフビーツ的なテクノ“アイ・ビリーブ・ユー”などのトラックを聴いてみるとよくわかる。
私は、かつて “水星”を聴いたとき、浅はかにもラップだからというだけで“今夜はブギーバック”のテン年代からの返答みたいに思ったものだが、いま聴き直すと、あきらかに宇多田ヒカル“オートマティック”への変奏/返答といえなくもない(彼は宇多田へのリスペクトをつねに公言している)。あの「寂しさ」の感情は、トーフビーツにしっかりと受け継がれている。そうアーバン・ブルースだ。とくに循環コードの中に切なく胸しめつけるような和音を紛れ込ませるワザ。本作ではクレバを迎えた“トゥ・メニィ・ガールズ”の「メニィ・ガール」のリフレインを聴いてほしい。
そんな彼のアーバン・ブルースが極まるのが、エゴ・ラッピンの中納良恵を迎えた“別の人間”ではないか。この曲で彼はあえてビートを封印し、ヴォーカルとピアノ(打ち込みで作られたという)をメインにしたトラックを制作した。この曲はインターネット時代以降の歌謡曲=ブルースの魅力がある。
そう考えると、トーフビーツの音楽は流行のシティポップといっけん近いようで実は(決定的に?)違うような気がする。なぜだろうか。それは90年代J-POP(歌謡曲)の「遺産」を引き継ぐ場所に彼が立っているからではないかと思う。
CDが売れなくなった時代に、CDがもっとも売れた時代の「遺産」を受け継ぐこと。それは当然、ビジネスの側面ではなくて、あの時代のJ-POP(歌謡曲)が持っていたポップスとダンス・ミュージックの「享楽性」と「切なさ」を引き継ぐことを意味するのではないか(このアルバムで、あの小室哲哉と共作しているのは象徴的だ)。
トーフビーツは音楽が消えてゆくことの「寂しさ」と「切なさ」を知っている。だからこそ音楽は素晴らしいということも。
音楽はいつか消える。パーティは必ず終わる。ダンスフロアの光もやがて消える。パソコンから再生される音楽も、アイフォーンの中の音楽も、イヤホンから流れ出る音楽も唐突に終わる。すべては消えていく。そして、トーフビーツの音楽は、そんな享楽が終わったあとに続く日常や生活の寂しさを彩る。それこそポップ・ミュージック=ダンス・ミュージックの力(ポジティブ!)ではないか。そう、「ポジティブ」とは「ミュージック」であり、同時に「ライフ」のことなのだ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE