MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Anna Meredith- Varmints
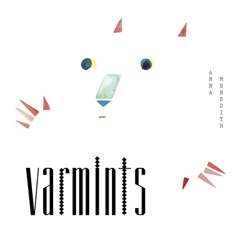
アンナ・メレディス。クラシックとインディ・ミュージックのハイブリッドとして、いまもっともエネルギッシュで個性的な作曲家と言えるだろう。しかしそれは、クラシカルな音楽をはじめとしたさまざまな音の素養を身に付け、また専門的に修めながらも、それらをすべて「忘れて」しまった人間による音楽だ。
BBCスコティッシュ交響楽団のコンポーザー・イン・レジデンスとしても活躍するなど、彼女の素養の高さは「専門的」どころの話ではない。そしてクラシックばかりか、音の端々からはグランジ、ポニーテイルにダーティ・プロジェクターズらを思わせるエクスペリメンタリズム、アニマル・コレクティヴやシン・ファン・ブーに通じるドリーミーなサイケデリア、バトルスの構築性にタイヨンダイの現代音楽的な発想、デイデラスの引用する映画音楽やオールディーズを彷彿させる優雅なIDM、さらにはシンセ・ポップ様のものまでが片鱗を見せ、この作曲家の度量や音楽体験の豊かさを想像させる。
でも、それらの要素も全部、いちど忘れられたものというふうに出てくるのが素晴らしい。きっと彼女はそういうふうに生きている人なのだ。あまたの音楽をめぐって、歴史を学び、構造を解析し、構築や表現の方法を知ったのだろうが、その音はけっして何かを覚えておいて応用するというようなものではない。それぞれの方法や要素は、アーカイヴされていつか引き出されるのを待っているのでも、憧れて真似したいと思われているのでもなく、ただただメレディスの中で溶け合っていて……何かの拍子に彼女の中に入ってきたまま記憶と感性の中に沈みこみ、まったく別のものとして書き出されてきているように感じられる。それは忘れるという体験の本質であるように思われる。失われるのではなくて変化するということ。おのおのの要素自体は、まるで異なるアルゴリズムを持ったものに変貌してしまって、○○を消化した音、とか、ジャンルをまたいだ音、とかいう言い方では少しもなぞることができない。
彼女の作曲はそんな場所ではじまる。「作曲するときに何かを聴いたり参考にすることはない」とメレディスは言うが、おそらく「いま聴いたもの」は彼女にとって邪魔なものであり、忘れていたものこそが創作の素材でありモチヴェーションになるのだ。コピペを前提とする時代に(だからこそヴェイパーウェイヴが批評でありえる)、これほどコピー的でありながらコピーをはねつけるオリジナリティを持っているのは、ひとえに彼女が彼女自身をこそ信頼しているからであり、汲み出されてきた記憶が熟成と変色を経ているということによるだろう。
これまでに2枚リリースしているEPは〈もしもし〉からで、そこもおもしろい。IDMや電子音楽の実験的かつ先端的なレーベルや、あるいはかつてのジュリア・ホルターのように〈リーヴィング〉や〈リヴェンジ〉といった境界的なアンダーグラウンド・レーベルからの発信ではなく、ホット・チップやフローレンス・アンド・ザ・マシーン、あるいはドラムスなどでおなじみのインディ・ポップの名門がバックアップしてきたというのは、メレディスの音楽が誰に聴かれるべきであるのかということを物語っている。複雑で高度で、しかしポップ。ピッチフォークが「イギリスのモダン・ミュージックにおける、もっとも革新的な精神のひとつ」と評しているが、もっとも革新的なものこそポップ・フィールドで鳴らされるべきで、その意味で〈もしもし〉が支え、フル・アルバムとしていま多くのメディアから高い評価を集める作品を送り出したことには大きな意義がある。
“ノーチラス”や“ザ・ヴェイパーズ”のブラスと変拍子の高揚にきわまれれりというメレディスの有頂天が本作のコアかもしれない。いま彼女は音楽的な旅において「南中」状態にあるという。“テイクン”のガレージ―なサウンドに忘れられない歌メロ、“スクリムショウ”“R・タイプ”“Dowager”の本流のような上昇とクレッシェンド、“ラスト・ローズ”の讃美歌のような歌唱や“Blackfriars”の厳かなオルガンでさえも、抑制をしらない喜びや高まりに満ちている。メレディスはクラリネットとエレクトロニクスを担い、チェロやエレキギター、チューバ、ドラムなどの編成からなるバンドとともに制作しているようだ。
彼女はまた、作曲家/ミュージシャンというだけでない顔を持つのも魅力である。もちろん、オーケストラとの仕事や、有名ブランド等への楽曲提供に映画の仕事、美術館の仕事など音楽だけでも多岐にわたる活躍だが、テレビやラジオにレギュラーを持っていたりと、タレント的な才能も併せ持ち、その活動はとても自由。今後さらに、いろんなところでメレディスの音を耳にすることになるのではないかと思うし、それが耳にできるかぎり、わたしたちは形式ではないもの……忘れたものからつくられた、見たことのない見たことのあるもの、その新鮮な感覚に、胸がすっとするような風通しを感じるだろう。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE



