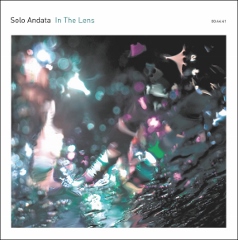MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Solo andata- In The Lens

デンシノオト Jul 20,2016 UP
何もしたくない。そんなときにはアンビエント・ミュージックが効く。怠惰。この勤勉と抑圧の近代国家ニッポンでは、もっとも反社会的と思われる行為への誘惑。そう、アンビエント・ミュージックは、社会からの逸脱=怠惰へと誘う。ああ、なにもしたくない。ああ、疲れた。ただ、寝ていたい。いや、なにもしたくないから、寝ることすら面倒である。ゆえにアンビエントを聴いてゴロゴロしていたい。できることなら休みたい(いや、休めない)。そう、怠惰という極楽への誘惑。その意味で夏こそアンビエント・ミュージックを聴きたい。なぜか。暑いからだ。なにもしたくない。そこで今回は、そんな気分に合うアンビエント作品と一作と、正反対に、そんな気分を瓦解させてしまうようなエクスペリメンタルな作品を紹介してみたい。どちらも、とてもクールな作品である。
まずは、ニューヨークの〈12k〉からリリースされたソロ・アンダータの新作『イン・ザ・レンズ』について語ろう。ソロ・アンダータは、ケイン・アイキンとポール・フィアッコによるオーストラリアのアンビエント・ユニットである。2009年に〈12k〉からリリースしたファースト・アルバム『ソロ・アンダータ』は、いま思い出してもかなりの傑作だ。イーノ的な環境音楽/アンビエント・ミュージックでもなく、KLF的なチルアウト/アンビエント・ミュージックでもなく、日常の隙間にアンビエントの空白を生むための「00年代以降のエレクトロニカ・音楽的アンビエント」を、彼らは『ソロ・アンダータ』で確立したのだから(むろん、当時、似たような音楽は、たくさんあったが、彼らのクオリティは抜きん出ていた)。
そして6年ぶりとなる新作は、その「エレクトロニカ・アンビエント」の、その先を見据えたような作品に仕上がっていた。電子音のみならず、ピアノやベース、ギターなど楽器演奏=アンサンブルによって楽曲が成立しているわけだが、そこにさまざまな細やかな物音やノイズがレイヤーされ、音楽の層とやわらかく融解しているのである。そのソフトなノイズと音楽のアンサンブル/融解は大変に気持ちがよく、聴き進めていくと夢の中にいるような感覚になってくる。ノイズと楽音的なハーモニーの境界線がシームレスになっている。これこそまさに2010年代的なアンビエント/ドローンの新しいオトノカタチではないか。クラシカルでもあり、ジャズのようでもあり、しかしそのナニモノでもない音楽と音響の生成。まさに音楽/アンビエントの深化。では、この進化の源はなにか。私には、曲のなかで、そこかしこに鳴っているベース(低音)の存在が大きいように聴こえた。つまり、ひかえめなベースの進行が音楽としての構造を生んでいるのだ(ウワモノが持続音でもベースが旋律と刻むと進行が生まれるのだ)。それにしても、本当に素晴らしい作品ではないか。これぞポスト・ノイズ、ポスト・エレクトロニカというべきアルバムだ(本年、ケイン・アイキンのソロ『モダン・プレッシャー』もリリースされている。インダトスリーでありながら浮遊感と現実感が入り交じったような秀作であった)
***
そんな夢見心地の気分に、砂漠の崩壊していくさまを顕微鏡のような音響/映像感覚で表象し、われわれの現実の足場がすでに倒壊しているのだということを、極めてスタティックなスタイルで示す作品が、 ベルリンのサウンド・アーティスト、ヤコブ・キルケゴールの『サブレーション』である。
ヤコブ・キルケゴールは、これまでも環境の中に存在する音響の変化を主軸においた音響作品を発表してきたアーティストだ。その作品はまるで、彼の耳のありようをトレースするかのように音響の要素がコンポジションされており、聴き手は、アーティストの耳と同化するような感覚を持つことになる。たとえば2013年に〈タッチ〉からリリースされた弦楽作品『コンバージョン』は、弦の軋みや揺らぎを録音・再構成した作品であったが、同時に、彼の耳の反応そのものを音に「変換」したものにも思えた。
本年、日本の〈マター〉からリリースされた新作『サブレーション』は、「砂漠化」の名のとおり、オマーン砂漠の映像と音響によって成立している映像作品である。もともとは2010年のあいちトリエンナーレで池田亮司の作品などとともに公開されたインスタレーションが元になっているというが、今回、ついにDVD+フォトブックという形態でリリースされた。まるでヤコブからの「手紙」が届いたような美しく親密な装丁も素晴らしい。
砂漠が崩壊していく集積/運動のさまを捉えた緻密な音響とモノクロームの映像のコンビネーションは圧倒的で、ずっと聴いている/観ていると、まるで自分の足場が倒壊していくような感覚に襲われてくる。それは知覚の拡張ともいえるのだが、私たちの知覚=現実が倒壊していくような感覚でもあった。ちなみに本作は勅使河原宏の映画『砂の女』(1964)へのオマージュでもあるようで、いわれてみると不穏感覚や、現実への崩壊感覚には通じるものがある。そこからわれわれ「日本という現状/問題」へと結びつけることは、さほど困難でもないだろう。そして、先に書いたように近年のアンビエントが再び足場を確かめるように「低音」を導入しているのに対して、ヤコブは、幾千、幾万もの砂塵が、砂が散り散りに倒壊するような崩壊感覚を音響化/映像化している。そう、これは、「砂漠化」し、やがて崩壊する「世界」そのものではないか。本作の表象は、抽象的に見えつつ/聴こえつつ、やはり一種の(強烈な)リアリティに思えてならない。
だが、である。いまは暑い。夏が本格化してきた。現状への批評的な視線も大切だが、この美しく砂漠が倒壊していくさまを捉えたモノクロームの冷たい質感の映像と音響に、いつまでも浸っていたい気もすることも事実である。美しい、からだ。たしかに本作はアンビエントというより音響的にはフィールドレコーディング作品(映像)だが、われわれはヤコブの耳をトレースするように、音の磁場が生むアンビエンスを聴くのだからアンビエントとしても聴取/視聴可能なはず。なにより、このモノクロームの砂漠の映像/音響は、灼熱のなかの氷のように冷たい。ゆえに夏の猛暑に効く……。
ともあれ、「ベースと崩壊」である。それは夢と現実の表象でもある。この2作からは、そんな響きを、音楽を聴き取ることができたわけだ。それにしても、今年の日本の夏は夢見るように不安定だ。本当に夢だったらよいとすら思えるほどに。冒頭の無気力さは、暑さのためだけではないかもしれない。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE