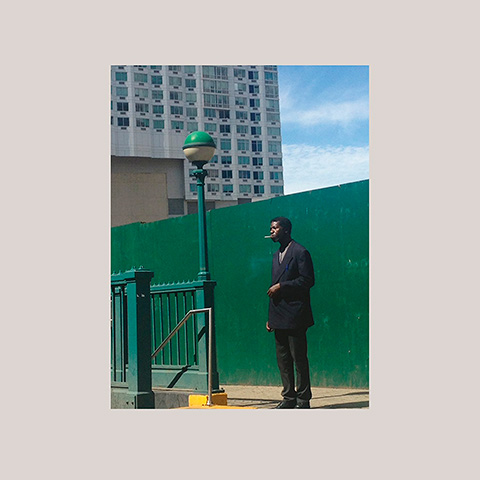MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース
- 『成功したオタク』 -
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙
Home > Reviews > Album Reviews > Jay Daniel- Broken Knowz
だからなんども言っているように、ぼくはトラップは嫌いじゃない。デトロイト・テクノの根っこが同じくエレクトロ・ファンクであるから、マイアミベース経由の現在形とはいえ、むしろサウンド的には親しみを覚える。ただ、それは、おそらくは「考えるな、感じるんだ」であり、決して「考えろ、考えろ、それはイリーガルではない」(byジョージ・クリントンの名言)ではないように思う。ぼくが間違っていたら指摘してくださいね。「考えるな、感じるんだ」は、たしかに説得力がある。妄想が膨らむ。しかし、ぼくは「考えろ、考えろ」のほうに惹かれてきた。デトロイトは、「考えろ、考えろ」の音楽の街である。「考えるな、感じるんだ」は、初期衝動は良いが、すぐに行き詰まる。サッカーも同じだ。レヴェルが高いところでは、運動神経だけでは通用しない。いや、まあ、運動神経だけでもある程度のところまではいけるんだけど、そう、ある程度までは。
ジェイ・ダニエルは、なんども言っているように、ナオミ・ダニエルの息子である。ナオミ・ダニエルは歌手で、90年代にカール・クレイグのレーベルから2枚の12インチ(うち1枚は2枚組)をリリースして、そしてその2枚、いや、正確にいえば2曲なのだが(つまり、ヴァージョン違いが多数あるだけ)、その2曲は、いまでもうっとりする素晴らしい歌モノのハウスで、名曲で、クラシックで、中古で見つけたら絶対買いで、ぼくは彼のお母さんの曲の大ファンなのだが(正直、ナオミ・ダニエルがなぜアルバムを残さなかったのか不思議でならない)、息子のジェイは母がやったことをなぞろうとはしなかった。
アフロ・フューチャリズムとは、黒人の宇宙観/SF趣味のことだけではない。アフリカ系アメリカ人の文化において、若い世代は必ず親の世代のやったこととは別のことをやること、新しいことに集中すること、つまり、ソウルで育った親の子供がテクノをやること、その更新力のことも意味する。
白人や日本人の黒人音楽ファンは、つねに古きよきブラック・ミュージックを求めたがる。エイミー・ワインハウスでもアデルでもノラ・ジョーンズでも、拍手される彼女たちの音楽は、基本、ひと昔前のソウルである。黒人音楽はこうであって欲しいという願望が、そこには見え隠れする。しかし、たとえば、今年最高のダンス・アルバムを発表したジャマイカのイキノックスは、ルーツ・ミュージックから離れて、むしろベース・ミュージックとシンクロしている。手に負えない新しいモノ好き。ブラック・カルチャーのその本質の一部を、懐かしむべき過去を持たないための未来志向と解釈したのが、アフロ・フューチャリズムとも言えるのだ。
とはいえ、ことはそう単純ではない。すでに懐かしむべき過去がブラック・カルチャーにあることは、URやムーディマンのリスナーでも知っている。トラップやドリルのような音楽のほうが、現時点では、過去を懐かしまないアフロ・フューチャリズムだと言えよう。しかしそこには、かつての、いち部のハウスやテクノのように、刹那主義以上のものはない。刹那的だからこその美しさもあるし、まあ逆に言えば、いまさえ良ければもうどうでもいいというくらいに、逼迫しているのだろうけれど。
ジェイ・ダニエルは、カイル・ホールもそうだが、親の世代を否定せずに新しいことをやろうとしている。そのとき彼らは、まずはリズムから入る。というか、リズムしかない。リズム・イズ・リズム。本作『Broken Knowz』において、ジェイはリズムを更新するためすべてを機械まかせにせずに、ドラムスティックを握って、叩き、試行錯誤したという。要するに、古きを重んじながら新しきを追い求めた結実が、これだ。このリズム。反射神経だけに頼らず、「考えろ、考えろ」の街で生まれた、リズムである。それは……ある種コスモポリタン的な、と同時に生粋のアフリカンなのだろう。2曲目の(アルバム中のベスト・トラック)“Paradise Valley”とは、1920年代から50年代にかけて、デトロイトが北部の工業都市として賑わっていた時代の、アフリカ系の人たちの華やかな商業/娯楽エリアのこと。白も黒もジャズを楽しんだ場所であり、しかし43年の暴動以降、白と黒の溝は空き、そして重なる再開発に打撃を受け廃れていったエリアだという。それからジェイは5曲目の“Squeaky Maya”では中米の先住民をたずね、クロージングの "Yemaya"では西アフリカの生みの女神をテーマにする。それらの曲でも強調するのは、リズムだ。
ジェイは、決して認めないだろうが、ぼくなりに彼の最初のアルバムを言い表すなら──リズム・イズ・リズムの「ザ・ビギニング」の続きを見たと。25年経ったいま、なんて素晴らしいことだろう。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE