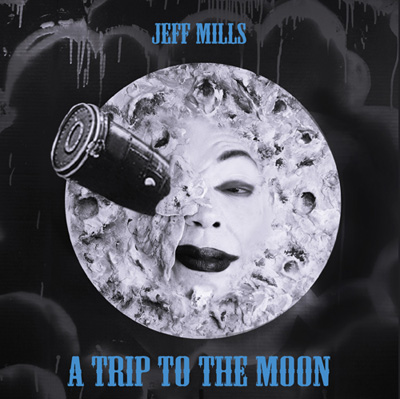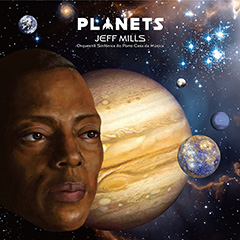MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jeff Mills- A Trip To The Moon
レイヴ真っ盛りの時代に刊行された、ジョン・ラインドンの最初の自伝の最後のほうには、レイヴ・カルチャーは現実逃避でそれじゃ何も現状を変えないというお叱りの言葉が出てくる。この言葉を、ぼくはそのまま「どう思うか?」と、まだフッキー在籍時のニュー・オーダーの4人に対面取材で訊いたことがある。その答えは、まさにその通りだよね。でもね、現実逃避できるから素晴らしいんじゃないのかな、と、そのときの彼らは言った。
昨年、ブラック・ミュージックを専門に論評している音楽ライターの河地依子さんからいろいろ教えていただいたなかで、ぼくがもっとも深く納得したことのひとつに、P-FUNKの──今年河地さんよって詳述された書が刊行される予定なので、ここでは手短に暗喩的な説明にとどめておこう──そう、パーラメントの『マザーシップ・コネクション』の裏ジャケット。デトロイトのゲットーに浮かぶ宇宙船。あの宇宙船はゲットーにやって来た宇宙船なのか、いや違う、Íいままさにゲットーから飛翔する宇宙船ということである。このことは、ぼくに次のような場面を思い出させる。
ジェフ・ミルズは、ぼくが初めて彼のDJをブリクストンで聴いた1993年の夏の時点で、たとえば他の優秀なDJがフロアから30cm浮かすことができるのなら、ミルズはオーディエンスを余裕で屋根をも越えさせた。実際、そのクラブには天上にぶら下がっているクラバーが何人もいた。後にも先にもあんな光景は見たことがない。いや、スティーヴ・ビッククネルが当時出たばかりの“スター・ダンサー“でミルズに繋いだ瞬間、すでにフロアは地球圏外にワープしていたのかもしれない。
ジェフ・ミルズはあるインタヴューで、デトロイトにおいてクラフトワークの“ナンバーズ”がかかったときのことをこう回想している。「私たちには、ただ明日をどう生きるかしか興味がなかった。黒人にとってどれだけ長くファンキーでいられるか……」そこにクラフトワークがやって来たのだ。
何度も繰り返しになるが、デリック・メイがいみじくも言った天才的な表現──「デトロイト・テクノとはジョージ・クリントンとクラフトワークが同じエレヴェーターに居合わせてしまった音楽」とは、まさにこのことである。どんな音楽よりも高く飛翔すること、そしてもうひとつ、「ただ明日をどう生きるか」。ファンク、SF、テクノロジー、これらが絡み合ったときに、その音楽は(この辛い毎日を生きるための)かけがえのない逃避であることから、社会変革への渇望を反映するものへと劇的な変化を遂げる。それがURであり、あるいはジェフ・ミルズである。
ジェフ・ミルズの新作が2枚リリースされる。先に発売されるのは、ここ数年続いているSFシリーズの最新版で、ジョルジュ・メリエスの映画『月世界旅行』(1902年)を主題とした『A Trip To The Moon』。タルホイストのぼくに言わせれば、この映画は10代後半から20代にかけて、──ミニシアター/自主上映の時代だったので──、いかなる労苦も惜しまずに上映先を見つけ、そのファンタジーに酔いしれたものだった。『ユゴーの不思議な発明』より30年以上前に、ぼくはこの映画を溺愛し、フィルムの所有者に交渉して自主上映すら考えていたほどなので、映画について話すと長くなる。ひとつ映画のポイントを言えば、これが特撮のルーツであり、そしてまだ特撮をわかっていない観客に、現実にミサイルがお月様の顔にぶち込まれたものだと信じ込ませた作品だったということだ。このヨーロッパSF映画のアンティークを未来的なエレクトロニック・ファンクに更新するという大胆な発想が『A Trip To The Moon』では具現化されている。
とはいえ、ジェフ・ミルズの音楽は90年代末にはすでに完成されているので、それ以降の作品において大きな変化があるわけではない。が、2年前にベース世代のあいだでX-102がリヴァイヴァルしたりと、いまもなおシーンに影響を与え続けているという意味では、ミルズは、クラフトワークやイーノのような先駆者として存在している。現在のクラフトワークが“ナンバーズ”と同等の衝撃を与えられるとは思えないように、先駆者と呼べるアーティストたちは、すでにある程度の実践は終えているのだ。10代のときに天才DJとしてシーンに衝撃を与えた彼は、ダンス・ミュージックにおいてさまざまな試みをしてきている。『A Trip To The Moon』は、乱暴な表現として、白い骨董品を黒い未来が塗り替えるという説明もできるかもしれないが、もうひとつの紹介の仕方としては、アンビエント・テイストが盛り込まれた作品というのもあるだろう。ん? アンビエント? 「どれだけ長くファンキーでいられるか」じゃないのかい? と思われる方もいるだろうから、はっきり言おう、これはファンキーなテクノ・ミニマル・アンビエントだと。アートワークをよく見ればそのことは察していただけるはずÍ。
さて、2月22日発売とずいぶんと先のリリースになるが、ジェフ・ミルズのもう1枚の新作、『Planets』をここで紹介するつもりだったが、力尽きた。じつは年末、サッカーで右手人差し指の第二関節を骨折、全治3か月という、いまも痛み止めを塗りながらキーを叩いている。もう止めた。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE