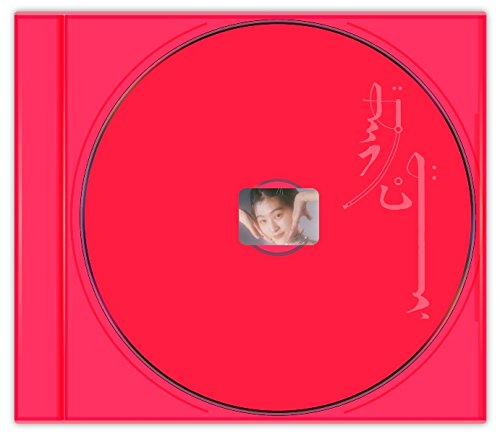MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 水曜日のカンパネラ- ガラパゴス
出羽守という言葉がある。「でわのかみ」と読む。きっとあなたも一度は耳にしたことがあるだろう。「海外ではこうである、しかし日本ではそうではない」というような議論を展開する人びとを揶揄するための言葉だ。けれど、「海外では」という言い回しを使う人びとは必ずしも「ゆえに日本もそうすべきである」と主張したいわけではなくて、たいていの場合たんに参考例を挙げているだけなのではないか。海の向こうのケースを参照することで見えてくることだってあるんじゃないと、ちょっとした提案をしているだけなのではないだろうか。そこに悪意や攻撃性を読み込んでしまうのは、受け手の自意識が肥大しているからなのかもしれないし、あるいは「そんなこと言ったって、結局何も変わりゃしねえよ」というシニシズムが働いている可能性もある。なかには、閉鎖性を優位性へと置き換えたい人もいるのかもしれない。
水曜日のカンパネラによる最新EPは、「ガラパゴス」と題されている。資料によるとそれは、いまの日本(の音楽)に対するメタファーなのだそうだ。たしかに、昨今のJポップのクリエイターのなかには、洋楽を聴かない人たちがそれなりに存在しているなんて話も聞く。ということはつまり、水カンはいま、日本(の音楽)の閉鎖性を憂い、歎いているのだろうか? それとも逆に、このアイソレイテッドで特殊な生態系を誇り、褒め称えようとしているのだろうか?
冒頭“かぐや姫”の歌い出し、左右と中央に振り分けられた「アォ」という音の連なりを耳にした瞬間、彼らがこれまでとはまったく異なるステージに立っていることがわかる。弦と管によって緩急をつけられたヒップホップ・マナーのトラックも意外だ。zAkによるエンジニアリングの効果も大きい。そしてコムアイは、トレードマークとも言えるその独特のラップを手放し、大々的に歌っている。にもかかわらず、おもしろいほどにリリックの内容が頭に入ってこない。歌詞カードを確認しない限り、それが日本語であることさえ認識できない。同じタイミングで新作をリリースしたムードイドは、声もあくまで楽器のひとつと見なしているそうだけれど、その彼とコラボレイトした5曲目“マトリョーシカ”では、テープを逆再生したような奇妙な日本語とフランス語とのかけ合いが、言葉から次々とその意味を剥奪していく。
水カンの音楽を評する際にしばしば用いられてきた術語に「ナンセンス」というのがあるけれど、僕はこれまでどうにもそういう評価のしかたに居心地の悪さを感じてきた。というのも、水カンの歌詞に「ナンセンス」という言葉をあてがってしまった時点で、不可避的にナンセンスというセンスが発生してしまうからだ。つまりナンセンスはナンセンスではなくなってしまうのである。「ガラパゴス」がおもしろいのは、コムアイの声をどんどん音へと近づけて歌詞性を引き剥がしていくことによって、ナンセンスというセンスを持ったナンセンスではなく、文字どおりのナンセンスが実現されている点である。
そのことと対応するかのように、本作ではプロダクションの面でもこれまでとは異なる水カンが打ち出されている。中盤はダンサブルな曲が続き、一部では4つ打ちも導入されているものの、それがこのEP全体の雰囲気を決定づけているわけではない。“ピカソ”や“メロス”から聴き取ることができるように、各々の曲には今日のベース・ミュージックやコンテンポラリーR&Bなどの要素が細かく織り込まれている。“南方熊楠”や“見ざる聞かざる言わざる”のパーカッションのような聴きどころも多く、とにかくサウンド面での魅力が飛躍的に向上している。もちろん、これまでも彼らはフットワークやクワイトといったスタイルを参照してきたわけだけど、とはいえそのサウンドはあくまでJポップという枠組みのなかに収まるものであった。しかしこの「ガラパゴス」は、そのJポップの慣習を盛大にぶっちぎっているのである。
だからこそ、アンビエント・ポップとでも呼ぶべき最後の2曲の違和感が際立つ。オオルタイチが作詞・作曲・編曲を手がけた“愛しいものたちへ”も、コムアイが作詞し彼女とケンモチヒデフミとzAkの三者が作曲を担当した“キイロのうた”も、シンセの持続音が静けさを演出する一方で、異様なまでにコムアイの歌が強調されている。この2曲からは日本語が聞こえる。彼らはここで、一度ぶっちぎったはずのJポップの慣習を意図的に呼び戻している。これまで基本的に人名(やユーマ)を曲名に採用してきた彼らが、この2曲に関してはそのルールを適用していないことも示唆的である(直前の“見ざる聞かざる言わざる”は、それを「猿」と捉えれば人やユーマの系列に所属させることができる)。ナンセンスでもなく、ナンセンスというセンスでもなく、ストレートなセンス。この2曲には、じつに意味らしい意味が蠢いている。
Jポップという鎖からの解放を希求し、海外のポピュラー・ミュージックを参照することで一度はそれを否定しながら、最終的にはもとの枠組みへと帰ってくる――けれどもそのとき、もといた場所はすでにもといた場所ではなくなっている。これこそが、彼らがこの新作を「ガラパゴス」と名付けたゆえんではないだろうか。つまり、「では」によって一度「あちら」が切り拓かれるからこそ「こちら」の充実もまた望めるのである……と、あまりにも当たり前の結論に至ってしまったことに呆然としているが、しかし水カンが戦っているのはそういう「当たり前」のことを言っていかなければならない舞台だ。であるなら、言うべきことはひとつ。僕たちは遠慮なんかせず、がんがん「では」「では」と連発していけばいい。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE