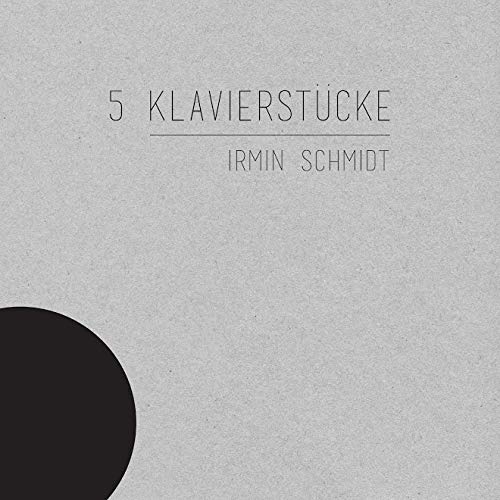MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Irmin Schmidt- 5つのピアノ作品集
ジョン・ケージといえばやかんの音である。ぼくがまだ20代半ばの若造だったころ、松岡正剛さんはニューヨークにケージを訪ねたときの話をしてくれた。2人が対話をはじめたちょうどそのとき、部屋のキッチンのお湯を沸かしていたやかんから音がした。するとケージは、自分はやかんの音が好きだと笑ったという。蓋がカチカチ鳴る音か、シューシューという蒸気の音のことか、どっちなのかは忘れてしまったけれど、松岡さんからこのエピソードを教えてもらってからは、ぼくのなかでジョン・ケージとはやかんの音のひとになっている。
DJが現代音楽という名の古典をスピンする21世紀では、どうってことのないエピソードかもしれない。が、ここにはジョン・ケージの本質が集約されているんじゃないかとぼくは考える。それはメタ音楽とでもいえるアプローチであり、あるいはルネッサンス以降の西洋音楽(クラシックと呼ばれる音楽)の堅苦しさに対する大いなるパンク的アティチュードとも言える。周知の通り、もともとケージは西洋音楽に学んでいる。アカデミックな場において、たとえば「やかんの音って良いよね」というようなことを言ってしまうのは(もちろん彼の師であったシェーンベルクに対してそんな言葉はつかってないだろうけれど)、演奏が上手いのはかっこ悪いと言ってしまうパンク・バンドみたいなものだ。アンチ権威というか、伝統主義への反論というか、いっしゅの破壊行為である。
CANという70年代に活躍したドイツのロック・バンドが希有だったのは、4人のうちの2人のメンバーが西洋音楽の厳格な理詰めを学びながら、むしろケージ的な破壊を好んだところにある。ホルガー・シューカイとイルミン・シュミットは、西洋音楽の聖なる理論(トータル・セリー)上でいろいろ小難しい思考をかさねがら電子音楽へとたどり着いたショトックハウゼンに学んではいるけれど、同時に敷居の高いヨーロッパにアメリカからの自由の風を吹き込んだというか、たとえばクラシック音楽にとってはNGだった“反復すること”を自らの武器とした。乱暴な言い方をすれば、クラシック音楽における“前衛”の代表格のひとりであるシュトックハウゼン(想定されうる結果に向かう緻密な計算)と、その流れに反旗を翻したケージの“実験”(むしろ結果が読めないところに向かう)とがロック・バンドというフォーマットのなかで合流しているのだ。
イルミン・シュミット(CANの4人のメンバーのなかで唯一の生存者)の18枚目のソロ・アルバム『5つのピアノ作品集(5 Klavierstücke)』は、きわめてケージ的なアプローチの作品だ。たんにプリペアド・ピアノを使っているからではない。プリペアド・ピアノは、ケージが発案したときには紛れもなく“実験”ではあったけれど、いまとなってはひとつの“型”であり、想定されうる結果が見えている。シュミットはプリペアド・ピアノの不協和音を鳴らし、そして調律されたピアノによる調和的な旋律を重ねている。ピアノ以外の楽器は使用されていない。曲によっては演奏されたときの環境音がミックスされている。2曲目は、夜のしじまの向こうで聞こえる風の音か、ムシの声か……とにかくその場の環境音がかすかに聞こえる。
「やかんの音」をアンビエント・ミュージックに仕立てること。こうした発想自体も、いまでは別段珍しいものではない。では何に賭けるというのか。あとは内から湧き出るもの。シュミットはとりあえず、どういう結果になるのかわからないけれど演ってみた。エディット無しの一発録り。まばらに響くピアノの音、ピアノを叩く音、弦を爪弾く音、ときにリズミックに鳴り、ときに不安定に鳴る。雅楽の影響もあるというが、それは間(沈黙)の取り方においてだろう。シュミットの回想によれば、すべての曲は自然な瞑想状態のなかで生まれたそうだが、こうしたコンセプトもまたケージ的だ。
4曲目の後半ではミニマルなドラミングが展開される。CANらしいといえばCANらしいのかもしれないけれど、プリペアド・ピアノを打楽器として演奏することは、これまたとうの昔にケージが試みていることである。結局のところ現在81歳のシュミットは、CAN以前のみずからの転機において大いなる影響を授かった音楽をたずねているのだろう。クラウトロックの評価が定まりながらも、CANを語るうえでスルーされがちな重要な事実。いまジョン・ケージについてあらためて考えてみると。そういうことなのかもしれない。とはいえ『5つのピアノ作品集』は、ミニマル・ミュージックを吸収した初期ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのように、手法を楽しむというよりは、ぼくのようなずぶの素人の耳を楽しませるためにある。目ではなく、耳からも景色は見えるのだ。このアルバムはスマホにイヤホンではなく、家のスピーカーの前に座って聴いて欲しい。
※〈ミュート〉からこのような作品がリリースされるいっぽうで、渋谷系に影響を与えた〈el〉レーベルは最近シュトックハウゼンやヴァレーズの作品を再発している。20世紀における前衛音楽の冒険は、松村正人が来春1月に上梓する『前衛音楽入門』に詳しく綴られております。ええ、たぶんすごい力作になるでしょう。ご期待下さい!
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE