MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Paulius Kilbauskas- Elements
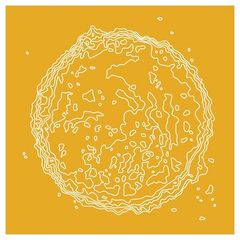
まるでスティーヴ・ライヒとデリック・メイを同時に聴いているみたいだ。ガムランの響きに始まり、トライバル・ドラムが絡み、以後も同様な曲が続くものの、ところどころでクラブ・ミュージックのクリシェが面白いようにミニマル・ミュージックに加えられ、ライヒとは異質の高揚感が湧き出してくる。リトアニアにニュー・ウェイヴを紹介してきたゾーナ・レコーズから1年前にリリースされたエディションにオープニング曲を加えた8曲入りがライセンス盤として出回り始めたようで、シンプルな“Space”から始まる構成が余計にそうした演出度を高めてくれる。どこまでいっても低音は響かず、ガムランの音が密度を変化させながら空間性を担保していく。ブラシの抜き差しはどうしてもデリック・メイを強く想起させ、これで影響を受けていないといわれたら嘘でしょうとしかいえない。正月からデザイナーの祖父江慎がデリック・メイで朝の5時まで踊ったというから、余計にそう思えてしまうのかもしれない(なんて……しかし、祖父江さん、何歳よ~)。
後半はデリック・メイをまさにガムランでカヴァーしていると捉えた感じになっていく。チャカポコという響きがほんとにそれらしく、デトロイト・テクノをここまでオーガニックに聴かせた例はないのではないかと思ったり。“Seven”にはハープ奏者も加わり、瑞々しさは一層増していく。“Space”と”Fire”にはゴングとメタロフォンという楽器で実際にインドネシアのガムラン奏者である通称バロットも参加し、とくに”Fire”は華やかで音が自由に乱舞しまくり(イントロとアウトロでポクポクと打ち鳴らされるのは木魚だろうか)。ぜんぜん知らなかった人なので、調べてみるとパウリウスはどうもリトアニアのギタリストで、リトアニア語をグーグル翻訳で読んだのではっきりしたことはわからなかったけれど、小学校もロクに行かなかったらしく、4弦ギターと出会うことから彼の人生は変わり始めたらしい。93年に結成されて、ドラムとキーボードが死んだために01年に解散せざるを得なくなったエンプティ(Empti)というバンドでプログラムなども手掛けていたそうで、それまではアシッド・ジャズの流れでトリップホップとかブロークン・ビートとカテゴライズされる音楽性を追求していたという(フェスティヴァル・オブ・ワースト・グループで優勝したとも)。ソロ活動は07年に『バンゴ・コレクティヴ』と題されたダンスホールとブレイクビーツを組み合わせたようなアルバムからスタート(これがまたなかなか)。続く『ペピ・トゥリー』(09)ではゲーム音楽、マリウスくんたちと取り組んだ『スタジオ・ジャム』(09)はいわゆるインプロヴィゼイション・ジャズと、音楽的にはなんの脈絡もない。2014年には2枚のサウンドトラック・アルバムを手掛け、それらがロックンロールだったり、現代音楽だったりするのは映画の種類に合わせたものだから仕方がないとしても、ダブリケイトの名義ではハードコアから発達したジャンプスタイルにもチャレンジしているらしく、これは昨年、イタリアのアドヴァンスド・オーディオ・リサーチが『ファースト・グレード』で極めて面白い展開を見せたジャンルとしても気になっていたので、がぜん興味が増してくる。これを2013年にはすでにやっていたとは。『Elements』に通じる作品としては09年の『スケッチ・トゥ・ペインティング』やマーク・マッガイアーをユルくしたような3枚のライヴ・アルバムがオーガニックなギター・アンビエンスを展開していて(『LRTオーパス・オーレ・ライヴ』“Part 2”の前半はベイシック・チャンネル風)、この辺りから少し『Elements』へと通じるものが見えてくる。しかし、決定的だったのは1年間、家族4人でバリに住んだことらしい。それはゴミが燃え、犬が飛び、色が現れる世界だたっという。
バリで受けた影響は曲名が地水火風に基づいていることや「空気を吹き付けるような音楽を探していた」という表現などニューエイジに向かってもおかしくはないはずなのに、時間がなくてガムランをベースに音楽を組み立てるまでには至らず、ガムランに多大なインスピレーションを受けながらも伝統音楽との間に距離を感じたままのレコーディングとなったらしい。そのことがむしろ幸いしたのだろう。中途半端にクラブ・ミュージックの要素が残ったことが新たな道筋を切り開いたという気がしてしまう。彼はすでに次のアルバムのことも考えていて、ニューエイジに近づきかねない「軽くて明るい音楽」というヴィジョンを語っているから、良かったのはここまでだったということになりかねない恐れはあるものの、この瞬間が素晴らしいことはとにかく間違いがない。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE