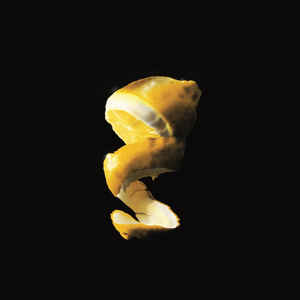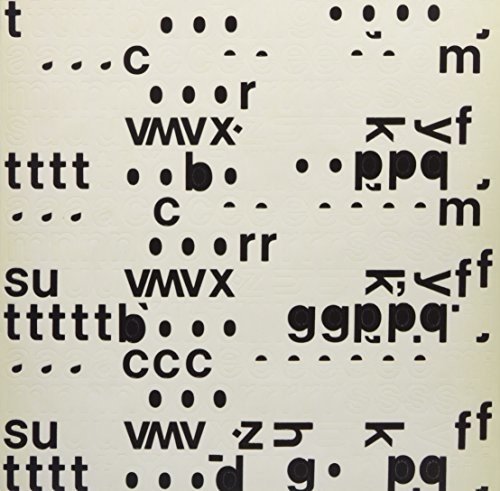MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jay Glass Dubs- Epitaph
忘れがちなことだけれど、2012年あたりのオリジナル・ヴェイパーウェイヴの特徴のひとつにスクリューすることがあった。スクリューというのはですね、2000年に夭折したヒューストンのヒップホップDJ、DJスクリューが編み出したテクニックで、再生の回転数を下げることで得られる効果を駆使すること(一説によれば咳止めシロップの影響下による)。ゴーストリーな音声などはその代表例だが、スクリューは面白いことにヒップホップ・シーンの外部であるLAのアンダーグラウンドなインディ・ロック・シーン(昨年、食品まつりを出したサン・アロウなんかも関わっていたシーン)へとしたたかに伝播し、そしてヴェイパーウェイヴにも受け継がれた。そうすることによって「蒸気=ヴェイパー」な感触が生まれたのだった。
スクリューは、楽曲をメタ・レヴェルで操作することによって別もの(ヴァージョン)を創造するという点においては、ダブと言えるだろう。もちろんジャマイカのオリジナル・ダブとは、スタジオにおいて録音されたマルチトラック上のヴォーカルないしは楽器のパートを抜き差しし、あるいはエフェクト(リヴァーブ、そしてエコーやディレイ)をかけながらオリジナルとは別もの(ヴァージョン)を作ることである。音数を減らし、引き算足し算しながら骨組みだけにすることから「レントゲン(x-ray)音楽」とも呼ばれる。
しかしながらスクリューやオリジナル・ヴェイパーウェイヴのようなデジタル時代の音響工作は、キング・タビーとはあまりにも違っている。なによりも「レントゲン音楽」的ではないし、楽器の部品(パート)を操作するのではなく、音の位相(レイヤー)を操作する。そしてその音像は独特のくぐもり方をする。ジャマイカのダブには、サイケデリック体験における酩酊のなかにも霧が晴れていくような感覚があった。しかし、スクリュー以降の新種のダブはむしろ霧を呼び込んでいるようなのだ。Mars89の作品でも知られるレーベル〈Bokeh Versions〉からリリースされたジェイ・グラス・ダブスの『エピタフ』がまさにそうだ。
OPNの『レプリカ』をリー・ペリーにコネクトしたような感じというか、『エピタフ』はジャマイカのオリジナル・ダブの基盤であるドラム&ベースを削除することなく継承しつつも、まったく違ったものになっている。鄙びたサウンドシステムもなければ埃もたたないピクセルの世界に踏み込んでいるからだろう。それはひとの生活の何割かがインターネットの向こうに及んでいるというリアリティをただ反映しているぐらいのことかもしれない。
あるいはまた、“セイキロスの墓碑銘”からはじまる『エピタフ』はコクトー・ツインズと初期のトリッキーをスクリューしたようでもあり、ジェイムス・ブレイクの新作は生ぬるい(ぼくは嫌いじゃない)というひとが聴いても面白いかもしれない。Burialが深夜の侘びしい通りから聴こえるレイヴ・カルチャーの記憶だとしたら、こちらはいったいなんだろう。アルバムには“模倣の新しい型”という曲名があるけれど、タッチスクリーンの向こう側の、暗闇なきダークサイドから聴こえるダンスホールなのだろうか……。いや、この音楽からはなにも見えてこないのだ。
ジャマイカのオリジナル・ダブにおける音の断片化は、ディアスポラの記憶すなわち観念上の“アフリカ”=理想郷の想起ではないかという説がある。しかし『エピタフ』にはそうした音の断片化はないし、理想郷も想起されない。にも関わらず、エコーがさらにエコーし、ディレイがさらにディレイする世界……いったいどこに連れて行く気だ?
なんにせよ興味深いなにかが起こっている、そんな気がしてきた。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE