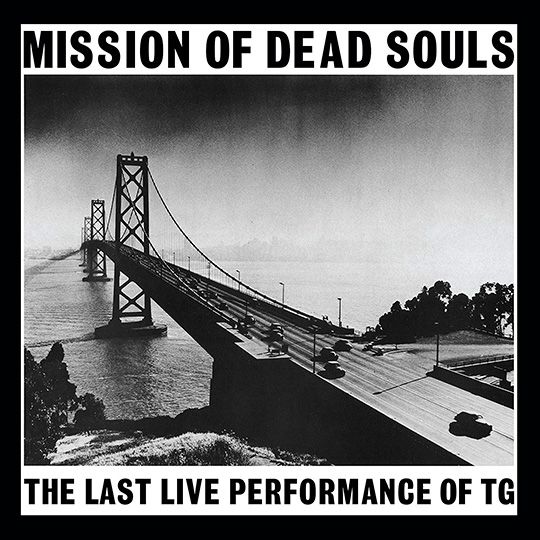MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Cosey Fanni Tutti- Tutti

Cosey Fanni Tutti
Tutti
Conspiracy International
イアン・F・マーティン (訳:五井健太郎) Mar 27,2019 UP『トゥッティ』のなかに一貫して存在している、不吉で、ゾッとするような、何かを引きずって滑っていくような感覚──いいかえるなら、すぐ側にまで迫りくる湿り気のある暗さが生む、閉所恐怖症的な強度。オープニング曲“トゥッティ”の単調なベースラインと機械的でガタガタと騒々しいパーカッションのなかにはそうしたものがあり、そしてそれはそのままずっと、クロージング曲“オレンダ”のもつ、近づきがたいような重い足どりのリズムのなかにも存在しつづけている。最初から最後までこのアルバムは、息苦しいほどの霧に、隙間なく包まれている。
この霧をとおして、おぼろげな影がかたちを結んでいく──ときに現れた瞬間に消えてしまうほどかすかに、そしてときに水晶のような明るさのなかにある舞台を貫き、それを照らしだしながら。オープニング曲では、トランペットのような音が暗闇を引き裂いていく一方で、5曲目の“スプリット”における、音の薄闇のなかを進んでいく、かすかに光る金属の線のような粒子は、おぼろげだが、しかし距離をおいてたしかに聞こえてくる天上的な雰囲気をもったコーラスによって、悪しきもののヴェールを貫いてるそのメランコリックな美しさによって、そのまま次の曲“ヘイリー”へと繋がっていく。
おそらくはきっと、メランコリーの感覚へとつづいていく、ガス状のノスタルジーのフィルターのようなものが存在していて、それがトゥッティのこのサード・アルバムに入りこんでいるのだろう。このアルバムは、コージー・ファニー・トゥッティの2017年の回想録『アート・セックス・ミュージック』のあとに作られる作品としては、またとないほどにふさわしいものとなっている。というのもそれは、部分的に、彼女の生まれ故郷であるイングランド東部の街ハルで、同年に開催された文化祭のために作られたものをもとにしているからだ。やがてロンドンにおいてインダストリアルの先駆者となるバンド、スロッビング・グリッスルを結成する前の時代を、彼女はその街を中心にして過ごしていたわけである。
1969年における、パフォーマンス・アート集団COMUトランスミッションの結成からはじまり、スロッビング・グリッスルやクリス&コージーによるインダストリアルでエレクトロニックな音の実験を経由する、過去50年にわたる経験と影響関係を描いていくなかで、過去について内省し、ふかく考えるそうした期間が、『トゥッティ』という作品の性格を、根本的な次元において決定づけているようにおもわれる。その回想録や近年に見られるその他の回想的な作品をふまえると、トゥッティはこのじしんの名を冠したアルバムによって、ひとつの円環を──はじめてじしんの名義のみでリリースした1983年の『タイム・トゥ・テル』以来の円環を、閉じようとしているのだという感覚がもたらされる。
だが、コージー・ファニー・トゥッティはまた、まとまりのあるひとつの物語のなかに収めるにはあまりに複雑で、たえずその先へと向かっていくアーティストでもある。たしかにトゥッティは、幽霊的な風景をとおって進むビートとともに、彼女の作品のなかに一貫して拍動している人間と機械の連続性のようなものを、じしんの過去から引きだしている。だが彼女にとって過去とは、みずからの作品を前方へと進めていく力をもったエンジンなのである。『タイム・トゥ・テル』におけるリズムは、捉えがたく、ときに純粋なアンビエントのなかに消えさっていくようなものだったが、それに比べると『トゥッティ』は、はるかに攻撃的で躊躇を感じさせないものとなっている。こうした意味で、この作品に直接繋がっている過去の作品はおそらく、比較的近年にリリースされた、クリス・カーターと、ファクトリー・フロアーのニック・コルク・ヴォイドとともに制作された、2015年のカーター・トゥッティ・ヴォイドでのアルバムだろう。とはいえこの作品と比べると『トゥッティ』は、より精密に研ぎすまされ、より洗練されたものとなっていて、その攻撃性や落ちつきのなさは、節度をもって抑えられている。
ゾッとするような暗さをもつものであるにもかかわらず、そうした落ちつきのなさと節度の組みあわせのなかで、『トゥッティ』はまた、これ以上ないほどに力強い希望の道を描きだしてもいる。というのも、このアルバムが強力で完成されたものであればあるほど、そこらからさらに多くのものがもたらされるのだという兆しが高まっていくからだ。
(訳:五井健太郎)
A sinister, creeping darkness slithers through “Tutti” – the claustrophobic intensity of humid darkness that clings too close. It’s there in the grinding bassline and mechanical, clattering percussion of opening track “Tutti”, and it lingers on in the grimly trudging rhythm of the closing “Orenda”. From start to finish, the album is wrapped tight in a suffocating fog.
Through this fog, shapes take form – sometimes faintly, fading away as quickly as they appeared, sometimes piercing through and illuminating the scene in a moment of crystal clarity. On the opening track, a trumpet cuts through the darkness, while on “Split”, solar winds seem to shimmer matallic through the sonic murk, joined on “Heliy” by a celestial chorus, blurred but distantly chiming, a touch of melancholy beauty piercing the veil of evil.
There’s perhaps a gauzy filter of nostalgia to the melancholy that creeps into the Tutti’s later third, which is fitting for an album that comes off the back of Cosey Fanni Tutti’s 2017 memoir “Art Sex Music” and has some of its roots in work she created for a culture festival in her hometown of Hull that same year, which she based around her own early years before leaving for London with her then-band, industrial pioneers Throbbing Gristle.
This period of introspection and reflection seems to have informed “Tutti” on a fundamental level, drawing on five decades of experiences and influences from the founding of the COUM Transmissions performance art collective in 1969, through the industrial and electronic sonic experimentations of Throbbing Gristle and Chris & Cosey. Taken together with her memoir and other recent reflective works, there is a sense that Tutti is closing a loop with with this self-titled release – her first album solely under her own name since 1983’s “Time to Tell”.
But Cosey Fanny Tutti is also too complex and forward-thinking an artist to let that be the whole story. Certainly “Tutti” draws from the past, with the beats punding through the ghostly soundscapes a continuation of a man-machine heartbeat that has always pulsed through her work. However, for her the past is an engine powering her work ahead into the future. Where the rhythms of “Time to Tell” were subtle, occasionally dissolving into pure ambient, “Tutti” is far more aggressively forthright. In that sense, the release it hews closest to is perhaps the comparatively recent 2015 “Carter Tutti Void” work, produced with Chris Carter and Factory Floor’s Nik Colk Void. Still, “Tutti” is a more finely honed, more refined work, its aggression and restlessness tempered by restraint.
Through its creeping darkness, it’s in that combination of restlessness and restraint that “Tutti” also holds out its strongest line of hope, because as powerful and accomplished as this album is, it also extends the promise of more to come.
イアン・F・マーティン (訳:五井健太郎)
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE