MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Maria Chavez- Plays (Stefan Goldmann's Ghost H…
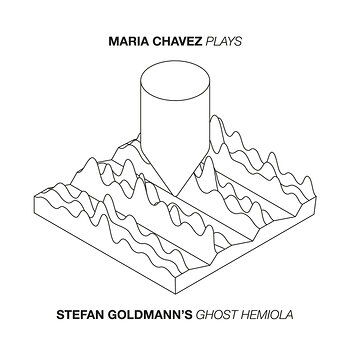
瀟洒な作風で知られるテック・ハウスのプロデューサー、ステファン・ゴールドマンに「Ghost Hemiola」(13)というアナログ盤のダブル・パックがあり、それぞれのAサイドに音のしない66本のループが刻まれている。本人がユーチューブで使い方を解説しているものを見ると、ターンテーブルの上で回っているレコード盤のループにナイフで傷をつけることでプチッという音が等間隔で再生され、同じことを2枚同時にやることで一種のポリリズムが出来上がるという仕組みになっている。タイトルの「ヘミオラ」というのはポリリズムを表すクラシック音楽の専門用語で、ゴールドマンはなんとも芸術的な手つきでレコード盤に次々と傷をつけていく。かつてはトーマス・ブリンクマンがターンテーブルにアームを2本付けて、やはり2ヶ所同時に音を再生するということをやっていたけれど、アナログDJの技やトリックはさらに広がっていく一方である(なんて)。
ターンテーブルを使ったパフォーマンスで定評のあるニューヨークの現代音楽家、マリア・チャヴェスはこのダブル・パックを使って11パターンのコンポジションをつくり上げた。プリペアード・ピアノならぬプリペアード・レコードが用意されたということ以外、あとはどこをどうやっているのかはさっぱりわからない。『Plays (Stefan Goldmann's Ghost Hemiola)』と銘打ってはいるけれど、明らかに「Ghost Hemiola」から得られた音は素材に過ぎず、様々なプロセッシングを施したものが完成形となっているはずである(もしかすると米電子音楽のパイオニアであるウサチェフスキーがすべてライヴでエフェクトを加えていた例もあるので、本当に「Plays」だけなのかもしれないけれど)。レコード針と溝が擦れ合う擦過音だけが素材のはずなのに、その表情はあまりにも多岐にわたり、商業主義とはかけ離れた地平で繰り広げられる無邪気さはとても伸び伸びとしていて、妙な爽やかさまで感じられる。レイアーを重ねたドローンなどはすでにクリシェと化して久しいにもかかわらず、バジンスキーやケヴィン・ドラムに感じられる老獪さとも無縁で、DJワークをベースにしているからか、随所で遊び心が炸裂し、現代音楽といえば不条理なトーンを醸し出すという図式にも当てはまらない。それでいてヘンな音が出ることに感覚のすべてを任せっきりにしてしまうダグラス・リーディーやスペース・エイジの時代とも違い、頭の中をほぐしてくれるような現代性もある。それはきっと2019年に特有の感情表現が成立しているということなのである。全体的な構成は静から動へ。そして淀みと混沌の対比へ。
ここにあるのはローレル・ヘイローやベアトリス・ディロンが現代音楽やミュジーク・コンクレートをDJカルチャーの磁場に引きずり込んだのとは正反対に、DJカルチャーの養分を現代音楽に注ぎ込もうという試みだと思う。現代音楽がDJカルチャーに寄生するのはこれが初めてではないし、カールステン・ニコライのあたりはすでに境界線は溶けきってしまった感もある。マヤ・ラトキエがポップ・ミュージックのメディアで評価される時代が来るとはまさか思わなかったけれど、ホットなジャンルがお互いに刺激し合わない方がウソだし、ターンテーブルが果たした役割はおそらくミュジーク・コンクレートの時期のシンセサイザーに匹敵するものになりつつあるのだろう。かつてフィリップ・グラスが1銭も手にすることができなかった数々の奨学金や助成金を手にしたマリア・チャヴェスはマース・カニンガム・ダンス・カンパニーのレジデントとなり、ターンテーブリストの草分け的存在であるクリスチャン・マークレイとも共演、さらにはパウウェルやリック・ウェイドといったDJカルチャーのプロパーだけでなく、サーストン・ムーアやリディア・ランチといった野獣のようなアウト・オブ・アカデミズムとも親交を持っているという(『いだてん』で勇壮としたサウンドトラックを奏でる大友良英とも)。マリア・チャヴェスはペルー生まれ。ターンテーブリズムに関する著作も。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE