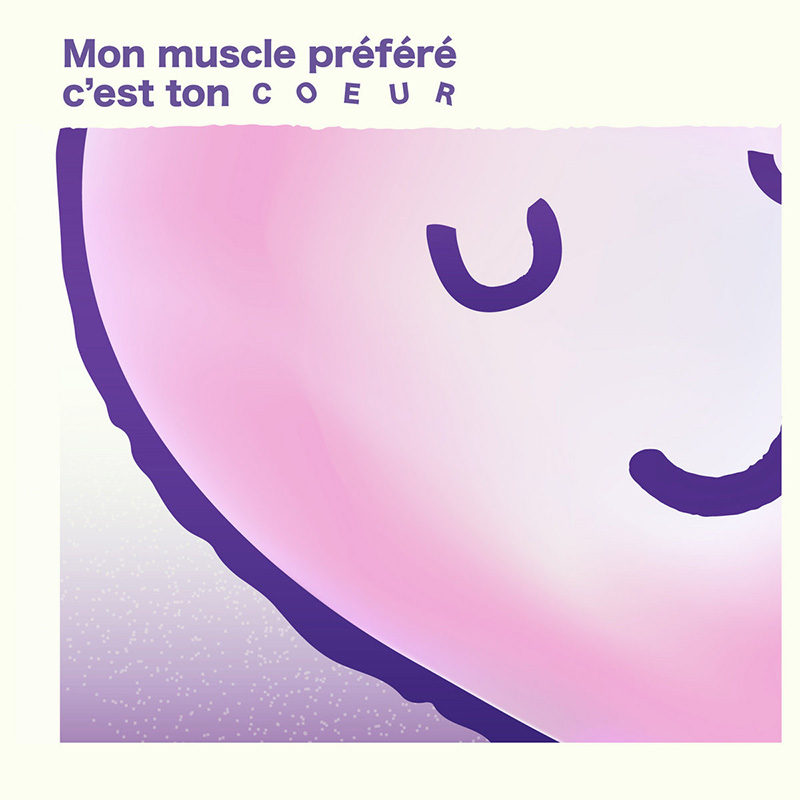MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Various Artists- tiny pop - here’s that tiny days

コンピレーション・アルバム『tiny pop - here's that tiny days』は、インターネットから生まれた新しいポップ・ミュージックの始まりを告げる大切な記録だ。本作に収録されているアーティストたちの楽曲を聴いていると、リヴァイヴァルの文脈が海外のシティ・ポップ・リヴァイヴァルとはいささか異なっていることに気が付く。海外のマニアの参照地点からは取りこぼされた音楽からの継承を感じるのだ。
ここで本作と繋がる重要な二作を挙げよう。1982年にリリースされた大貫妙子『Cliché』と1987年にリリースされたピチカート・ファイヴ『カップルズ』である。この二作に共通するのは「小さな宝石箱のようなポップ・ミュージック」という点だ。フランス音楽とアメリカ音楽の上品な香水のよう音楽性と、日本語と旋律の交錯。それはチャートを席巻するような「大袈裟さ」とは無縁の、小さな美しいメロディとハーモニーによる日本のポップ・ミュージックの理想型であった。そして日本が豊かだった(とは何か?)時代に生まれた珠玉のポップ・ミュージックでもあった。
この「小ささ」と「豊かさ」こそ「tiny pop」へと継承されるものだと思う。提唱者にしてアルトサックス奏者でもある山田光は「tiny pop」を「インターネット上にあるプライベートな音楽の中でも歌謡曲の記憶を聴く者から引き出すような音楽」「DIY歌謡曲」と定義している。むろん若いアーティストばかりであるので、80年代の音楽の援用はほとんど無意識なのかもしれないが大切なものなのだろう。なぜならポップとは無意識の発見と発露でもあるのだから。
では「豊かさ」とは何か。「豊かさ」はこの時代にあって反転して継承される。つまり微かなアイロニーを含んだ憧れとして、である。たとえばアルバム冒頭に収録された西浦マリのソロ・ユニット mukuchi の “午前十時の映画祭” などは、私にはまさにピチカートの『カップルズ』の楽曲のように聴こえた(特に “七時のニュース” などの鴨宮諒の楽曲群)が、しかしこの曲は、87年に制作されたピチカートの曲とは異なり、現代のムードを濃厚に捉えているのだ。特に「ツタヤでは100円でレンタルできる名画を映画館に観に行くことの贅沢さ」をいささかのアイロニーと共に歌っている点は重要に思えた。80年代・90年代とは違う「この時代特有の捻じれた不景気さ」(その意味でバブルが崩壊直後の状況を歌っていた第三期ピチカート・ファイヴとの繋がりを考えてしまう)。ちなみに西浦マリ= mukuchi は関西の漁村に在住し、これら珠玉の印派的なDIY歌謡曲を制作したという。
以降、各収録曲の詳細と解説はCDに付属のライナーに書かれているので、ぜひともCDを購入してそちらを読みこんでほしいので、ここでは簡単な楽曲の紹介にとどめたい。まず関西在住のトラックメーカー SNJO による “Ghost” と SNJOとゆnovation “Days” は、80年代AORと90年代渋谷系と00年代ダフト・パンクを交錯されたタイニー・ファンク・AOR(+ラップ)といった楽曲。
wai wai music resort の “Blue Fish” は、ミニマルなエレクトロニック編成のハイ・ラマズのような趣の箱庭ポップで、メロディの切なさが胸に迫る。wai wai music resort で作詞・作曲・編曲を務めるエブリデのソロ名義 “牛の記憶” はキリンジ直系の捻じれた叙情が堪らない名曲だ。そして「tiny pop」の提唱者であり、コンピレーションの監修者で、サックス奏者にしてインプロヴァイザーである山田光が「しょぼいポップス」を作ろうと天啓を受けて始めた feather shuttles forever の “ウェルウィッチア” は、「ele-king」の野田努氏のアイデアという「ウッドベースとサックスのサンプルとボサノバ的なギター」から始まった楽曲。「ジャズとポップの融合」だが大げさにならず、慎ましやかで、しかしジャズにもボサノヴァにも「似ていない」洗練された演奏と編曲が耳を潤してくれる。アルバムを締めくくるに相応しい名曲だ。ヴォーカルは mukuchi の西浦マリ。
ここでとんでもない爆弾級のアーティストをひとつ飛ばしていることにお気づきだろう。そう、日本アンダーグラウンド・フォーク音楽の系譜を継ぐ「ゆめであいましょう」というユニットだ。
ゆめであいましょうは作詞・作曲・編曲の宮嶋隆輔とヴォーカルの蒲原羽純によるユニット。本コンピレーションには “見えるわ”、“シャンマオムーン”、“誰もが誰かに” の3曲が収録されているが、まるで80年代の未発表歌謡曲のような、もしくは売野雅勇と芹澤廣明コンビの知られざる女性アイドルのデモテープのような、というかそもそも過去も未来も関係なく80年代そのものがあるような、要するにここまで書いてきたことをすべてひっくり返すとんでもない劇薬のようなDIY歌謡曲なのである。これは何か?
時間と空間をゆがめるような言葉の真の意味でサイケデリックとしか言いようがない感覚。じっさい DX-7 のようなシンセの音色と80年代歌謡曲のような歌唱は、作為や天然を超えて「そのもの」という存在感がある。
そう、ゆめであいましょうにおいては、シティ・ポップ・リヴァイヴァルも失われた過去もすべて吹き飛んでしまうのだ。「本当の過去」を蘇生する力というべきか。これが現在の曲なのか。という疑問は、しかしこれは現在録音された音楽なのだという事実に否定される。心底、驚いた。ゆめであいましょうの3曲を収録したコンピレーションの監修者は本当に素晴らしい仕事をしたと思う。
ともあれ全11曲、すべて綺羅星のような現在のポップ・ミュージックである。そしてパーソナルな音楽でもある。コンピューターによる作曲・録音環境と、インターネットによる楽曲の発表と配信が整備された時代だからこそ、生まれ、発表され、聴かれ、そして編まれた貴重な作品たちといえるだろう。このCDには「2020年の夜明けに相応しい新しい音楽シーン」が瑞々しく息づいている。20年代の始まりにぜひとも耳を傾けて頂きたい。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE