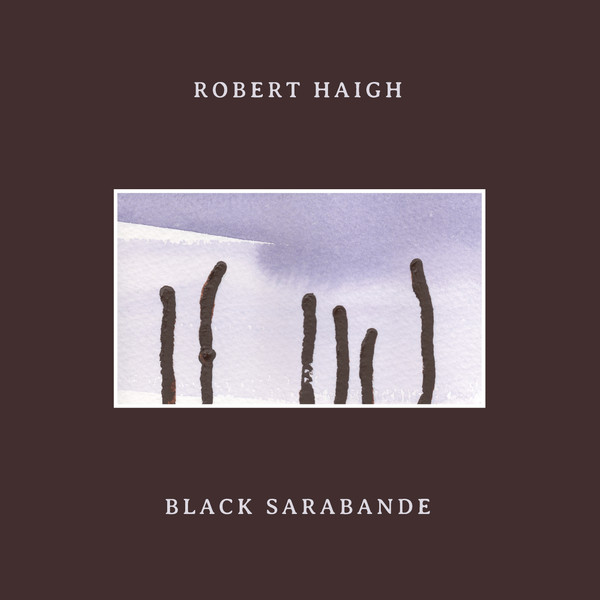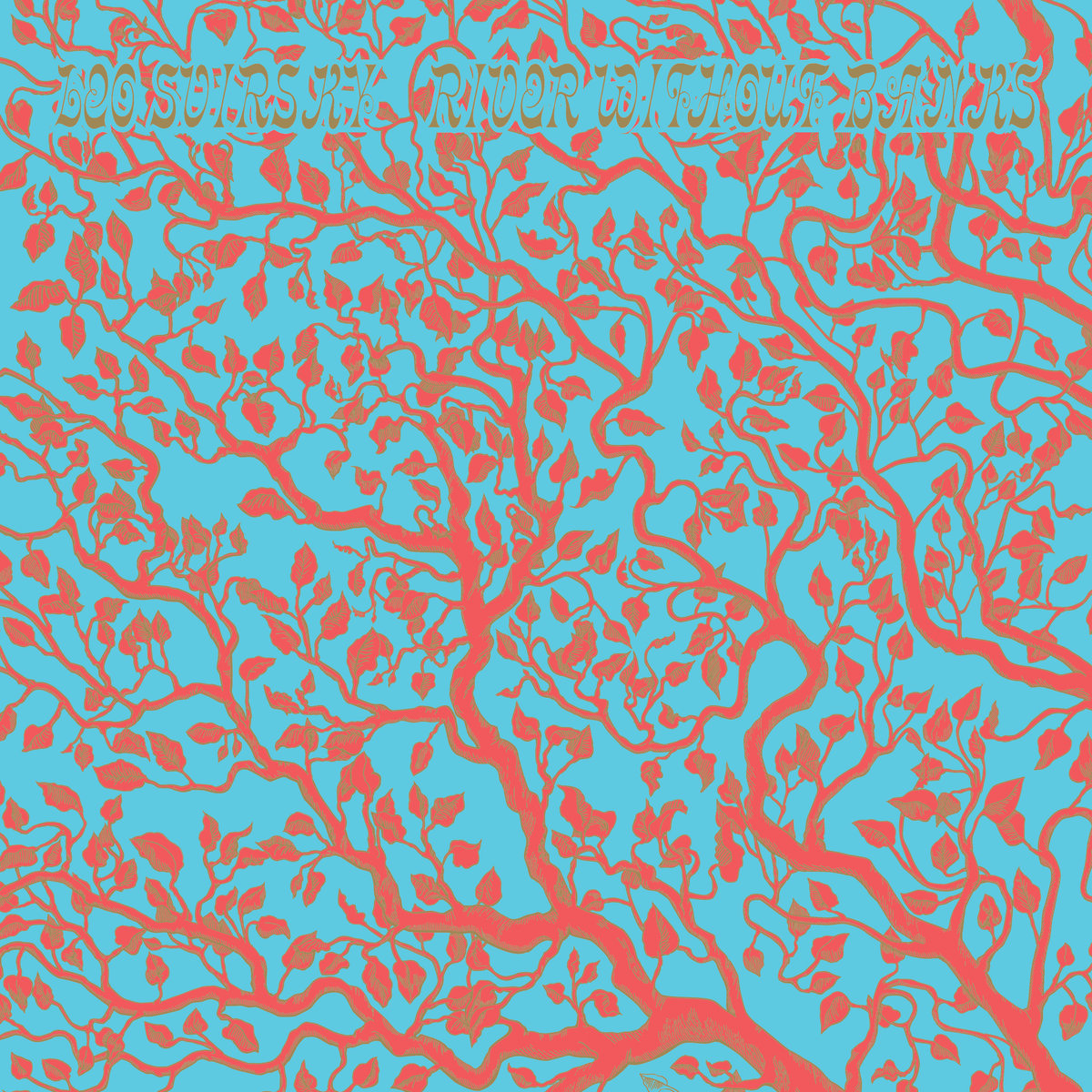MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Robert Haigh- Black Sarabande
ぼくは小1から小6まで、柔道の道場に通っていた。夜の6時から8時まで週に3回、バスに乗って片道30分。道場は安倍川を越えた市の外れにあった。最初の2年間は弟と2人で通ったが、途中からは1人だった。バスはいつも空いていて、ぼくはいつも窓の外から見える寂しい夜の通りと川の向こうに見える黒い山々、その山腹に見える小さな光に見とれていた。不思議なもので記憶では、一緒に稽古した子たちの顔も道場の練習もぼんやりとしているというのに、バスから眺めていた夜の景色だけは、その景色をいつも眺めていたことだけはよく憶えている。
どんな人間にも、そうした自分の遠い過去の日常のなかの、喜びとも悲しみとも違う、誰かと共有していたわけでもない、郷愁というほどの懐かしさでもない、なかば色褪せながら、しかしいまでも吸い寄せられてしまいそうになる景色があるのだろう。ロバート・ヘイの音楽が呼び覚ますのはそんな景色だ。こども時代に見とれていた寂寥とした日常のひとコマ、たわいもない風景への切ない気持ち。
ロバート・ヘイは、90年代にドラムンベースを聴いていた人にはオムニ・トリオの名前で知られている。オムニ・トリオは、ゴールディーや4ヒーローを初めて聴いたときのような〝ほかと違った〟衝撃を携えたアーティストだったが、彼のスタイルは〝アンビエント・ドラムンベース〟と呼ばれたように、その音楽の背後にはいわゆるダンス・ミュージック以外の何かがあった。調べていくと、彼が80年代にナース・ウィズ・ウーンドの名作『The Sylvie And Babs〜』に参加していたことがわかった。ポストパンク時代にはSema名義で、ドビュッシーないしはサティ風のピアノを主体とした実験音楽作品を出していることもわかった。寂寥とした響きの、壮麗さはないが地味に美しい作品である。
いまロバート・ヘイのディスコグラフィーを見れば、オムニ・トリオ時代が異例であったことがわかる。レイヴフロアから離れ、イングランドの田舎に越してからのヘイはふたたびピアノに向かい、何枚ものアルバムを発表している。日本のアンビエント/ドローン/モダン・クラシカルのレーベル〈Siren Records〉からも何枚も佳作を出しており、前作『Creatures Of The Deep』からは現在カール・ストーンなどが所属する〈Unseen Worlds〉がリリース元となっている。
ロバート・ヘイには駄作/失敗作というものがない。すべてが良い。その代わりにこれこそ傑作と呼べるものもない。80年代初頭からコンスタントに作品を出している彼のキャリアには(オムニ・トリオ時代を除けば)特別なピークというものがなく、が、そのことは彼の飾り気のない表現における魅力となっている。ハイにもならずロウにもならず、変わりなくピアノがただメロディを奏で、リズムを取っている。なんとも言いようのない、色褪せた風景や寂寥さのなかに包まれていくときのなかば陶酔じみた感覚。
新作『ブラック・サラバンド』にもそれがある。まあ、それでしかないというか。だからぼくはロバート・ヘイの音楽を聴いている。静かな時間が好きな人にはオススメです。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE