MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Emeka Ogboh- Beyond The Yellow Haze
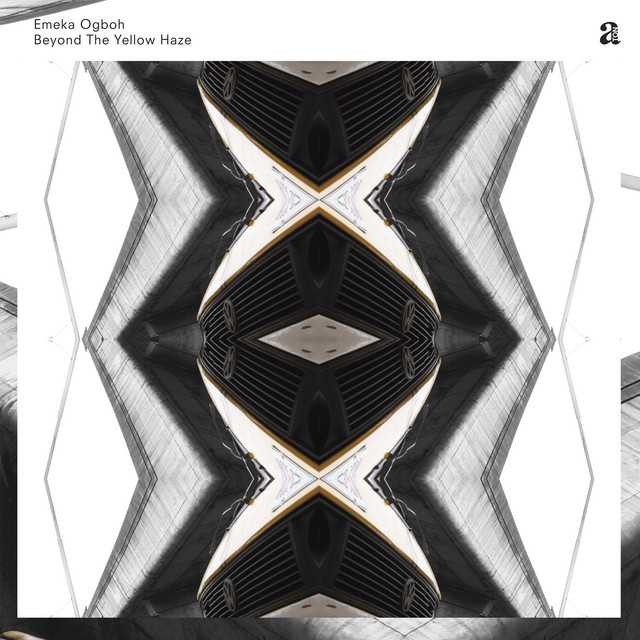
どこにも行けないこの部屋でも鳴り響き、アフロビートの陶酔で未知のラゴスの雑踏を幻のようにたぐり寄せる。ひとときの白昼夢を見せるアフロ・ビートダウン──エメカ・オグボー『Beyond The Yellow Haze』は、2021年のはじまりとともにベルグハイン系列のレーベル〈OSTGUT TON〉傘下〈A-TON〉からリリースされた作品。なんというか、いつまでも聴いていたくなるような、ミニマルな陶酔に文字通りハマる作品だ。
エメカ・オグボーは、ナイジェリアはラゴス出身のアーティストなのだが、これまでのその活動領域はいわゆるコンテンポラリー・アートにある。すでにそちらの領域においてはそれなりにキャリアのあるアーティストで、これまでにヨーロッパやアメリカなどでそのインスタレーション作品は展示され、いくつかの賞レースもものにしているとのこと。その生活圏もベルリンとラゴスを行き来しており、現在はこのコロナ禍でベルリンに留まらざるをえない状況が続いているという。彼のインスタレーションの多くはラゴスの都市をテーマにしたもので、形式的にはラゴスのフィールド・レコーディングや映像、そして彼の音楽で構成。6年に及ぶベルリン生活で培った電子音楽の感覚と、ラゴスの雑踏が彼の作品のインスピレーションであり、そのテーマは比較的政治的な問題(権利、ナショナリズム、外国人恐怖症、人種差別など)を提起するものだという。最近ではリアーナやビヨンセなどもSNSなどで連帯を呼びかけた、ナイジェリア警察の「対強盗特殊部隊(SARS)」による暴力行為へのデモ活動にシンパシーを寄せ、また作品としても今後とりあげることを示唆している。
さて、話はずれたが、今回のリリースはこのコロナ禍のある種の偶然によって呼び込まれたものだという。この状況でクラブ営業のできない〈ベルグハイン〉、そのメイン・フロアは現在アートスペースとしてときおり活用されているようで、オグボーの作品がとあるアート・イベントで展示されていたのだという。そして、そこで展示されているオグボーの作品を〈OSTGUT TON〉のスタッフが見初め、そのサウンドに衝撃を受け彼らは、今回のリリースへと歩みを進めたということなのだ。
という感じなので、これまでに私家版のような形でインスタレーション時に販売された作品と、パフィンランドの、Ilpo (パンソニックの生きている方とは別人)なるアーティストと1枚 Bandcamp にてリリースのみなので、ほぼ音楽作品としてのリリースはコレがデビューといっても過言ではないだろう。また、ここ数年盛り上がるアフリカのエレクトロニック・ミュージックの隆盛という流れ(詳しくは紙 ele-king の三田格氏の原稿を参照)に目を移せば、その手のアフリカ由来のアヴァン・エレクトロニクスや実験音楽を集めた2020年の名コンピ『Alternate African Reality – Electronic, electroacoustic and experimental music from Africa and the diaspora』(そちらは今回の作品とは違ったラゴスの街なみで録音されたとおぼしき完全なフィールド・レコーディング作品)にも収録されている。
ちなみにリリース元の〈A-TON〉は、エフデミン名義で知られるフィリップ・ソルマン名義の作品やマルセル・デットマン(+α)によるプロジェクトなど、アンビエント~エクスペリメンタルなエレクトロニック・ミュージック作品、もしくはルーク・スレイターのリスニング方面の名義たる 7th Plain 名義の未発表集成をリリースするなど、完全フロア対応の〈OSTGUT TON〉に比べてリスニング色の強いサブ・レーベルとなっている。
さて本題の『Beyond The Yellow Haze』だが、内容としては長尺の楽曲4曲+フィールド・レコーディングなアウトロで構成されており、ダンス・ビートはそこにあるものの、そのチルな雰囲気は、やはりこれはアンビエント・テクノと言ってもよさそうな質感が全体を支配している。ラゴスの雑踏からスタートする “Lekki Aiah Freeway” は、ポリリズミカルなパーカッションから徐々にアルバムが立ち上がるように不穏なグルーヴをミニマルにゆっくりとつむいでいく。そして本作のハイライトとも言えるのは11分を超える2曲目 “Danfo Mellow” だろう。まるでエイフェックス『Selected Ambient Works 85-92』のクリアで内省的なサイケデリアを、セオ・パリッシュがモコモコとアブストラクトでポリリズミックなアフロ・ディープ・ハウスでミニマルにミックスしたような感覚というか、どこまでも続いていくようなアンビエント・タッチのアフロ・ビートダウンだ。またこの曲名の “Danfo” というのはラゴスの街中を縦横無尽に走る黄色いバス(乗り合い?)のことのようで、まさにラゴスの街を象徴する、住民の移動手段だという。気に鳴る人はオグボーによる短い映像がBBCにあがっていたのでそちらをぜひ(https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51210773)。
続く “Everydaywehustlin” は、骨太なブレイクビーツを足場に不穏なループがひょこひょことラゴスの街を歩き回るトリップホップ。そして雷雨のなかを、祈りなのか物売りなのか雑踏の呼び声がループする “Palm Groove”、そして短いフィールド・レコーディング “Outro” でアルバムは幕を閉じる。アルバム全体を貫く、前述の様なアンビエント・タッチの抑制された響きというのは、ひとつ、このラゴスという街を表象させる作品において、少し陰鬱でノスタルジックを呼び起こす。それは帰郷を果たせぬエメカ・オグボーの心象風景からくるものなのかもしれない。またアルバム全体の陶酔の響きは、どこかモーリッツ・フォン・オズワルド+故トニー・アレンによる『Sounding Lines』、その躍動感を排した麻酔のようなアフロビート、そのさらにアンビエントへの展開を彷彿とさせるサウンドでもある。
河村祐介
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE
