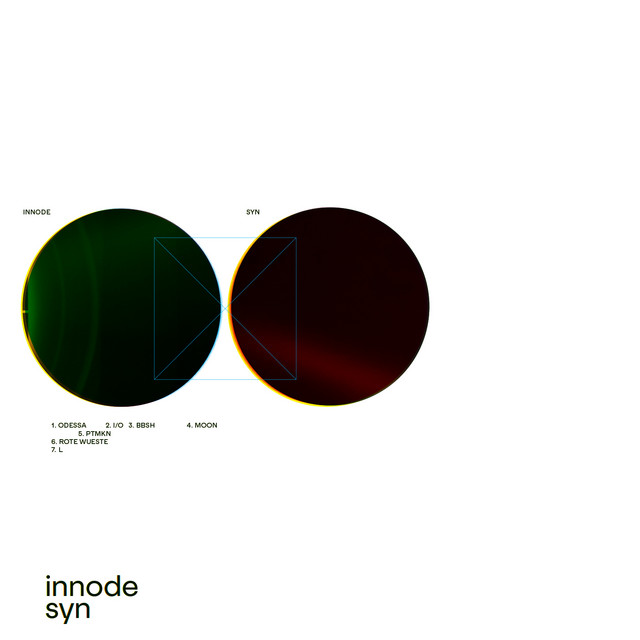MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Innode- Syn
2010年代初頭において音響と音楽の実験とは何だったのか。グリッチ? インダストリアル? ノイズ? ドローン? ミュジーク・コンクレート? それらは自ずと00年代以降の「音楽の尖端とはなんだったのか」「音楽のノイズとは何だったのか」という問題に行きつく。その問いの答えを示す作品のひとつが2013年にリリースされたインノードのファースト・アルバム『Gridshifter』だったと仮定してみたい。
『Gridshifter』は、90年代以降におけるグリッチ美学の応用による電子音響作品が定着してきた00年代~10年代初期において、「音響/音楽の先端/進化とは何か」という命題を「演奏」と電子音の「生成」の両極から追求した極めて重要なアルバムだった。『Gridshifter』にあるのはサウンドをエディットし、別の方法でノイズと音楽を交錯させていくという音響実験と音響実践である。となればつまるところ00年代~10年代の先端的な音響とは「ノイズ」の新しい活用方法を実践したムーヴメントだったといえるはずである。
インノードの中心人物であるステファン・ネメスは、あのラディアンのメンバーでもあったので、オーストリアの音響派系譜の中で重要な人物である。ゆえにこの「ノイズと音楽の新しい方法論」の問題に行くつくことは当然のことかもしれない。私見だが〈Thrill Jockey〉のラディアンに対して、〈Editions Mego〉のインノードを重要な二本の柱として置いてみるとオーストリアの、ひいては00年代中盤以降のエクスペリメンタル・音響派の豊穣さが分かってくるような気もする。
そのような電子音、ノイズ、音楽、音響、演奏、解体、再構成。これらの要素を分解しミニマルな素材として蘇生し、それをコンポジションに用いるように音楽/音響へと変換していくような「ノイズの新しい方法論」は、ファースト・アルバムから8年の月日を経てリリースされたセカンド・アルバム『Syn』でも変わらず継承されていた。いや、そのコンポジションの手腕はさらに研ぎ澄まされていたとでもいうべきだろう。
電子ノイズの嵐のような炸裂を経て、瀟洒でミニマルなサウンドへとギアチェンジするような1曲め “Odessa” からして凄まじいのだが、アルバムの本領が全面化するのが続く2曲め “I/O” からだ。硬質なドラムの音色が空間を切り裂くように炸裂し、ワンコードで刻みつけるベースに強烈な電子音・ノイズが冷徹に蠢く。3曲め “BBSH” と4曲め “Moon” でも同様に鉄のようなドラム/ビートとノイズがミニマルに、かつ強靭に交錯し、聴覚がどんどん覚醒していくかのような透明にしてハードな音響空間を生みだしていくのだ。
そして静寂と炸裂を交互に繋げるような複雑なコンポジションである “Rote Wueste” ではリズムとノイズという本作の(インノードの)のコンセプトを突き詰めたようなサウンドを構築する。この曲に限らないが本作は硬質なビートに対してメタリックなノイズ・サウンドがまったく引けを取っていないことが重要なポイントに思える。
そのノイズ・コンポジションが本アルバム中、もっとも結晶しているのがアルバムの最終曲 “L” だ。アルバム中、もっとも静謐なムードの曲だがミニマルなリズムに微かなノイズがレイヤーされていくトラックの精度と密度はアルバム中随一といえる。途中から展開するトライバルなムードのリズム展開も含めて、まるでトーマス・ブリンクマンによるミニマル・テクノといった趣の緊張感に満ちた持続を実現しているのだ。
全7曲、このアルバムのすべての曲は、リズムに対するノイズの位置付けを問い直し、リズムの位置付けをノイズの側から問い直すような緊張感がみなぎっている。前作からリリースが8年ほどの歳月を必要としたことも、そのサウンドとノイズの緊張関係を維持したまま、作品に落とし込むために必要な時間だったのだろう。ステファン・ネメスは、本作によって、自身が2020年代においても重要な音響作家であることを見事に証明してみせたのである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE