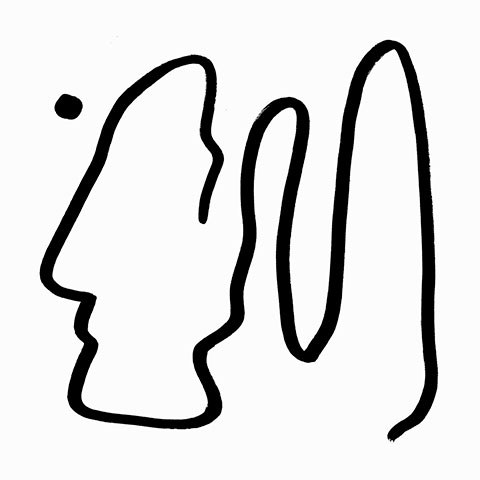MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > John Also Bennett- Out there in the middle of nowhe…

『Out there in the middle of nowhere』の幕開けを飾る “Nowhere” のスチール・ギターの音が聴こえてきたとき、ぼくはかなり意外な気持ちだった。彼が関わる作品を聴くときに期待している柔らかなミドルを、スチール・ギターの持つ鋭い高音が引き裂いてしまったからだ。ここからもわかる通り、今作はいままでの彼の作品に対して批評的な視点を持つものだ。
と、話を進めてしまう前に、JAB こと、ジョン・オルソー・ベネットという作家について掘り下げておいたほうがいいだろう。彼は〈Kranky〉からもリリースがある、フォーマ(Forma)というシンセ・ウェイヴ・バンドで活動をするかたわら、妻である Christina Vantzou との共作を2018年、2020年に1作ずつリリースしている。どちらも、まるでそよ風や水の流れる音が持つ空気感を音響に精錬したかのような、シンセサイザーやピアノのやわらかい音が印象的な作品だった。その音響へのまなざしは、いままでの彼のリリースをいくつか手がけている、〈Shelter Press〉を運営する実験音楽家、フェリシア・アトキンソン と共通のものがあるだろう。
またソロ名義である JAB の作品においては、共作でも使用されていたフルートによる音響構成をさらに練り上げている。波打つドローン・シンセの音と、フルートの少しカサついた質感が絡みあう、2019年作の『Erg Herbe』はリラクゼーションばかりではなく、精神世界に沈滞していくような瞑想性を持つ名作だった。
そうした JAB の作家性を前提とすれば、冒頭一曲目、“Nowhere” のスチール・ギターが生み出す強いアタック音は、彼がいままで紡いできた、あらゆる「でっぱり」や尖りをヤスリで削った、ビロードのような音響感覚から離れたものであることがよくわかるだろう。しかしゆったりとしたタイム感で奏でられるスチール・ギターのバッキングが繰り返されるうちに、スチール・ギターの長い残響から、本来減退するべき余韻が自律し、特定の周波数がせり出てくるような不思議な音場が立ち現れていることに気が付く。
その音響の変化は決して劇的ものというわけではない。ギターらしいキラキラとしたアタック音の本体は残ったまま、その残響がひとつの独立した音響──以前の彼らしい、ドローン・シンセ的なサステインの長い発信音──にまで引き伸ばされていく。リリース・インフォによるとこの独特の音場は、スチール・ギターの響きに加工を加えることで作られたもののようだが、それはまるで彼の以前までの作品のもつ現代的な音響感覚が、毛羽だったスチール・ギターのクラシックな音響のなかから削り出されていく過程そのものを表現しているかのようだ。
またこの「過程」は、アルバムの進展のなかでも表現される。今作の最終楽曲(デジタル版ではボーナス・トラックが一曲追加されているため最後から二番目の楽曲となる)“Embrosnerόs” では、JAB が以前から好んで使用した DX7 のシンセの音と、スチール・ギターの引き伸ばされた残響が混ざり合い、ひとつの「層」のような音響が構成されており、スチール・ギターの尖った響きはすっかりそこに飲み込まれてしまっているのだ。
ところで本作は、サウスダコタ州のバッドランズの地形や風景から霊感を受けたものであり、録音自体もバッドランズ国立公園でおこなわれているのは興味深い。乾燥した気候と植生の貧しさゆえ、バッドランズでは水と風による浸食作用が激しく働き、複雑な谷と崖が形成され、谷や崖の断面には数万年かけて堆積していった砂や泥や粘土が層をなして折り畳まれているという。
おそらくこの作品には、バッドランズの地層に宿るような、壮大な時間に対する諦念のような感覚があるのだ。動植物の死骸が経年のなかでカラカラに乾燥した砂礫に変わり、滑らかな地層を形成していくように、スチール・ギターのとがったアタック音はのっぺりとしたテクスチャーにすり潰され、『Out There In the Middle of Nowhere』というひとつの「地層」のなかに織り込まれていく。またバッドランズで録音されたであろう、乾燥した草の擦れる音や砂礫を踏みしめる靴の音などの今作に配置されている様々な環境音にしても、時間の流れのなかに溶け去ってしまうことをあらかじめ知っているかのような哀愁を湛えている。
JAB がいままで志向していたニュー・エイジ〜アンビエント的な柔らかさが、感情の起伏を忘れさせていくようなある種の無時間性をもつものだとしたら、今作は経年劣化の過程、時間の流れそれ自体をぼくらに意識させる。いや、単に「時間の流れ」といってしまうのは正確ではないだろう。『Out there in the middle of nowhere』は地層を形作るほど途方もない時間のなかにぼくらを運び去るのだ。意識も、身体も、それらが作り出す自他の境界も、スチール・ギターの鋭い輪郭も、すべて崩れ去っていくほどの長い時間……。
ここにあるのはいくらかペシミスティックで、荒涼とした想像力かもしれない。しかしこのようなイメージは、ソーシャル・メディアの発達ですっかり肥大化してしまった自己意識と、それが形作るプライベートな時間に閉じ込められてしまっているぼくらを、別の時間の尺度のなかにセットし直してくれるものでもあるはずだ。
原音よりも長く引き伸ばされたスチール・ギターの残響が教えてくれる通り、ぼくらの自己意識が経験している「ウェットな」時間よりも、感情や精神がすっかり抜け落ちてしまったあと、ぼくらの物理的な身体が経験するであろう「ドライな」時間の方が、ずっとずっと長いのだ。
島崎森哉
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE