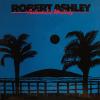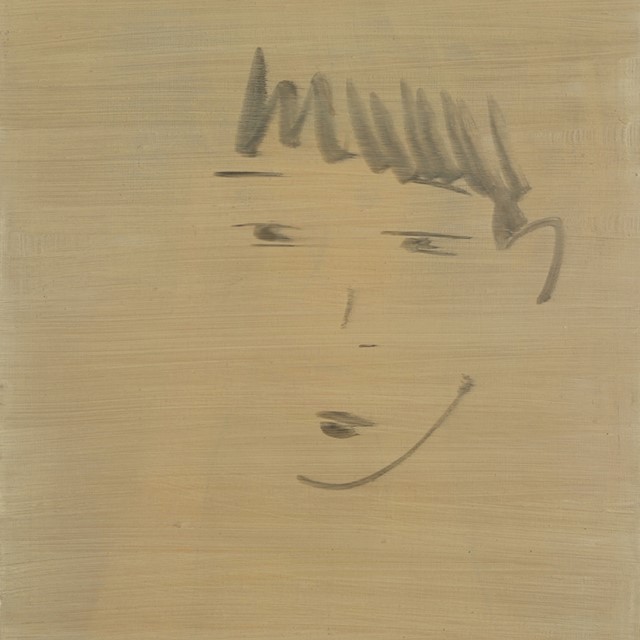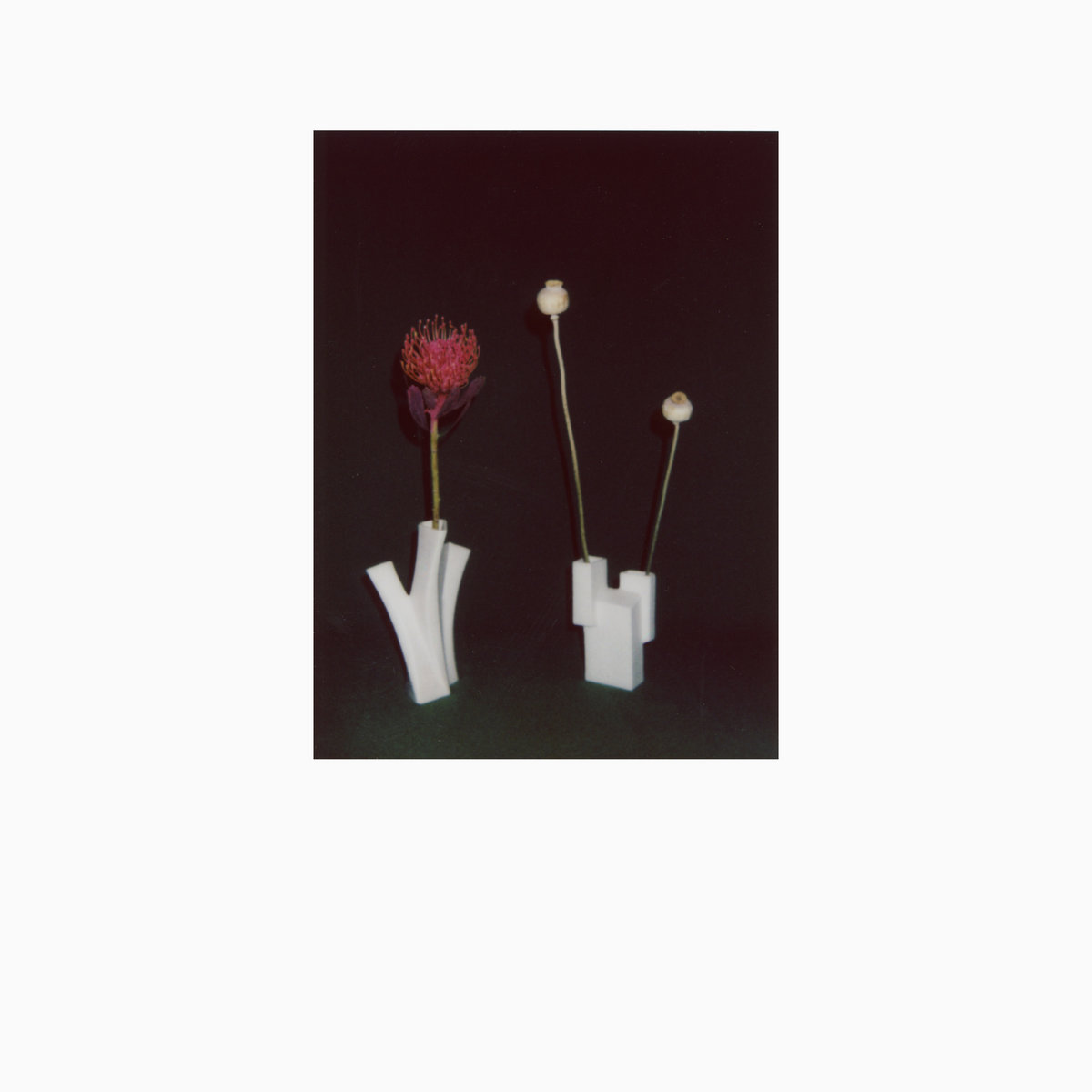MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Félicia Atkinson- Image Langage

ブライアン・イーノの「非音楽家(ノン・ミュージシャン)」というコンセプト、あれは「楽器が弾けないけれど音楽を作れる」という表現よりも、「誰もがミュージシャンである」という逆説的な言い方のほうが意味は深くなる。ジョン・ケージの“4分33秒”ではないが、聴こえる音すべてが音楽であり、われわれはつねに音楽に囲まれているというコンセプトが、音楽というものの可能性を阻害する制度のいっさいに抗することでもあるように。その昔フェリシア・アトキンソンは、タイニー・ミックス・テープの取材に応えて、(ミュージシャンがリスナーに対して)「聴いて楽しんでほしい」と言うのはちょっと下品でしょう、と言った。「そうではなく、リスナーとミュージシャンが一緒にフォームを作って、そしてそれを問うこと」
音楽を聴くという行為も創造的なのだから、最初から一方通行的に与えられたものを楽しむ(消費する)だけでは、音楽の可能性を矮小化してしまっている、もったいない、アトキンソンにしたら、そういうことなのだろう。だから自分の音楽がアンビエントと括られることにも、彼女なら窮屈に感じているんだろうな。これはバックグラウンド・ミュージックではないし、静的であることは、必ずしも平穏さや瞑想に着地するわけではない。静けさとは力強さだ、アトキンソンなら言う。
それにしてもアトキンソンの学際的な探究心とその豊富な知識、柔軟な思考やそのとめどない理屈には舌を巻くばかりだ。ディレッタント的と言ってしまいそうだが、彼女の場合の知識は、自身の芸術的な欲望を穴埋めするような趣味的に蓄積されたものではない。フランスの、労働者階級出身でフェミニストの知識人は、どれだけ自由で平等で、創造的な人生を歩めるのかという実践における養分として、ジョーン・ディディオンからジル・ドゥルーズ、アンドレ・ブルトンからジャック・ケルアック、ギー・ドゥボールからジェイムズ・ジョイス等々たくさんの書物を横断的に読む。ただ学ぶのではなく「逸脱して学ぶこと」、そう彼女は言う。読書することひとつ取っても創造的な行為で、だからリスニングに関しても、集中して聴くことが唯一正しいリスニングではないと考えよう。リスニング行為それ自体にも思いを巡らせるのだ。(誤解されているようだが、彼女の創作とASMRが無関係であることは、TMTのインタヴューを読むとわかる)
彼女の新作は、12歳でロバート・アシュレーを聴いた彼女が「声」における音楽的魅力について考察していたように……、と、ここまで書いたがいったん中断して、もう少し彼女の経歴を書いた方が良さそうなのでそうする。
彼女はいわゆるエリートではないし、幼少期からクラシックを学べるような裕福な家の出でもない。経済力はないが文化を愛する両親のもとに生まれ、ビョークとキム・ゴードンとキャット・パワーとPJハーヴェイをアイドルとした思春期を過ごしている。90年代は『NME』と『The Face』を愛読し、マッシヴ・アタックとトリッキーのライヴを見たくてパリからブリストルに向かったのは16歳のときだった(けっこうミーハーである)。高校卒業後に学校で音楽を少し学んではいるそうだが、自分に合わなかったと辞めている。もっとも重要なことはジョン・ケージから学んだと公言しているが、それは独学。27歳で東京の〈Spekk〉からデビューするまでは、演劇の音楽をやったりしていたそうだ。
また彼女は、自分のスタジオを持たないことを主義としている。リルケのように旅を好み、旅をしながら創作しているそうだ。初期はiPhoneやガレージバンドを使って作っていたほどで、Je Suis Le Petit Chevalierなるロック・バンドも同時にやっていたような人だったりする。自分自身を、作曲家でもポップ・ミュージシャンでもないローリー・アンダーソンや小野洋子のような中間的な存在に重ねている。そんな彼女が12歳でロバート・アシュレーを聴いたのは、看護師だった父親の趣味として家にシュトックハウゼンやジョン・ケージやアルヴィン・ルシエやコーネリアス・カーデューなんかのレコードに混じってそれがあったからだった。
で、そう、彼女は大人になってアシュレーを再発見し、これまでも自身の作品において「声」はさんざん使っている。デンシノオトや渡辺琢磨のような昔からのファンにはもうお馴染みの「声」だろう。それでもアトキンソンにとっては、ゴダール映画、および『二十四時間の情事』、およびロベール・ブレッソン映画のような「ささやき声」を効果的に使っている映画作品から受けたインスピレーションを音楽のなかで全面的に応用することは、かねてからやりたかったことのひとつだったようで、それが本作『Image Langage』になった。
もうひとつの動機としては、ゴダール映画におけるアンナ・カリーナの「ささやき声」のように、画像がなくても「声」のみで物語は構築できるというコンセプトがあった。この話を抽象化すると、以下のようになる。インターネット以前に人が得ていた情報源は、おもに身の回りにあった。本やレコードはもちろん、石や海辺もそうだった。それらは本と同じように、人がそのページを開くのを待っている。ひび割れるのを待っている、何かが明らかにされるのを待っている、開かれるのを待っている、そういう考え方にあると彼女は説明している。たしかにそうかもしれない。その気になれば、「声」それ自体からも音楽は聞こえるのだから。
幸か不幸か、ぼくにはフランス語がさっぱりわからない。少しだけ英語も混ざっているようだが、ぼくのリスニング行為においては、必然的に、意味に左右されることのない音としての「声」が曲の構成要素のひとつとしてそこにある。ほのかな電子音とサックスが交流する1曲はインストゥルメンタルだが、“湖は話している”以降からは、ピアノや電子音の断片が控えめに描く風景のなかで、「声」が聞こえる。リスニングの旅をうながすサウンドと「声」のコンビネーションが、自然のイメージを仄めかすこともあれば、各々の物語をふくらませることもあるだろう。表題曲が素晴らしく思えるのは、それがまさに感性の彷徨をうながすからで、アメリカの詩人シルヴィア・プラスに捧げられた曲における不安定さにもぼくは魅力を覚える。まあ、ほかの曲に関しても、いつもとは違ったエクスペリエンス(音楽体験)において、だいたい良い気分になってしまうのだ。高尚な主題を、それこそアカデミックな実験音楽とポップ音楽との中間にまで調整させてしまえるだけの力量がこの人にはあるし、アトキンスの澄んだ音響には人をネガティヴにさせる要素がないので、ぼくはすっかり“楽しんでいる”。あ、ちょっと下品だったかな?
イーノにしろ、アトキンソンにしろ、理屈っぽい人の作る音楽が必ずしも理屈っぽいわけではなく、エクスペリメンタルであることが音楽を難しくすることではないわけで、そもそも「実験」というのは、「結果がどうなるかわからないけれどやってみよう」ということを意味している。リスニング行為もまたしかり。それはオウテカが言う「慣れてしまうことに対する抵抗」だったり、アトキンソンの音楽のように迷うことの楽しさであったり、だいたいやってみてもいないのに、見たことがない世界を見ようってこと自体が無理な話なのだ。音楽にできることはまだある。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE