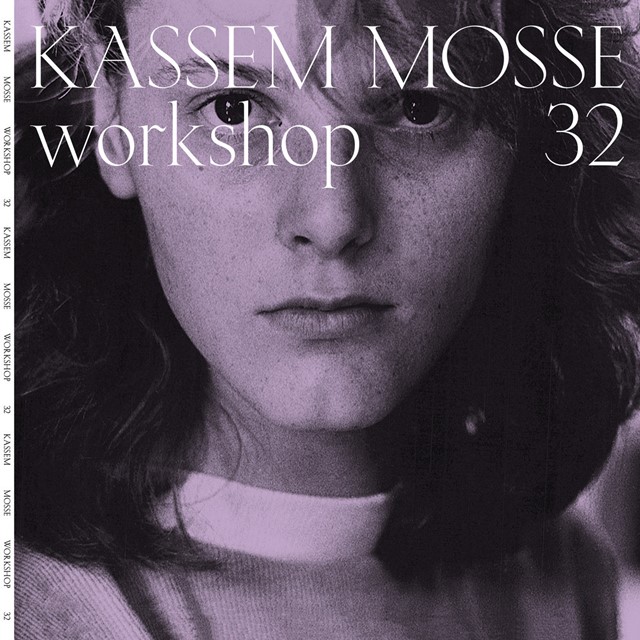MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kassem Mosse- workshop 32
ガンナー・ヴェンデル、カッセム・モッセ名義4枚目のアルバムは古巣、ロウテック率いる〈Workshop〉から。本名義での〈Workshop〉からのリリースはというと、コレより前がファースト・アルバムにあたるLP2枚組『Workshop 19』が2014年、ということでココからのリリースはじつにひさびさ、9年ぶりの作品となるわけですね。もろもろのコラボやライヴ盤などを除くと名門〈Honest Jon's Records〉からの2016年『Disclosure』、続く、自身のレーベル〈Ominira〉からは『Chilazon Gaiden』を2017年にリリースしています。またマンチェスターのレフトフィールド・テクノなレーベル〈YOUTH〉(〈PAN〉の切り開いた「その後」を個人的には感じてしまうレーベルです)から、別名義の Seltene Erden で2020年にリリースしたり。また上記のようにコラボや DJ Residue 名義で〈The Trilogy Tapes〉からアブストラクトな電子音響作品『Residual Manifesting』のテープ・リリースもありますが、今回は待望の本名義のアルバムと言えるのではないでしょうか?
2010年前後、〈Workshop〉がもろにそうですがディープ・ミニマルからの、セオ・パリッシュなどのローファイでラフなハウス・サウンドを昇華したある種のジャーマン・ディープ・ハウスの新たな展開、そうした流れの象徴的なアーティストのひとりとしてあげられるのではないでしょうか。そのサウンドは上記『Workshop 19』あたりを聴いていただければと思いますが、セオ・パリッシュの影響を感じさせるビートダウン・ハウスを、さらにドイツ流にミニマルにクリアに展開といった感覚のサウンドで注目を集めました。
さて時系列的にそのサウンドの流れを追うと、セカンド『Disclosure』はちょっと異質な作品で、ディスコグラフィーを後から見渡すと、どちらかと言えば Seltene Erden 名義や DJ Residue 名義のアブストラクトな電子音の冒険の前哨戦といった感じもします。前作にあたるサード『Chilazon Gaiden』は、そうした電子音の実験がストレンジな音感のハウス・グルーヴへと進んだ感覚で、ファースト『Workshop 19』が醸し出すムードとも、セカンドの電子音響的な実験的な世界観とも違ったシンプルなリズムの探求を目指した結果という感覚もします。どこかグルーヴだけを手がかりにストーリーやムードといった表現を排除したような、「鳴っている」ことの面白さを極めているようなそんな作品です。
こうしたキャリアのなかでリリースされた本作は『Chilazon Gaiden』で示されたクリアな質感とシンプルなリズムを表現の中心に備えた作品ではありますが、同時に初期にあったデトロイト・ディープ・ハウスの影響を後半に見せてもいるのが特徴ではないかと。アルバム冒頭、シンプルなフレーズとパーカッションが蛇行したグルーヴを淡々と作る “A1”、彼の真骨頂とも言えるディープ・ハウス・トラック “A2”。このあたりはリズムの冒険を中心に据えた楽曲と言えると思いますが、こうした楽曲でこれまでの作品になかった要素としてあげられそうなのは、ダビーとも表現できそうなサブベースの使い方(サブスク音源だったりあまり現代的でない指向性のスピーカーだとそれほど伝わらないので再生環境に注意が必要ですが)。ミキシングなのか機材なのかマスタリングなのか判断しかねますが、本作の下の方でブンブンと低音が鳴っているのが結構印象としては強いアルバムです。
リカルド・ヴィラロボス的なサイケデリアを発する “C1” やキックを排した “D2” などの楽曲にもやはりベースラインがよりサウンドの要として活躍しています。リズム、フレーズ、そしてスウィングする地鳴りのようなサブベース、この3つの要素が有機的にからんでグルーヴを作り出していく、そんな印象を受けます。“B1” や “B2” はベースラインの印象は薄いですが、初期ハーバートあたりを彷彿とさせるストレンジなファンクネスです。このあたりの要素は『Chilazon Gaiden』の先にある作品であることは間違いないでしょう。そしてアルバム後半はハイライトとも言える “C2” 以降、前作にはなかったストリングスが流麗にムードを作り出していて、このあたりは逆にファーストあたりで見せていたデトロイト・ディープ・ハウスの影響をひさびさに感じさせるサウンドになっています。アルバムのラスト “Provide Those Ends” は “C2” のダブ・ヴァージョン的な趣ももあります。
テクノ由来の電子音の実験性が醸し出すストレンジな感覚、淡々とどこまでも続く抑制的なディープ・ハウスのグルーヴ、このふたつの有機的な絡み合いがこの名義の魅力と言えるとは思いますが、本作では彼のキャリアをひとつ総括するように、その才覚が遺憾なく発揮されています。サブべースの援用はもちろん昨今の制作ソフトウェアや機材、モニタリング機材、PAを含めた再生・音響技術の変化といったテクニカルなところから、不断となったベース・ミュージックとハウス/テクノの関係性というモダンなシーンへの反応というアップデートを示すものとも言えるでしょう。ともかく、なんというかミニマルなジャーマン・ディープ・ハウスの真骨頂、そんな言葉が浮かぶアルバムです。アゲず、終わらずなグルーヴの感覚、そこから導き出されるヒプノティックないわゆる「ハメ」の感覚は、バシッとDJプレイでハマったときに「アレからのコレ」なのか「コレからのアレ」なのか、まぁともかくこうした楽曲の真価はそうした瞬間に訪れるものですよね。
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE