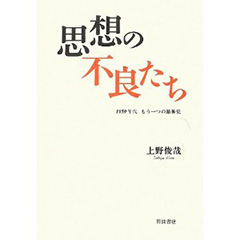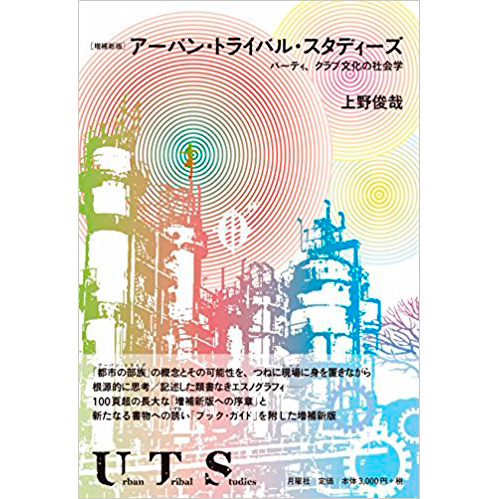MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 上野俊哉- 『思想の不良たち 1950年代、もう一つの精神史』
鶴見俊輔、花田清輝、きだみのる、安部公房の四人。戦中・戦後の混乱期、転形期のなかで培われた思想が「不良」とここでは捉えられている。その思想は決断主義によらず「転回と倒錯」というとらえどころの難しい精神性をもっていたし、また共同制作、つまり無名性を運動論として持っていたからヘゲモニーをとることはなかった。しかし、その不良性は途絶えたのではなく、現在まで命脈をつないできているのだ。上野俊哉の久しぶりのこの本では、その彼らの思想を丹念に掘り起こし、そして現在周りで起こっているさまざまなパーティーやデモとつなげて考えられている。
新日本文学という文学集団のなかで花田清輝の薫陶を受けた小沢信夫さんは、その半生を振り返った『小沢信夫さん、あなたはどうやって食ってきましたか』という本のなかで、文学の無名性ということについてこんなことを言っている。
「だから、鶴見(俊輔)さんはすごいな。長谷川四郎の文章は、無名の文章だと。自分の文章のなかに、墨子みたいな古典を平気で入れてくる。つまり、文章が共有なんだよ。そこを鶴見さんはちゃんと指摘するね。そういわれりゃ、そうだ。
いまどきの詩人というのはさ、詩のなかに誰かの一行を入れて、後ろに注をつけて、この言葉は誰それさんの詩集からっ、て......けっ。まったくちっぽけな。せまっこさ。おれは長谷川四郎派だ、と思いますけどね。」
そして花田清輝は『復興期の精神』の書き方についてこう述べている。
「文献や年代記を拒否し、虚偽以上の虚偽だけに私の視野を限るということが、冒頭において私の宣言した方法であった。この方法は、あくまでつらぬかれなければならない」
こうしたやり方は誰にとっても受け入れられることではないかもしれないが、そうでなくては受け取ることができない表現でもある。少なくともぼくにとってはそうだ。シュール・レアリズムがやはり戦争という非常事態を経て生まれたように、彼らのどこか過剰な表現も戦争を契機として生まれ、その後の世代、たとえば書いているうちに対象が憑依してしまい、「オレがコルトレーンだ」と本人になりきって評伝を書いた平岡正明さんなどに受け継がれ、そして現在までつながってきたのだと思う。
「気をつけなくてはならないが、カーニバルやパーティーの媒体となる「ハーメルンの笛」は「革命」や「運動」のためのプロパガンダの道具や拡声器ではない。笛や拍子にノッて、人が踊ること、我を忘れて陶酔することのなかに、システムから降りる、「世間」から離脱するヴァイブスとグルーヴがある。次の社会、未来の制度を準備するイデオロギーや主義、政策ではなく、拍子(ビート)と舞(ダンス)のなかに宿る精神、あるいは情動こそ、本当に権力が恐れる非暴力、暴力よりもねばり強い非暴力のコアなのではないか」
こうした認識は、現在その渦中にいる人たちには当然のことなのかもしれない。けれどもさらに本書では、サイケデリック、ニューエイジ、スピリチュアリズムまでをも含めて、それらを肯定的に対抗文化として捉えている。そうした視点は著者のこの十年の実践から導きだされたものなのだろうか。花田清輝のすべてを俯瞰し飲み込んでいく思想には実際めまいを覚えることがある。戦争さえもスペクタクルなのだと花田清輝が考えていたとこの本で読んだが、正直ぼくはいまだそこまで行き着かない。この十年ほど著者の文章をほとんど見なかったけれども、それならやはりその実践の方も読んでみたいと思う。
岩波書店というカタイ版元から出ているからわざわざいうけれど、最終章の「砂漠のカップル」という文章は少しでも多くのひとに読んでほしい。幾何学的でとらえどころのない砂粒の運動は、現在の大衆論としても読めるし、とくに「無名性」ということにかかわる美しい文章だ。今現在の運動論としても読めるし、それ以上に1948年に書かれた「砂漠について」という花田清輝の文章を読んだであろうたくさんの知らない人たちを想起することができる。たとえば先日読んだブレイディみかこさんの文章に出てきた算数教師のような、自分だけの表現をしながら生きる人たち、そのような知らない人たちのことを思い返すことのできる、パースペクティヴが広がる多層的な文章だ。
市原健太
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE