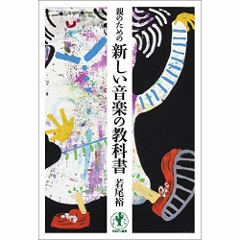MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 若尾裕- 『親のための新しい音楽の教科書』
小学3年生のときの担任の先生を、私たちが暴力パンダと渾名したのは、みんな大好きなパンダによく似た丸っこい顔のやさしそうな先生(男性)なのにすこぶる暴力的だったからだが、彼は音楽を偏愛し音楽の授業への熱の入れようは尋常でなく、全盛期の山下洋輔ばりに鍵盤をぐわんぐわん叩くものだから音楽室のぼろぼろのアップライトはいまにもばらばらになりそうである。合唱コンクールや学芸会なぞちかづこうものなら、国語や算数の授業そっちのけで練習にかかりきり。指導方法は「でかい声を出せ」の一点張りで血管が千切れるほど絶叫するか、喉から血ヘドを吐くか、トチった者が木琴のバチで側頭部を殴打されるか、いずれにせよ血を見なければおさまらない。ハーモニーはおろか男声女声おかまいなし、基本的にユニゾン、いやほとんどトーン・クラスター状態であり、私は後年グレン・ブランカの音楽になによりまず懐かしさを感じたのはこのときの体験の賜物ではないかと思うのだが、ともかく、その年の合唱コンクールの課題曲は“行きゅんにゃ加那節”という奄美では誰でも知っているシマ唄だった。ほんらいファルセットを多用し別れの哀切を歌う切々たるこの唄を私たちは教えられた通り絶叫した。叫ぶ詩人の会でもあれほど叫んだことはあるまい。結果は憶えていない。優越感も落胆もなくただ解放感だけがあった。私たちはそうそうに帰路についた。夏は終わったのだ。夏ではなかったかもしれないが。
私はながながとおもいで話をしたいのではない。『新しい音楽の教科書』と題したこの本の第一章「こども用の音楽」で、若尾裕は幼稚園/保育園では「なぜこどもたちにあんなにも大きな声で歌わせるのか、なぜ小さな声ではいけないのか」と疑問を投げかける。私はこの原稿をある神社の裏手のマンションの一室で書いているが、その神社には付属の幼稚園があり、まさにいまこの瞬間も園児たちが唱歌を怒鳴るのが聞こえる。これはこの神社が軍神を奉っているからではない。幼稚園や保育園はどこもかしもそうなのだ。若尾裕はそれを「おとなたちが考える『こどものあるべき姿』のひとつなのだ」という。理想像をつくりあげ全体をそこに漸近させる。もちろんすべての園児が理想像に完全に一致するわけはない。個別の分布があり、そこから平均値が生まれ、上方であれ下方であれ偏差はいずれにせよ少数派として捨象され、理想像はおもむろに平均値にすりかわる。あらゆる教育現場に横たわる問題を背景に若尾裕は音楽を語りはじめるが、それは音楽が身体に直接訴えかける形式だからだろう。幼稚園では歌を歌い、絵も描く、お遊戯もするが、文字はまだ教えない。彼らは芸術は身体にあらかじめ内在すると見なしているかのような教育方法をとる。ということは、教化する主体によっては身体を制度化できる。なかでも音楽は明治を期に伝統を切断し、人為的に近代西洋音楽にもとづいた教育法を導入したので、日本の音楽の現状を考えることはある体系の受容と定着の深度をはかるかっこうの題材である――だけでなく、私たちが信じて疑わない音楽上の価値観もこのわずか百年あまりの慣例にすぎない(かもしれない)と、視点をあげることをうながすのである。
たとえば演奏技術の巧拙、高尚な芸術音楽と俗謡、障害者と健常者の(ための)音楽。誰もが知る教則本『バイエル』はハ長調の練習曲ばかりで欠陥がある――というのをはずかしながら私は娘が通うピアノ教室の先生にいわれるまで考えもしなかった(練習とはそういうものだと思っていた)のですが――にもかかわらずなぜあれがあれだけ重宝されたのかといえば教える側の都合でしかない、と若尾裕は喝破する。ところがひとはそれをよそにあらゆることに日々馴化し「音楽は楽しいものだよ。なにせ、音を楽しむ、と書くのだからね」とまで宣うまでに単純化する。私は書き落としたが、本書の正しい書名は『親のための新しい音楽の教科書』である。「親のための」となっているがからずしも子どもがいるひとのために、ということではない。すっかり常識となった誤解を解くための教科書であり考え直すための端緒であり、固着した脇に置くためのヒントであるとともに、支配や従属によらず「親にとっての子ども」の他性を尊重する。あるいは上記の二項対立を「解決」――というのは音楽的に協和な状態を指す言葉でもある――するのではなく、世界の広がりと深さをはかるためのモノサシにするために、若尾裕はプラトンからアドルノ、レヴィ=ストロース、サイードらの思想、彼のいい方にならえば先達の「ナラティヴ」をふまえ、『奏でることの力』や『音楽療法を考える』をはじめとした彼の先験的な臨床音楽学で培った知見をそこに加え、徹底して相対的であるとともに対話的なナラティヴを提示する。それさえもポストモダン状況を一歩も出られない――というのがポストモダンであるのだから――なかでは陥穽に陥るおそれはなくもないとしても、また音楽を語ることそのものが作曲家~演奏家~聴衆の分業体制が確立した近代の産物であることからくる切断線を秘めるにしても、この教科書は多用に応用可能なまことにやわらかい思弁です。
文・松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE