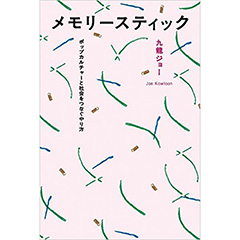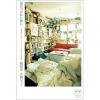MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Book Reviews > 九龍ジョー- 『メモリースティック ポップカルチャーと社会をつなぐやり方』
音楽、映画、演劇、お笑い、プロレス、落語、歌舞伎、女装……更新されていく日本のポップ・カルチャーのフロンティアをつぶさに追い、丹念にドキュメントする一冊。まだ名づけられていない事柄に深くコミットし、取材と執筆を通して現場をつくり、リスペクトと共感をもってそれらをつなげてきた、真性の編集者/ライター九龍ジョーによる初の単著。
社会は変態の夢を見るか矢野利裕
九龍ジョーの初単著『メモリースティック』は、「1章 音楽と映画のインディペンデント」「2章 非正規化する社会と身体」「3章 格闘する記憶をめぐって」という3章からなる。ライター・九龍ジョーの持ち味は、刺激的なカルチャーをいち早く見つけてきては、それを紹介することだと言える。だからだろう、『メモリースティック』も、ネットなどの反応を見ていると、知られざる刺激的なカルチャーを紹介した、という受け取られかたが多いように思える。もちろん、間違いではない。というか、その通りである。しかし、本書に圧縮されたファイルを僕なりに解凍すると、その印象は少し変わる。膨大な固有名が詰まった『メモリースティック』を貫いているのは、おそらく変態‐性なのだ。
2章の最後「鏡になってあげると大島薫は言った」は、AVの話題からはじまって、リアル男の娘・大島薫が紹介される。この「ノンホル/ノンオペの男性にしてAV女優」という変態‐性こそが、本書の核心だと思う。大島をまえにして、九龍は言う。「彼女がそうであるように、ぼくたちも自分の欲望のポテンシャルを低く見積もらないほうがいい」と。つまり、「変態であれ!」ということだ。いつのまにか成立している社会や秩序や規範のありかたに目を奪われず、変態であれ!――このメッセージに、強く共感する。大島薫が登場する記事の直前、「「女装」のポテンシャル」と題された座談会では、松井周(劇団サンプル)、鈴木みのり(ライター)、Koyuki Katie Hanano(モデル・女装男子)、井戸隆明(『オトコノコ時代』編集長)が、それぞれセクシュアル・アイデンティティをめぐって言葉を交わしている。印象的なのは、馴染みのない人からすれば、大雑把に括ってしまうかもしれない「女装」のありかたが、当事者たちにとっては、それぞれ非常に微細な差異を持っているということだ。考えてみれば、当然のことである。座談会ではそのような、それぞれ固有の性のありかたが披瀝されている。ドゥルーズ&ガタリを参照する九龍が、「人間の数だけ「n個の性」がある」(「トランスするサンプル」)と言うとおりだ。だとすれば、これはマイノリティ/マジョリティという数の水準を超えて、すべての人に投げかれられるべき問題である。わたしたちは、自らの性をどのくらい解放/抑圧しているのだろうか。いつのまにか成立している社会や秩序や規範のなかで、自らの変態‐性を見て見ぬふりしていないだろうか。
九龍は、そもそも舞台芸術にトランスジェンダーの物語が多いことを指摘し、「ジェンダーという社会的構築物とセクシャリティとの間にすでに「演じる」という要素が入っている」(「トランスするサンプル」)と言う。九龍からすれば、わたしたちは程度の差こそあれ、みな変態である、その変態‐性を一般社会に馴染ませながら生きている、ということになる。いつの間にか成立した普通を「演じる」ことで、社会を生きている。これはなにも、性に限ったことではない。わたしたちは、あらゆる領域において、固有の生と社会的な生の偏差を演劇的に埋めている。九龍の舞台への関心は、おそらくここから来るのだろう。チェルフィッチュ、五反田団、サンプル、あるいは、落語やお笑い、プロレスにいたるまで、九龍にとって舞台芸術とは、わたしたちが抱く演劇的な真実とでもいうべきものを、現出させてくれる空間なのかもしれない。変態とは、「アブノーマルabnormal」を意味すると同時に、「メタモルフォーゼmetamorphose」を意味する。社会的・秩序的・規範的な生から脱し、なにか別の存在に変身する、その瞬間に顕わになる変態‐性を九龍は見逃さないだろう。固有の生と社会的な生が重なるその瞬間を、リアルな身体とキャラクターの身体の「二重性」を抱えたミスティコのその跳躍を(「ロロと倉内太のポップな反重力」)、立川志らくによる「これからは師匠(立川談誌‐引用者注)は自分の身体に入ってきて落語を喋るんだ」と思うことにした、というその発言を(「江戸の風の羽ばたき、立川談誌の成り行き」)、九龍は見逃さない。
『メモリースティック』が、知られざる刺激的なカルチャーを紹介した、というのは、その通りである。とくに1章で紹介されている、前野健太、松江哲明、どついたるねん、大森靖子、韓国のインディ音楽など……。九龍は、いまだ知られざるミュージシャンやクリエイターが一般的な認知を得ていく過程をリアルタイムでドキュメントしていた。しかし、その営みを単なる紹介として捉えないほうがいい。それはまさに、固有の文化が社会に認知されていく――その変態の瞬間を保存したものなのだ。九龍の『メモリースティック』はさしずめ、名づけえぬ変態たちを「名前を付けて保存」する作業だということか。「ポップカルチャーと社会をつなぐやり方」という本書の副題は、その地点から見るべきだろう。九龍は、「ドラマ性をはぎ取られた真空の位相でこそ、「正しい」も「間違い」も「真面目」も「でたらめ」もすべてが可能になる」(「現実を夢見る言葉の位相」)と言うが、変態‐性を秘めるポップカルチャーこそ、社会自体の変態可能性をはらんでいる。『メモリースティック』においては、インディーシーンも労働問題もセクシュアリティの問題も、変態の夢を見ているのだ。
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE