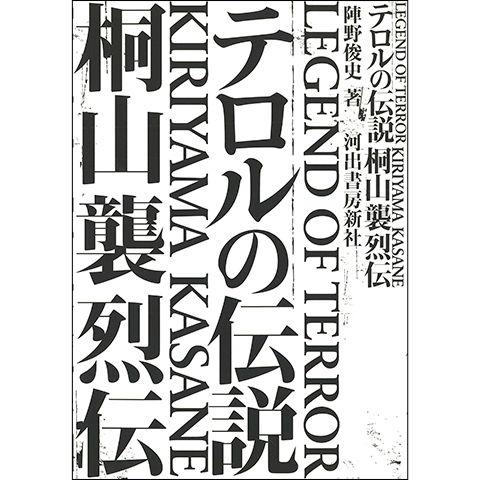MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > テロルの伝説──桐山襲烈伝- 陣野俊史
桐山襲とは一度出会っていた、もちろん本の上でのことだ。
私は学生時代、といってもカープがこの前リーグ優勝したときくらいだから四半世紀も前、時代区分でいうと90年代ころ、世の中のすべての雑誌を読んでいた――というのはいいすぎにしても、目につく雑誌に片っ端から目を通していた。囲碁、将棋はもとより鉄道、航空、釣り雑誌で陸海空を制覇し、農業の専門誌も、農法や農薬などわからないし必要ないが目をとおさずにいられない。むろんすべて立ち読みである。金のない学生が数百円とはいえ膨大な量の雑誌を買いこむわけにはいかない。地方都市だったので大宅壮一文庫はなかったが、あればおそらく住みこんでいただろう。とはいえ情報がほしいのではない。ことばや写真や図版が書物のかたちをとることの不思議さと、それにふれることでできる空間に、いま思えば魅了されていたのはレコードと変わらない。当時私は世界の広がりとはレコードと書物が生み出す空間の乗数だと思っていたのでページを捲る指先にも力が入ろうというものだ。あまりの力の入りように用紙がコート系だと指先を切ることもしばしば。流血さえいとわなかったのである。
音楽誌、ファッション誌、カルチャー誌、マンガ誌のたぐいはもちろん、文芸誌も例外ではなかった。五誌ばかり押さえればことたりるし、月初発売なので月があらたまった感じがするのも儀式めいていていい。この数ヶ月、本媒体にはご無沙汰だったのは、紙の世界の仕事がたてこんでいたからだが、そのあいだもたゆまず読んだ。読むのは習慣なのである。つらい仕事を終えて、床に就き読書灯の下ですごす2時間ばかりが日々の唯一の愉しみ。拙文は同衾した本たちの感想文である。夏休みあけの課題提出にまにあったかは心許ないが。
話が逸れた。くりかえすが、桐山襲の名前を目にするのははじめてではなかった。陣野俊史による桐山の評伝とも批評ともいえる『テロルの伝説 桐山襲烈伝』(河出書房新社)を手にしたときに情景がフラッシュバックした。棒きれのような絵が載った表紙、もしやあれではあるまいかと古書を詰めた段ボールを漁ると捨てずにとってあった。『文藝』1992年夏号、私はこの雑誌を買ったのは、毎月の少ない自由になる金から吟味に吟味をかさねたうえで購入する媒体を決めたなかのその月の一冊だったのである。巻頭は久間十義で「ヤポニカ・タペストリー」が四〇〇枚と表紙に謳っている。私はここでいうのもはずかしいが、久間十義を久生十蘭ととりちがえていた。久生十蘭の未発表原稿でも発見したのか、それはけったいなと思ったのだ。買ってから気づいた、吟味していたはずなのにまぬけである。とはいえ、買ったからには読まないのももったいない。久間氏の名誉のために書くが「ヤポニカ・タペストリー」はなかなかに興味深い小説だった。私は出口王仁三郎とはあさからぬ縁がある。それを述べはじめると本論にたどりつかないので稿をあらためるのが、その次に載っていたのが桐山襲の「未葬の時」だったのである。ただし表紙に載せた表題の上には【遺作】とある。
私は桐山襲の死をもって彼と巡り会った。
ここで若い読者のために、桐山襲はどのような作家だったか、陣野が下敷きにしたという講談社文芸文庫の年譜をもとに要約すると、桐山襲は1949年7月、東京は杉並区阿佐谷に生まれ、杉並第一小学校五年時に母を病気で亡くすも、日大付属第二中~高と歩むなかで、高校生になると仲間と同人誌を発行し小説を書いてもいる。早稲田大学第一文学哲学科に入ったのは1968年、「あの68年」と強調することがまたしても若い読者を遠ざけないかとのおそれは抱きつつも、言下に全共闘世代といってスルーできない思想の細分化と対立と混沌は72年の浅間山荘事件であらわになるが、政治の季節のただなかで桐山は解放派系の運動に加わりつつ、カントを読み大江健三郎を読み高橋和巳を読み、沖縄を旅した。まだ日本に帰る前の沖縄、やがて日本に帰ったのは正しかったのか悩むことになる沖縄――南の島へのこだわりが桐山に巣くっていたのはデビュー作「パルチザン伝説」であきらかになる。パルチザンとは銃をとって叫ぶ民衆によるレジスタンス運動を指すが、桐山がこの小説を文藝賞に投稿したのは勤め人の暮らしも板についた1982年、と知った私はこのような小説が80年代の世に生まれたことにめまいをおぼえた。テクノポップとニューウェイヴと消費礼讃の時代とのキャッチコピーをいただきがちな80年代に桐山の「政治」小説は世に出たのである。おない年の村上春樹は同年、「1973年のピンボール」で政治の季節の終わりを綴ることで専業作家として身を立て、年下のサヨクである島田雅彦が頭角をあらわしはじめていた。私たちはそこに、文学の営みの「遅さ」をみるべきか、それともことばの発酵にかかる時間の重さを読むだろうか。というよりそれは時代にあらがう表現がもたらす居心地のわるさなのだろうか。
桐山は「パルチザン伝説」を長い二通の手紙を中心に構成する、書簡体小説である。兄と弟のふたりがいて、1982年4月の日づけのある「第一の手紙」とその二月後の「第二の手紙」ともに弟がしたためている。彼らはともにある政治的な事件が原因で、兄は決意した啞者に、弟は爆発で身体の一部を欠損した不具者になった。弟が彼らをそうさせた顛末を綴るなかに、父の来歴が出来し、ふたつの爆破事件がかさなりあう。「パルチザン伝説」はきわめて政治的な現実の出来事を意識的な方法で構築した野心的な作品だったが、ことはそう簡単には運ばない。文藝賞では選にもれた。選考委員は江藤淳、野間宏、島尾敏雄、小島信夫の四者だったが、彼らの選評をもとに、桐山のデビュー作は世に問う前に小説につけた評価のみがひとり歩きしたのである。いわく、「恐るべき題材に強烈に迫っている」――野間宏の惹句めいた文言が小島信夫の選評の「実名である天皇」とあいまってイメージは肥大化し、無名作家の手になる読めない小説への読者の想像をたくましくさせた。賞には落ちたが編集は桐山を気にかけていた。翌年桐山は第二作「風のクロニクル」を「文藝」の編集者に手渡すも、一作目と二作目どちらでデビューしたいかと問われ、思い入れの深い前者を希望する。新人賞への応募作をときをおいて掲載するのは異例だが、「パルチザン伝説」は世に出たのもつかのま、「週刊新潮」の「おっかなビックリ落選させた『天皇暗殺』を扱った小説の『発表』」とのタイトルの「風流夢譚」事件へ世相を(ミス)リードしようとする記事により、版元は右翼の街宣を受けた。ゴシップ・メディアの常套句であるスキャンダリズムとポピュリズムにより桐山襲が終生格闘しつづけることになる桐山のパブリック・イメージはことのきすでにできあがっていたが、読まないひとたちの無責任な関心がその肥大化に拍車をかけたとはいえまいか。あるいは無関心か。なにせ、ときは80年代なのである。と書きながら私は仮にそれが2010年代であっても、作品をめぐる状況は変わらなかったのではないかと思いもする。表面的には活発な議論がおこなわれているようでありながら、その一歩外には深い無関心とその陰画である憎悪が渦巻いている――
この本はそのような状況をときほぐそうとする。陣野俊史は桐山襲の人生よりも小説を問題にしている。作品が生のすべてを物語ることの確信があるから、小説の梗概をていねいに述べ、ふみこんだ解題をおこなっている(なので未読の方でもずんずん読み進められる)。「パルチザン伝説」にはじまり「スターバト・マーテル」「風のクロニクル」「亜熱帯の涙」「都市叙景断章」から冒頭の「未葬の時」にいたる十数作の小説と評論とインタヴューを丹念に追いながら、連合赤軍、東アジア反日武装戦線、ひめゆりの塔事件、永山則夫の文藝家協会入会問題といった題材の歴史的背景にあたり、そこに潜む意外なほど現在的な問題を指摘することで、陣野は桐山を70年代に、全共闘世代に、過去に置き去りにしない。古川日出男や目取真俊、佐藤泰志といった作家たちとの系譜をつなぐ視点は現代文学のすぐれた読み手としての陣野の真骨頂でもあるだろう。その読みはまた、桐山襲という作家の政治性のウラの抒情をもうかびあがらせる。
本文に引用した発言で桐山は政治と文学を明確に線引きした旨述べている。政治は多数の者がかかわる現実の運動であり作品をつくることとはまったく異なる行為であり、小説は現実を変えない。と同時に、桐山は文学においては、詩的言語と物語形式に引き裂かれつづけきた。というよりあえてどちらか一方を選ばなかった。桐山はインタヴューでそのあり方をポール・ヴァレリーがアストゥアリスのあの『グアテマラ伝説集』を指していった「物語=詩=夢」になぞらえている。散文性と詩情と現実を異化する虚構性の全部を抜け目なく高度に折衷するのは、私なんかは欲張りじゃありませんかといいたくなるが、桐山襲は意に介さない。書簡体をはじめ、作中作、人称の変化、時制の錯綜、叙述形式の混在、政治問題の積極的な援用も、いま考えるとリアルとフィクションの接着面を探るための実験だったともいえなくはない。そもそも、小島信夫が桐山の小説に反応したのも、「パルチザン伝説」を文藝賞に応募した年に、とりあえずの完成をみた『別れる理由』の、とくに第三部のあやうさ――ということばを私はいい意味で使っている――を念頭に置いた老婆心でなかったとはいいきれない。ところが桐山の意識的な方法は等閑視されないまでも政治性のウラに隠れてしまった。しかもそれは桐山の資質――というのはまことにヤッカイ――である抒情に覆われている。そうして「物語=詩=夢」は桐山のなかで、等式のように水平に整合的に展開していくというより作品ごとに配合を変え、生理という名の身体性にゆらぎながら積み重なっている。私は桐山襲の筆名の読みが「かさね」であることに、まるで推理小説のトリックがもっとも目につきやすい場所に最初から置かれていたような気さえするのだが、この本がなければそのようなことはおよびもつかなかった。
島に本書をもって帰ってよかった。ティダがカンカンのときはまいくのはフリムンべえよ、という制止をふりきって私はこの本を浜ぎわのアダンの木の下で読んでいる。アーマの忠告どおり浜にはだれもいない。熟れたアダンの甘い匂いが上からふりかかる。月のない初夏の夜はこの浜一帯がアマンで覆い尽くされたことだろう。生家にほど近いこの浜は沖縄が復帰した年にいまの天皇が皇太子だったころ訪れた縁でプリンス・ビーチと呼ばれている。当時はこのあたりがこの国の南端だった。皇太子が沖縄をはじめて訪れたのはその3年後の海洋博である。そのときおこったひめゆりの塔事件は、先の天皇の生前退位報道にからむ特別報道番組でもほんの数秒だがテレビに映っていた。桐山はこの事件を「聖なる夜 聖なる穴」にあつかっている。それだけでなく、デビュー作に沖縄をとりあげて以降、「ほぼすべての小説に「南島」が登場する桐山作品の底流には(中略)「国家」にも「民族」にも回収されない、「不定の位置」を保っている」(p203)沖縄への傾斜があった。つまり異化作用であり、それを俯瞰するだけならポスト・コロニアリズムだが、桐山は南からのまなざしに寄り添うことに腐心しながら小説では一貫して形式を呼び寄せるきっかけとして南島を夢想しつづけた。中島敦の希求したものとも土方久功の野趣ともちがう桐山襲の南へのまなざしは陣野俊史のいう、南米はおろか世界にも類例のすくない「海洋型マジック・リアリズム」に実を結んだからこそ、いまなお不定の小説として歴史上の位置はさだまらない。むろん問題は南島だけではない。桐山襲の射程は表現の自由にせよ集団のとる行動原理にせよ、ある時代に特有のものではない。おそらくそこには80年代というソリの合わない時代のなかでくりかえし70年代を考える相克が働いている。いまが最高だと転がっていく人間は無意識にせよそのようなものをうちかかえていやしまいか。
桐山が没した90年代初頭、世の中はデタッチメントの波にのまれていた。キャンバスにタテカンはのこっていたが、バリストは儀式でしかなかった。大教室で熱心にノートをとる、ちょっとかわいい子におちかづきになろうとノートを借りたら、トロ字混じりで遠い目になってしまうようなこともなくなっていった。女の子は授業で見かけなくなった。いやちがった、私のほうが授業に出なくなったのだった。あの娘はどうしただろう――というような、喪失を噛みしめるうちに口のなかに甘さが広がるようなところも桐山の作品にはなくはない。他者、とくに女性の描き方にはある種の典型から抜け切れてもいない。何人かの批評家はそれを指摘し、陣野俊史も「物語=詩=夢」の等式からその限界をみとめているようにも読める。
私は遺作「未葬の時」を「文藝」で読んだとき、追悼文を寄せた笹山久三や竹田青嗣がいうほどの政治性は感じられず、図書館で『都市叙景断章』を手にとったはずだが、残念ながらほとんど憶えていない。読みさしで終わってしまった理由に陣野俊史の解題を読んで思いあたった。アイラーのくだりである。私はアルバート・アイラーがフリージャズが破壊一辺倒で聴かれるのに抵抗があった。なんとなれば、アイラーの猥雑さも陽気さも太さも細さも置き去りになってしまう。もちろんそれは小説の設定のひとつにすぎない。私は若かったといえばそれまでだが、『都市叙景断章』の基調である「この都市に私の記憶はない」という視点を深く考えるまでにいたらなかった。若松孝二が永山則夫の足跡をたどった風景論としての映画『略称・連続射殺魔』(1975年)をはじめて観たのはもうすこしあとだ。数年経ち、阪神大震災と地下鉄サリン事件の年にテロリストはパラソルをさしはじめた。私はチョコレートじゃあるまいしと毒づいたきり、その手のものを遠ざけ、永遠に新作を発表することのなくなった桐山襲を思い出すこともすくなくなった。私はもったいなかった。詩と物語形式のつばぜりあいがデビュー時の抒情から後年のドライな感性へ移行していく課程も、「パルチザン伝説」騒動の直後、主人公が南の島へ放逐したと宣言する「亡命地にて」を書く傍ら、東京で役所勤めを淡々とこなしていたという桐山のユーモアさえ感じさせる実践(テロル)もみすごしていた。そもそも、桐山の小説における政治とは、私は彼のことばをくりかえすが、現実をさししめさないことでその背後の力線を暴くものなのではないか。
私たちはおそらくたいがいのことを誤解し誤解したまま生きるところにこのような労作が書かれる理由がある。本書は巻末に未刊行の短編「プレセンテ」も所収している。
準備は整った。この本で桐山襲とはじめて出会うあなたはラッキーである。(了)
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE