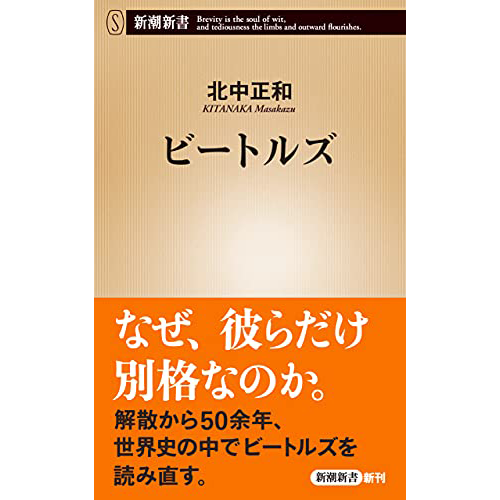MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 北中正和- ビートルズ
音楽が好きなようにぼくはそれにまつわる音楽本も好きだ。それなりにたくさん読んでいる自負もある。ところが、考えてみればビートルズに関してはほんの2~3冊の関連書を読んでいるくらいで、評伝の類は一冊も読んだことがない。
そんなぼくもご多分に漏れずビートルズが嫌いであるはずがなく、世代は違うが影響されている。自慢じゃないがレコードだって所有しているし、まだdiscogs以前の安かった時代には英盤(mono盤)まで集めたりとか、こう見えてもそこそこマニアックな聴き方もしているのだ。
ビートルズから引き出せる真理のひとつは、いい子が悪い子になった音楽ほど多くの人を惹きつけるものはないということだ。作家のハニフ・クレイシが言うように(※)、いい子が悪い子になってたくさんの人を一緒に連れていってしまった。デビュー前のジョンは充分に荒々しいだろうという声もあろうが、彼らは逆境をバネに音楽をやっていたわけではないし、基本的にはアートや音楽や楽器が好きな金持ちでも貧乏でもない子たちで、あの楽しげな“ラヴ・ミー・ドゥ”や『ヤァ!ヤァ!ヤァ!』なんかのビートルズはどう考えてもいい子たちに見える。それがのちに派手派手な衣装と丸メガネにひげ面で、“ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー”や“ア・デイ・イン・ザ・ライフ”、“シーズ・リーヴィング・ホーム”さもなければ“アイム・ソー・タイヤード”のような曲をやるようになるのだ。
もっとも日本ではオルダス・ハクスリーなんかといっしょにいるビートルズ(悪い子)よりも、無害で綺麗なラヴソングを歌っているビートルズ(いい子)のほうが表向きには語られているし、好まれてもいる。ただ、いい子の面があるがゆえにファン層はとにかく広い。そのお陰でぼくはビートルズの評伝を読まずして、いろんな人からいろんな話を聞きながら情報を蓄積していたのだった。だいたいビートルズぐらいになると、素人の話においてさえもあらゆる水準で分析され、ヘタしたら曲の発展に関する綿密な分析だって語られていたりする。個人的な詩情や感傷に重ねた言葉にいたっては無限大だろう。
ベテランの音楽評論家であり、近年はグローバル・ミュージックの研究者としても名高い北村正和氏による新著『ビートルズ』はこんな言葉ではじまっている。「ビートルズほど多くの本が出版され語られてきた音楽家は他にいないでしょう」。ベートーヴェンですら数ではビートルズの本には及ばないと。で、「それなのにビートルズについての本を書いてしまいました」
あまたあるビートルズ本のことをわかっていながら、では本書『ビートルズ』はビートルズをどのように書くというのだろう。ぼくの興味はまずそこだった。新書の音楽本というのは、ファンならだいたい知っている事実を手際よくまとめた安易なものが多い。入門編ということなのだろうが、冒険心の欠片もないつまらないものが目についてしまう。ぼくは寝際に、パジャマを着て布団に入って本書を読みはじめたわけだが、1章を読み終えたときには2章に進み、学ぶことの多さとその面白さにすっかり眠気も失せてしまった。
話は13世紀、日本では鎌倉時代、ブリテン島のマージー川のほとりにリヴァプールが建設されたところからはじまる。当初は寒村のひとつにすぎなかったリヴァプールは、18世紀の植民地主義の時代(大英帝国のはじまり)の大規模な貿易によっていっきに栄える。港町には奴隷としてのアフリカ人が輸入され(イギリス籍の奴隷貿易の8割がリヴァプール経由だったという)、町にはイギリスで最初の黒人居住地区ができる。
同時に、イングランドはアイルランドを支配し、安価な労働力としてのアイルランド人もリヴァプールへとやって来る。本書はこうして、世界史の遠近法を使ってビートルズ──本人たちは意識していなかったろうが、奴隷として連れてこられたアフリカ人の音楽に憧れるアイルランドに起源を持つ若者たちによるバンド──の輪郭を描きはじめる。
また、アイルランドに起源を持つということが、では文化的に、そして音楽的にどういうことなのかということを著者は歴史的な事実だけを揃えて説明する。なんと19世紀のリヴァプールは、ダブリンに次ぐ第二の(アイルランドの)首都とまで呼ばれていたそうだ。町の人口の20%がアイルランド人だったという。そして著者は、ビートルズにおけるアイルランド・ルーツと、ビートルズのじつは“ラヴ・ミー・ドゥ”より以前に録音し発売していた曲──スコットランド民謡の“マイ・ボニー”――におけるレイ・チャールズとの繋がりや、その歌詞に潜んでいる(イギリス史における民衆=スコットランド人/アイルランド人の蜂起にまつわる)政治性を解き明かす。ビートルズにふたりの天才がいたことはたしかなのだろう。が、ビートルズがビートルズになった背景には、それら才能の出し方を決定させたさまざまな世界史的要因が絡み合っているのだ。
ダブリン生まれで渡米し、歌手それもミンストレル・ショウの歌手だったという(仮説を持つ)ジョンの父方の祖父、ジョンの母ジュリアンが父から教わったバンジョーを弾いてジョンに歌った歌、19世紀に実在したサーカス団「ミスター・カイト」──、こうしたビートルズ前史の興味深いエピソードの数々もさることながら、本書の最大の魅力は、ロックンロール以前における大衆音楽史という大河とその継承に関する断片を描いているところだ。
たとえば、ビートルズのルーツのひとつにスキッフルがあるのは有名な話だが、ではそのスキッフルとはどんな発展のもとで20世紀初頭のアメリカ南部からイングランドへと伝わり、何者によってそれがイギリス化されたのか。あるいは、アメリカ南部のストリングス・バンドからの影響がビートルズのどの曲において具体的に表出しているのか、そんなところまで著者は追跡する。曲のなかに引用されたラテンやカリプソ、もちろん黒人音楽との関係も詳細に記されている。
おそらく本書が他のビートルズ本と決定的に違うのは──他を読んでもいないくせにこんなことは言えたモノではないのだが──、著者ならではのグローバル・ミュージック的なアプローチによって、21世紀の現在からビートルズを捉え直している点にある。その現在とはブラック・ライヴズ・マター以降の現在であり、インターネット普及後の現在でもある。インターネットによって古いものは古くなくなり、若いロック・ファンは同世代の新譜よりも90年代のオアシスに夢中になる。悪酔いしそうなほどすべてがフラットに広がる“イエスタデイ”を喪失した現在。時間の感覚も歴史感覚も20世紀とは何か違っている。
本書『ビートルズ』が試みている「世界史のなかのビートルズ」という視点は、時代(60年代)からも場所(リヴァプール)からも完璧に切り離されてしまっているビートルズをもういちど汗だくのキャバーン・クラブのステージに上げ、労働者で賑わう港町を徘徊してもらうばかりか、それ以前からあった、彼らが生まれ育った環境から聞こえる音楽、つまり大衆音楽の大いなるうねりのような、いわばその大河へと案内する。その大河とは、昼も夜もない眩しい現在という光に隠されて、もはやあまり語られることもないかもしれない大切な過去のことであろう。
まあ、こんなことを書きながらも、自分が若い頃は、ビートルズに関してはわずかな情報だけで充分ではあった。たとえば、名のある大学に通ったわけでも特別な音楽教育を受けているわけでもないのに関わらず、彼ら4人があそこまでの音楽作品を作ったということ。これだけでも10代のぼくにはインパクトがあった。そこに輪をかけて、“ストロベリー・フィールズ”のようなとんでもない曲がLSD体験の影響から生まれたと知った日には、スティーヴ・ジョブスでなくてもドラッグ・カルチャーに興味を覚えるのが若さというヤツだ。なにしろビートルズとは、自分たちがドラッグをやったことを恥じることなく堂々と打ち明けた最初のポップスターでもあったわけだし、ポップスターであることの居心地の悪さ、胡散臭さを自ら露わにした最初のポップスターでもあったのだ。
こうした若者文化の革新力において、しかしそれでもまだ充分ではなかったということは、後のパンク/ポスト・パンクないしはライオット・ガールズなどが証明している。が、もちろんビートルズとはポップ・カルチャーの文化的革新力における初期段階のもっとも巨大な推進力だったし、なによりもその音楽は群を抜いて豊かで、ゆえに愛され続けている。本書は、そんなバンドの主に音楽性における影響源に絞った解説で、彼らの曲を聴いてきた大人のためのビートルズの本だ。ビートルズを入口とし、あらためて大衆音楽の素晴らしい奥深さを教えてもらった次第である。
(※)ハニフ・クレイシ/柴田元幸訳「エイト・アームズ・トゥ・ホールド・ユー」(『イギリス新先鋭作家短篇選』収録)本書とは趣を異にするが、サッチャー時代に書かれたこの短篇も、いま我々がいる境遇=新自由主義時代を生きている立場から60年代とビートルズを回顧している点においてじつに興味深い。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE