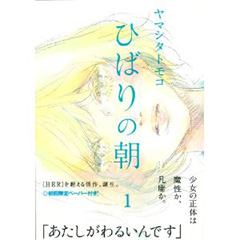MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Comic Reviews > ヤマシタトモコ- 『ひばりの朝』
押井守や北野武が描くアウトサイダーはたいていの場合、組織に属している。いわゆる「お荷物」とか「不良社員」といったやつである。泥棒やドラッグ・ディーラーを主役にして反社会的行為を色とりどりに描く洋画や香港映画に較べて、そのような「アウトサイダー」には当然のことながら「悪いこと」には一定のラインがあり、最終的に主役が手にするものは「美学」ばかりである。実を取る気配すらないし、間違っても生活感などは漂わせない。
不出来もいいところだった林海象監督『キャッツ・アイ』は論外として、最近だと内田けんじ監督『鍵泥棒のメソッド』や伊藤匡史監督『カラスの親指』でようやく日本の映画でも組織に属していない悪党たちがコン・ゲームを繰り広げはじめたと思ったら(以下、ネタばれ)「どこにも悪人はいなかった」という価値観に終始し、ストーリーの妙もそのような結論から演繹されるものばかりだった。バカバカしい。たかがエンターテイメントだけに、事態は余計に深刻な気がしてくる。犬童一心監督『のぼうの城』でも金子文紀監督『大奥~永遠~』でも権力者の内面に同調させる映画作りは得意なのに、持たざるものからの視点はタブーなのかと思ったり。
「組織に属するアウトサイダー」は、しかし、新自由主義があっさりと過去のものにしてしまった面もなくはない。 原田眞人監督『金融腐食列島・呪縛』や本広克行監督『踊る大捜査線』以降、「はみ出し者」のレッテルはどちらかというと組織の周縁ではなく、組織を内部から改革しようとする者に貼られるようになり、以後、ストーリー的には「敵は頭の上」という図式がデフォルトと化してしまった感もある。佐藤嗣麻子監督『アンフェア』といい、堤幸彦監督『スペック』といい、警察上層部が悪くない例を探し出す方が最近は難しいし、改革=正義を行うという意識ととらえれば、このことは『沈黙の艦隊』や『デス・ノート』から連綿と続いてきた感覚であり、ゼロ年代よりもさらに強化されていると言える(クエンティン・タランティーノ監督『レザボア・ドッグス』は無意味な殺し合いを描いたものだったのに対し、『ジャンゴ』では人を殺す時に「正義」が持ち出されるという驚くべき変化があった)。
こうした変化は押井モデルや北野モデルのアウトサイダーを組織内には居ずらくさせ、自主退社を迫られるものにしてきた。『鍵泥棒のメソッド』や『カラスの親指』だけでなく、吉田大八監督『クヒオ大佐』や、国家単位で考えた時には木村祐一監督『ニセ札』が美学の路頭に迷ったアウトサイダーたちを暫定的に詐欺師ものにトランスフォームさせたとも考えられるし、それはそのまま正社員が非正規(=ノンキャリ)にずり落ち、ついにはオレオレ詐欺に手を染めるしか生き延びる方法がなかった時代の写し絵とも見えなくはない(『クヒオ大佐』にはアレックス・コックスばりの政治的センスがあり、『ニセ札』には民衆側の視点というものがあった)。
さらには「ソーシャル」というキーワードが無条件で是とされ、「自由」に振舞うことが迷惑行為と同義語のようになってくると、「アウトサイダー」は単なる自己愛パーソナリティ障害か時代の変化に気づいていない人にしか見えなくなってくる。松本人志監督『大日本人』は戦闘少女に救える地球はあっても、旧型の男性ヒーローには救ってもらいたい人もいないというカリカチュアとしては有効に思えたし、同時に押井守や北野武の美学が笑われているようなセンスもあった。このような時期に押見修造『悪の華』は意外なほど反社会的行為をストレートに描き、しかも、「受けまくった」。ここには押井モデルのような屈折もなく、同時多発テロ以降、題材にしにくかったテロリズムを心情的に理解させながら話を進めていくことにも成功し、『殺し屋1』のように動機は捏造だったというようなトリックもない。それこそイスラムもないしw、強いていえば思春期原理主義というようなものかもしれないけれど、これに中2病のバイブルというような表現で時代性にフタをしてしまうと、見失しなわれてしまうことも出てくるはずであう。社会が常に変化しているならば、「反社会」も一定ではないはずだし、作者が参考にしたという『太陽を盗んだ男』だけが繰り返し上映されていれば、ほかはいらないということになってしまうし。
とはいえ、『悪の華』には「反社会」を内面化する決定的なプロセスがない。最も肝心な部分は主人公の外側からやってくる。教室で誰とも口を利かない女子生徒がいわば「反社会」の源泉のように描かれ、主人公はそれに染まるだけである。要するに少年マンガにありがちな「女の子は天使」とか、戦闘美少女と同じく、なぜか絶対なものとして描かれるものが、とくにこれといって位置関係を変えることなく男子生徒に影響を及ぼしているだけで、その女性徒が反社会的なパーソナリティになった理由はまったく明らかにされていない(少なくとも第1部では)。これではレールを踏み出したものがひとりいれば、後はつられて踏み外してもオッケーみたいな感覚に思えてくるし、逆にいえば、ひとりも踏み外す者がいなければ誰も踏み外さないということにはならないだろうか。最初のひとりはどうして反社会へと振り切れたのか。それが描かれていなければ、「反社会」を規定できるのはどの部分なのか、あまりにもわかりづらい。
ヤマシタトモコがいつもとは作風を変えた『ひばりの朝』が、そして、そのアンサーになっていると思えた。同作は3人の女性がそれぞれに社会と距離を感じていくプロセスが克明に描かれ、その気持ちが何度も上塗りされていくという残酷な作品である(全2巻)。彼女たちにつられて、同じように距離を表現する男性はひとりも出てこない(=だから、『悪の華』のようなテロリストは育たない)。男性たちはむしろ、彼女たちに距離を感じさせる原因でしかなく、ある種の男性たちに対する作者の怒りはみしみしと伝わってくる。彼女がここで描いている女性たちの何人かは、キャラクターをそのままにして男性化させれば吉田秋生の描いたアッシュやヒースと、そうは変わらないものになるだろう(……そう、ヤマシタトモコには、近い将来、吉田秋生の後継といえるような作品を生み出すのではないかとドキドキさせてくれるものがある)。『ひばりの朝』が、そして、とんでもないのは、『悪の華』ではひとりだった反社会的な女性のパターンが3倍になっているだけでなく、それらがさらに憎悪やネグレクトとして絡み合い、女性同士が必ずしも連帯しないという構図にもなっていることだろう。「反社会」性は、そして、なんらかの行動として実行されるものではなく、孤独へと跳ね返ってくるだけで、3種3様の諦めや逃避が描かれる。そして、周辺にいる登場人物たちは反社会に染まるどころか、近づくことさえできないものになっていく。
「息をとめていたので平気でした」
「人に興味を持たなければ 傷つかず 良心も痛まない」。
こうなってくると、もはや「アウトサイダー」という立場が成立していたことさえ奇妙なことに思えてくる。三池崇史監督『悪の経典』のように、一切の理由も正義も省かれている方が納得はできてしまうし、じとーッと『ひばりの朝』を読んでいると、一方では、きっと何も変わっていなかったのだろうと思わせるものがあり、それを普遍性と呼ぶならば、そのように呼べること自体が諦念と結びついているとも考えられる。吉田秋生でいえば『吉祥天女』のようでいて、どれだけ映画化されても悲惨な結果しか生まない(のに、懲りずに映画化される)『桜の園』に近い作品ではないだろうか。「社会」という言葉をもっと分解して考えなければ、ここではこれ以上は先に進めない。
安直に比較してしまったけれど、『悪の華』と『ひばりの朝』は主題も違うし、読者も効果も何も重ならないに違いない。強いていえば、『ひばりの朝』で克明に描かれているようなプロセスが省略されているにもかかわらず、『悪の華』がこれだけの読者を得たということは、理由もなく、反社会的な行動に駆り立てられている人が少なからずいるということにはならないだろうか。それは、もしかすると新自由主義が生み出したアウトサイダーの変貌がタイムリミットを迎えているのかもしれないし、小泉政権以降、組織に組み込まれなかった人たちが増えすぎて、情緒の受け皿が必要になっているということなのだろう。
(参考)
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE