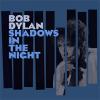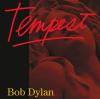MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Old & New > Bob Dylan and the Band- The Basement Tapes Complete: The…
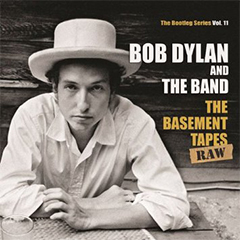
歌にしかできないことがある。東里夫『アメリカは歌う』(作品社)
エレキング的に……というか、僕個人の音楽メディアでの仕事経歴という点でも、2014年の大きな出来事のひとつは、萩原健太『ボブ・ディランは何を歌ってきたのか』を出版したことだった。多くの人から「どうしてエレキングで?」というような質問をぶつけられた。「どうしてエレキングで?」……この疑問には何通りもの背景があるのだが、僕が自覚していることのひとつを言えば、ボブ・ディランは、ビートルズが『サージェント・ペパーズ~』を出した1967年には、もはやそっち側にはいなかったということだ。僕個人は、どう考えても『サージェント・ペパーズ~』の側をたっぷりと過ごしてきている。キまっている人間が偉いと思うほどアホではなかったが、サイケデリックというコンセプトをほとんど無抵抗に、ほとんど無反省に、よろしきものとして受け入れてきた人間のひとりである。
そういう観点で言えば、ボブ・ディランが1967年にウッドストックのピンク色の家の地下室で、のちにザ・バンドと名乗るバンドと一緒に試みたアーシーなセッションの記録は、自分が長いあいだ遠ざけていたものとも言えよう。ちなみに、僕は今日、品川でフラング・ロータスのライヴを見てきたばかりなのだ。実にサイケデリックで、目が痛くなるほど派手なライティングのショーだった。そして、週末の電車のなかでくたくたに疲れながら家に着いて、その深夜に『ザ・ベースメント・テープス』を聴きながら、いまこうして文字を打っている。翌日大切なサッカーの試合があるので、緊張して眠れないというのもある。心の底から“アイ・シャル・ビー・リリースト”と言いたい心境だ。
最初の公式の『ザ・ベースメント・テープス』は、海賊盤が出回った後、1975年にリリースされていている。Discogsでも1975年作となっているが、さすが萩原健太の『ボブ・ディランは何を歌ってきたのか』では、ちゃんと『ブロンド・オン・ブロンド』の次の、1967年の作品に位置づけられている。『ザ・ベースメント・テープス』は、「誰もがストーンすべきである」と彼が歌った翌年の録音物なのだ。
ボブ・ディランは、サイケデリックで華やかな、そして効果音や電子音の時代に、アメリカの古い音楽(ルーツ・ミュージック)──ブルース、カントリー、フォーク、マウンテン・ミュージック等々──に向かった。シタールもなければミュージック・コンクレートもない。ブレイディみかこは、最新刊の『ザ・レフト』において、「誰もが度肝を抜かれるほど先鋭的なものを創造する鍵は、誰もが度外視している古臭いものの中に隠れていたりする。というのは、例えば、音楽の世界では常識だ」と書いているが、本当にその通りだ。ピカピカのニューウェイヴ時代にちんぴらモッズまる出しで登場したストーン・ローゼズ、プログレッシヴ・ロックの時代に50年代のロックンロールを引用したセックス・ピストルズ等々……、『ザ・ベースメント・テープス』が1967年に公式リリースされたわけではないが、これが「誰もが度外視している古臭いもの」であることに変わりはない。
ピッチフォークによる坂本慎太郎『ナマで踊ろう』のレヴューの出だしには、「日本のミュージシャンには、ブルースやフォークへの忠誠心がないという利点がある」というようなことが表向きな褒め言葉(?)として書かれている。たしかにアメリカにとってのブルース、カントリー、フォーク、マウンテン・ミュージックには、日本人が「いいなー、この音楽」という以上の、なかばオブセッシヴなまでの、歴史的な深い意味があるのだろうけれど、しかし現実を言えば、アメリカ人だからといってみんがみんなそれら古いアメリカを知っているわけではないし、イギリス人でも日本人でもアメリカーナに強い思いを抱いている人はたくさんいる。
むしろそれは忘れられたアメリカだ。たとえば歌のいくつかは、まだアメリカが(今日のようなグローバリゼーションの象徴ではなく)泥んこだった時代の、身体をはって危険な仕事を成し遂げてきた(ある意味では報われなかった)肉体労働者への敬慕や愛惜から来ている。ブルースやカントリーの歌詞に「トレイン」や「レイルロード」がよく出てくるのも、流浪の人びとの故郷への思いもさることながら、それらの歌がアメリカにとって鉄道がもっとも重要だった時代──19世紀から20世紀初頭──に生まれているからだ。そして歌は、人々によって伝承されている。「本や学問ではなし得なかった『ある思い』を伝える手段」(前掲同)として。
たしかに「歌にしかできないこと」がある。忌野清志郎は、『日本の人』という題名のアルバムで“500マイル”の日本語カヴァーを歌った。東京から500マイル離れた日本の地方と言えば、北に行けば札幌、西に行けば広島あたりで、その旅路に日本人としての何か歴史的な「思い」があるわけではないけれど、その歌は『ある思い』を確実に伝えている。1967年のボブ・ディランが“900マイル”(“500マイル”と同根のフォークソング)に託した「思い」とは別のものだったとしても、それはあるのだ。
先日リリースされた『ザ・ベースメント・テープス・ロウ:ブートレッグ・シリーズ第11集』は、『ザ・ベースメント・テープス』のコンプリートだ。完全盤『デラックス・エディション』には、なんとCD6枚組で138曲(ヴァージョン)が収録されている。新たに発掘されたテープもデジタル技術を使って修復されると、曲順は時系列順に並べられ、1967年の歴史的セッションは見事復元されるにいたった。38曲に厳選した2枚組『スタンダード・エディション』も同時リリースされている。僕のようなリスナーはこちらで充分満足できる。
サイケデリックの仰々しさから離れることで時代の先をいった『ザ・ベースメント・テープス』のリラックスした演奏/録音は、音楽批評の世界ではもっとも素晴らしいアメリカの音楽だとか、人によってはローファイ・カントリー/オルタナ・カントリーの先駆だとか評されている。先見の明だったとも言えるこのセッションが、ポール・マッカートニーやジョージ・ハリソンらを田舎に向かわせ、ロックにひとつの道筋を与えたのだろうけれど、まあ、このあたりの影響は研究者のみなさんに委ねるとして、なにはともあれ『ザ・ベースメント・テープス』が熱心なディラン狂だけのものにするにはもったいないほど、ラフでありながら超越的で、涙腺がゆるむほど美しい作品集であることは間違いない。138曲を網羅する必要はないけれど、2枚組の『スタンダード・エディション』は、2014年のリイシューもの年間ベストの1位である。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE