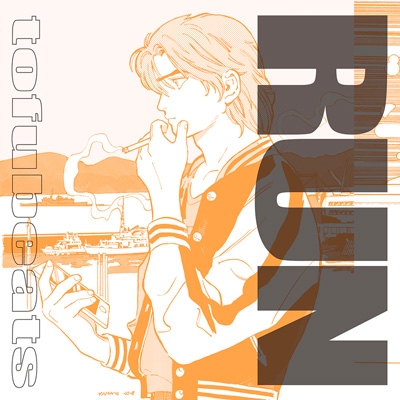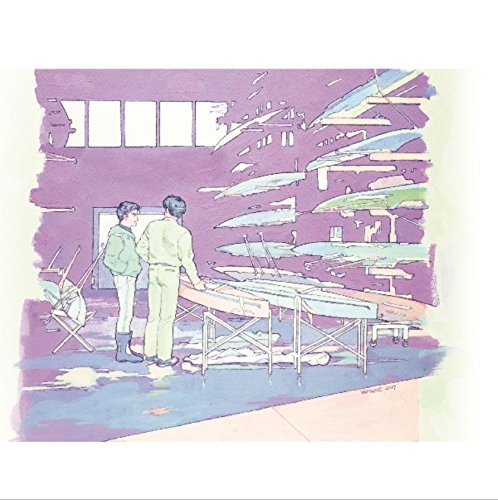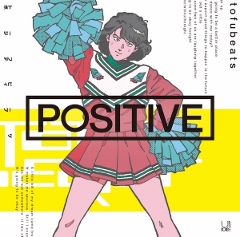MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > tofubeats- RUN
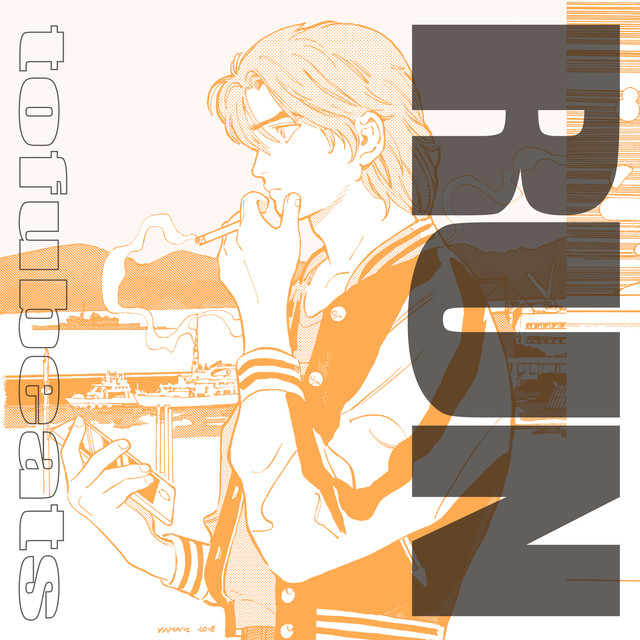
揺れている。やはりそれは地震によって引き起こされたことなのだろう。3・11以降、具体性を欠くものや実現可能性の低いものにたいする侮蔑がはびこっている。対案なき批判は一考の価値なしという風潮は完全にそうだし、批判する側も「投票に行きましょう」とか、具体的なことを強調せざるをえなくなってきている。明確な効果が見込めることに注力したくなる気持ちもわからなくはないけれど、それはようするに見返りを求めるということであり、つまりはビジネスの論理、資本の論理によってすべてが覆いつくされかけているということである。直接的には何をも解決しないだろう妄想や夢を語ること、それは想像力そのものにほかならないが、それが今日ほど困難になった時代はかつてなかったのではないか。
映画『寝ても覚めても』が舞台を3・11以降に設定し、仙台という場所に重要な役割を与えることによってえぐりだしたのは、そのような想像力の縮減というリアリティである。同作では東出昌大がひとり二役を演じているが、そのふたりは現実的なものと夢想的なもの、実現可能性の高いものとそうではないもの、具体的に解決可能なものと不可能なものとの対立を体現している。その二項のなかで前者を選びとらざるをえないということ、それこそが『寝ても覚めても』の描きだす現代日本のリアリティだろう。
メジャーからは4作目となる tofubeats の新作『RUN』は、その序盤をJポップのマナーに則った曲で固めている。まずはグライミーな表題曲でがつんとインパクトを与えつつ、すぐさまスキットを挟みこみ、『電影少女』の主題歌となった“ふめつのこころ”やポップなハウス・チューンの“MOONLIGHT”へと繋いでいく。広汎な層にたいする訴求を怠らないこと。この流れには、前作『FANTASY CLUB』が思うように「普通のユーザー」のもとへ届かなかったことの反省が表れているといえるだろう。
けれどもクラブ・ミュージックのリスナーにとってエキサイティングなのは、そのあとに続くインストゥルメンタルの曲たちだ。tofubeats はかねてよりハウスを大きなインスパイア源としてきたが、『RUN』にはとりわけその影響が色濃くにじみ出ている。彼のDJピエール好きな側面がよく表れた“YOU MAKE ME ACID”、“RETURN TO SENDER”、“BULLET TRN”の3曲は、フィット・オブ・ボディやリトン&カー=ロウ、あるいはアゲインスト・オール・ロジックなどと同様、オールドスクールなハウスの亡霊たちに憑依されることでいまのアンダーグラウンドのトレンドとの接点を確保している。Jポップのフィールドにおいてこれほどアシッドを響かせる作品はかなり珍しいんじゃないだろうか。なかでも“RETURN TO SENDER”はブー・ウィリアムスの甘くせつない“Summer Love”を彷彿させ、2分を過ぎたころにはいやでも涙腺がゆるんでくる。
それらに続く8曲目の“NEWTOWN”は、しかし、そのような昂揚を抑制しつつ物憂げなムードを呼びこんでいる。自身が育った環境でありまたかつてのステージネームでもある「ニュータウン」なる言葉を冠したこの曲は、ようするに tofubeats のアイデンティティを強調しているわけだけれど、ふたたびヴォーカルを招き入れることでかつて政治経済的な意志によって創出されたオールドなタウンを「新しい街」として解釈しなおしている。それは過去のハウスをリサイクルする彼のスタイルそのものでもあり、間違いなく本作のハイライトのひとつだろう。
その後アルバムはポリリズムの実験が試みられる“SOMETIMES”を経由して、ふたたびJポップのマナーへと立ち戻っていくが、そこでようやく本作全体を貫くテーマが明らかになる。10曲目“DEAD WAX”では驚くべきことに、彼の代名詞ともいえるオートチューンが影を潜めている。繰り返される「自分だけがいる」という言葉。あふれ出るロンリネス。ここでリスナーは冒頭のタイトルトラック“RUN”に同じ情感が忍ばせられていたことを思い出す。最初のヴァースの終盤、一瞬だけオートチューンが解除されたかのように聞こえるヴォーカル。そこで歌われる「たった一人走る時」というフレーズ。
なぜ tofubeats の新作は『RUN』と題されているのか。「走る」とはいったい何を意味しているのか。一度でも長距離を走ったことのある者ならばわかるだろう、それは前へ進むことでもなければ過去を振り切ることでもない。ランナーはつねに、ひとりである。走るとはすなわち、孤独を引き受けることにほかならない。まさにそれこそがこの『RUN』の主題なのだ。それは本作が tofubeats にとって初めてのゲスト不在のアルバムであることによっても明かされている。
とはいえそれはこのアルバムが閉じていることを意味しない。本作には『電影少女』や『寝ても覚めても』のタイアップ曲が含まれており、それは創作に外部の意向が関与していることを示唆している。その関わりのなかで出会った人たちからの影響もあっただろう。あるいは彼が制作中に読んでいたといういくつかの本もまた大きな役割を果たしているにちがいない。重要なのは、それら他者からもたらされる霊感や着想を整理し、吸収し、昇華するにあたって、tofubeats がひとりにならなければならなかったという事実だ。音楽は表現である。ゆえにそれは、想像力の問題と直結している。すなわち、不可能な夢の断片をつかむためには、孤独になる必要があったということだ。
オートチューンと地声。歌とインストゥルメンタル。Jポップとアシッド・ハウス。それらのあいだで tofubeats は揺れている。あるいは、政治的になりたくないと思いながらも、他方で世相を映し出さなければと考えてしまう逡巡。その姿はまるで『寝ても覚めても』で麦と亮平とのあいだを往き来する朝子のようではないか。
映画の終盤、朝子は山をバックに疾走する。目の前を男が逃げていく。朝子は孤独だ。不可能な夢を追い求めたがゆえに「クズ」呼ばわりされた朝子、そんな彼女が生きられる地平を探るかのように、この『RUN』は分裂を隠さない。他者と関わりながらも、孤独であろうと努めること。夢と現実のあいだで引き裂かれ、具体的なものへと引っ張られながらも、想像力への信頼を失わないこと。それこそが、前作で「ポスト・トゥルース」という時事的なテーマを掲げていた tofubeats がいま、あえてこのアルバムで実践していることなのではないだろうか。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE