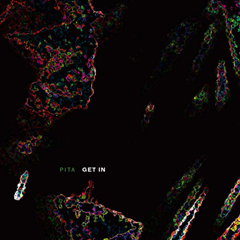MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Joanna Newsom- Have One on Me
還俗、と言うんだろうか。僧侶が普通の人に戻ること。これが僧侶ばかりでなく例えば巫女さんなんかにも使える言葉だとすれば、ジョアンナ・ニューサム、彼女はこの新作において「還俗」した。
数年前、フリー・フォークという概念とともに彼女のファースト・アルバム『ミルク・アイド・メンダー』を手にした方は多いことだろう。リリースが2004年、フリー・フォークという名が人びとの口の端に上るようになったのもこの前後である。デヴェンドラ・バンハートがキュレートしたコンピレーション『ゴールデン・アップルズ・オブ・ザ・サン』のリリースが同2004年だ(シックス・オルガンズ・オブ・アドミッタンス、ジョゼフィン・フォスター、エスパーズ、バシュティ・バニヤン、ココロージー等を収録)。ジョアンナはこの後、デヴェンドラとともにツアーに出ている。
世界史的にはウォーカー・ブッシュが大統領二期目の当選を果たしたものの、開戦前に比して支持率は著しく低下、都市リベラル層の反ブッシュ的なムードが高まっていた頃だ。翌2005年には、ブッシュ政権はイラクの大量破壊兵器問題の報告に誤りがあったことを認めるに至っている。ハリケーン・カトリーナがアメリカを襲ったのもこの年だった。アメリカがひとつの時代の終わりへ向かって、加速しはじめた――そんな時期である。フリー・フォークなる音楽は、その一種超俗的な佇まいによって、このように悲惨でめまぐるしいアメリカからの逃走として、あるいは闘争として、人びとの耳と脳裏に鮮やかに刻み込まれた。当時のリベラルで知的なリスナー層はこれを無視できなかったし、『ピッチフォーク』等の左派的メディアが現在持つ影響力を準備したムーヴメントだったとも言える。
彼女はこの頃、ほんとうに巫女のようだった。大きなペダル・ハープを抱え、悪魔的なロリータ・ヴォイスで独特の歌い回しをする。それはこの世の外のものを引き寄せ、世界を奇妙に揺さぶる。霊感に満ちた、一聴で人の耳を征服してしまう声。実に驚くべきパフォーマンスだった。
本作において真っ先に感じるのはその声の変化である。しかも1曲めで使用されているのはピアノだ。『ミルク・アイド・メンダー』がジョアンナだと思っていると、軽い戸惑いを覚えるだろう。これは、言わば「普通」である。少女の形をした悪魔の声、あるいは人ではないものと交信する声、あの声はどうしたのだとそう思うはずだ。
どことなくバルカンな異国情緒をたたえた哀愁フォーク・ナンバー"イージー"。室内楽的なアレンジを施されている点、前作の『イース』を思い起こさせる。『イース』においては、巫女的な彼女、あるいは悪魔的な彼女は世俗の権力を操って女王となった。それを永遠の寿命の中での退屈しのぎとした......そんなふうな想像を掻き立てる。だってアレンジにヴァン・ダイク・パークス、プロデューサーがジム・オルーク、エンジニアがスティーヴ・アルビ二だ。ジャケットも女王の偉容。大作主義的な佇まいも浮世離れしているし、彼女はこのままいくとどこに行き着くのだろうかと、超俗性が極まってカルト・スターに終わってしまうのではないかと個人的には危ぶんだ。が、本作のこの1曲目。ストリングスの綾の向こうから響くのは普通の声だ。もちろんジョアンナの声ではある。が、巫女ではなく、悪魔ではなく、歌うたいの声だと感じる。
この感触は表題曲である2曲め"ハヴ・ワン・オン・ミー"、3曲目"'81"により顕著だ。この2曲、楽曲と声自体はむしろ『ミルク・アイド・メンダー』に近い。とくに"'81"はハープのみでシンプルに紡がれる、ジョアンナ得意の3拍子の小品で、初期の破壊力のかわりにおだやかな色彩を感じる。4曲目などはジョニ・ミッチェルやローラ・ニーロなど70年代の都会派シンガー・ソングライターの手になるピアノ・ポップといった印象さえ受ける。ディスク2はとくにそうした印象が強い(なんと3枚組の箱入り仕様だ)。なるほど、彼女は「還俗」したのだ。そして新章を開こうとしているのではないだろうか。
"ハヴ・ワン・オン・ミー"は「黒い娼婦」の歌である。19世紀アイルランドのダンサーで、バイエルン王ルートヴィヒ1世の公妾、通称ローラ(国内盤付属の対訳参照)。スキャンダラスなダンスで手にした彼女の栄光と転落、不遇の晩年に取材した叙事詩だ。3枚分のスリーヴにプリントされたジョアンナの写真はいずれもこの「黒い娼婦」を模したものと思われる。自らをかのローラになぞらえ、俗界に舞い降り、人びとに芸を売って生きていく。言葉が悪いなら、フィギュア・スケートに例えたっていい。少女性や若さにしか宿らない一種のエネルギーを、難度の高い技に変換するだけで多くの人びとを魅了できる競技人生を引退し、より多彩な武器を手に、プロとして人びとに芸を売っていく。そうした覚悟が、下着姿のしなやかな肢体に読み取れなくはない。同時にそこには、絶対に客を飽きさせるものかという自信もある。
ハープの音色で奏でられる彼女のアパラチアン・フォークは、それがかつてはケルトの森からやってきた音楽であることを遥かに思い起こさせる。中世的で、現代的な感情表現が希薄な、緑青の錆びになめらかに覆われた音楽。全体として彼女は等身大の「私」をテーマとしない。古い伝承や古い詩のような物語を節にのせて誦する。時々は風刺も入る。
ディスク3はまさに中世の吟遊詩人を思わせる曲群だ。他の2章と同様にピアノの曲ではじめ、ピアノの曲で終えているのが象徴的だが、アップライト・ピアノのようにざらついたカジュアルな音を出している点がまた良い。歌のプレゼンスを助ける、完全に伴奏としての音だ。リコーダーや民族楽器をフィーチャーした曲でも、そうした彩りは彼女の歌でつながる絵巻物の背景に過ぎない。はねるような曲は少なく、しっとりとして引力のある曲で構成されている。
芸を、歌を売るものとして彼女は帰ってきた。再びプロデューサーに、バート・ヤンシュやデヴェンドラ・バンハートも手がけるノア・ジョージソンを迎えている。おそらく彼女は一生歌いつづけるだろう。そして歴史に名を残すだろう。その準備が整ったという印象だ。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE