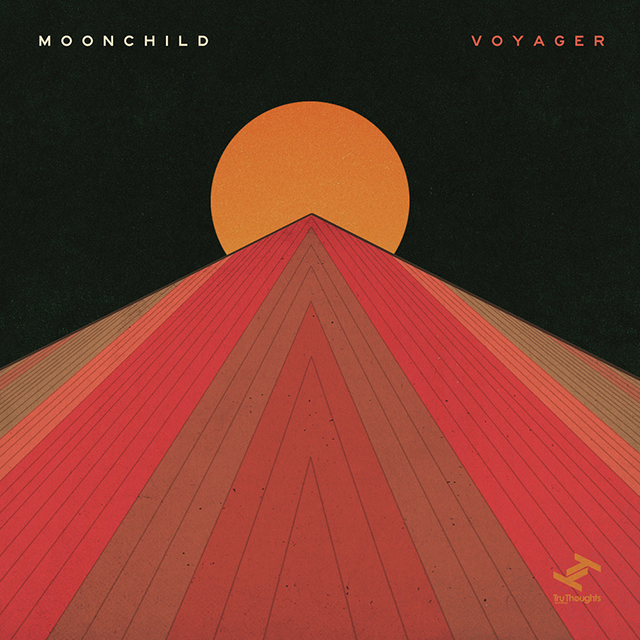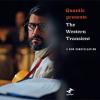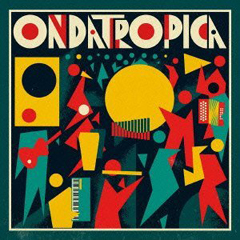MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Quantic presenta Flowering Inferno- Dog With a Rope

クァンティックのレコードを僕が最初に買ったのはずいぶんと遅い。2006年のミスター・スクラフとの12インチ・シングルだ。ウィル・ホランドのデビューは2000年だから、そのときにはアルバムを4枚も出している。つまり、僕とクァンティックとのあいだにはそれなりの距離があって、その12インチに関してはミスター・スクラフという媒介のおかげでたどり着けたに過ぎない。レコード店の人から「こういうのも聴くんですね」と言われたのを覚えているが、三田格を渋谷ディスクユニオンの地下で見かけたという人から「いました!」と言われたことがあって、きっと僕の場合も店からしたら意外性のひとつだったのかもしれない。そう思うとずっと追ってきている人には申し訳ない気持ちだが、まあ、嫌いなわけではないですよと言うしかない。
ラテン音楽を聴いていると、僕はいまでも90年代の渋谷にあった〈ミスター・ボンゴ〉というレコード店の店長のことを思い出す。あの店には、最新のクラブ・ミュージックが並んでいる店内の片隅に、店長の趣味のサルサをはじめとするラテン音楽の、しかもそれなりに値打ちの付いているらしいオリジナル盤がつねにあった。イギリスからやって来たその店長は、あるとき最新の12インチを手に抱えている、まがりなりにも客である僕に対して、「よくそんなものを買うね」と言ってきたことがあった。その言葉の次が彼の口から出ることはなかったが、彼が心のなかでこう言ったことは伝わった。「すぐに消えてしまうような12インチを買うなんて、カネを捨てるようなものだ。信じられないよ。僕なら一生もののラテン音楽を買うけどね」
それ以来、ラテン音楽を意識するようになった。ニューウェイヴ時代にブルー・ロンド・ア・ラ・タークやキッド・クレオール&ザ・ココナッツを聴いている世代としては、多少なりとも親しみだってある。「嫌いか?」と問われれば「好きだ」と答えるものの、正直な話、それを本格的に追求しようとは思わなかった。それをするなら、他のジャンルをある程度は諦めなければならないだろう。歴史や文化を勉強するのは嫌いじゃないが、5000円以上もする重要盤をリスト化し、探しに出掛け、そして揃えなければならない。スペイン語も習わなければならないだろう。その覚悟が自分にはないし、どのアルバムから聴きはじめればいいのか教えてくれる入門書もなかった。ポップ・ウィル・イート・イットセルフとティト・プエンテを両立させる自信もなかった。
だが、人間、歳を取るにつれて自分が知らなかった世界を旅したくなるものなのだ。僕がそうだったように、クラクソンズしか愛せない若者もブーガルーやクンビアやマンボを聴くときが来るかもしれない。それは自分の知らなかった"文化"との出会いで、個人的だがひとつのハイブリッド体験となる。それは自分のなかの自分が嫌悪する自分――あるいは極めて日本的な美徳に支配された自分に裂け目を与え、少しだけだが自由になった気分を味わえる。オシムがどれほどドイツの組織力を評価しようとも、やはりどうしてもマラドーナとメッシのばっかみたいに個人で勝負する自由奔放なフットボールが愛おしく思えてしまうように、いまの僕がラテンを避けて通ることはできないのである。
だからクァンティック・プレゼンタ・フラワリング・インフェルノ名義によるセカンド・アルバム『ドッグ・ウィズ・ア・ロープ』も魅力的に思える1枚である。ウィル・ホランドは、〈トゥルー・ソーツ〉のレーベル・オーナーであるロバート・ルーイと同じように、故郷のブライトンでファットボーイ・スリムがスマイリーとブレイクビーツのレイヴィングに励んでいた頃、ヒップホップを貪り、4ヒーローや〈ニンジャ・チューン〉に心酔して、飽きもせずジャズやディープ・ファンクを掘り続け、ラテンのエキゾティズムに憧れていた。ダンス・カルチャーがエネルギーを失いかけている頃、クァンティックはラップトップの電源を抜いてオーケストラをオーガナイズした。レコーディングやライヴをおこない、そして数年後に彼は音楽の探究のためにコロンビアへと向かった。フラワリング・インフェルノはその成果のひとつである。
この音楽の面白さはUKならではのハイブリッド性ということに尽きる。本作に関して言えば、ダブ、クンビア、サルサなどがシェイクされている。このように多文化的な響きを混合していくメソッドは、ポップ・フィールドではディプロの得意技といったところだが、同じDJカルチャー的アプローチであってもウィル・ホランドはギミックなしで勝負する。ディプロのように移り気ではなく、探求的なのだ。
そして〈トゥルー・ソーツ〉からデビューして〈ニンジャ・チューン〉移籍後に大きな成功をおさめたボノボのように、レトロの模倣という誘惑に屈することもなく、トロピカルな南米音楽の魅力を彼なりのアレンジでディープに伝えようとする。この手の試みが失敗するたいていの場合は、DJカルチャーの軽薄さのなかで消費されてしまうか、広告写真のようにイメージを強化し過ぎるあまり退屈な洗練性に陥るかのどちらかだが、ホランドはそうした落とし穴も回避する。ジャケットの写真のように路地裏のニオイが匂ってきそうなヒューマンな音楽で、ざっくりと言えばサウンドシステムと南米との出会い、ダビーなサルサである。
伝説的なペルーのピアニスト、アルフレディト・リナレスをはじめとするゲスト陣は玄人でもそれなりに納得するメンツらしい。ジャマイカ生まれでイギリス在住のベテランのレゲエ・ドラマー、コンラッド・ケリーが叩いているかたわらで、60~70年代に活躍したコロンビアのバンド、プレゴヨ・イ・ス・コンボ・バカナのフロントマン、マルキトス・ミコルタをはじめとする現地のお歴々たちも参加している。ちまたでの評判の通り、レトロな響きと未来......とまでは言えないまでも新し目のサウンドの両方を好む耳を惹きつける作品だと言えるのではないだろうか。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE