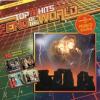MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース
- 『成功したオタク』 -
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙
Home > Reviews > Album Reviews > Prince Rama- Shadow Temple
何をいまさらというか、またそれかという話で恐縮だが、エスケイピズムの問題について考えてみる。ここ数年、ポスト・マス・カルチャーすなわちデジタル時代に突入した音楽シーンでさんざん指摘されていることだ。たとえば『ピッチフォーク』のアーケイド・ファイヤーのアルバム・レヴューにこんな一節がある。「あなたがエスケイピズムとしてのロック・ミュージックを高く評価するのであれば、アーケイド・ファイヤーの『ザ・サバーブス』はより小さく見られる可能性がある」
アーケイド・ファイヤーはゼロ年代以降に登場した、社会や政治を意識する数少ないロック・バンドのひとつだが、この一節は、彼らを積極的に評価するというよりも、アニマル・コレクティヴ以降のエスケイピズムをシニカルに突き放したいという欲望がもたらした言い回しのいち例だ。先月、『スヌーザー』誌でマニック・ストリート・プリーチャーズの取材をさせていただいたときに、ジェームス・ディーン・ブラッドフィールドは「(現代では)政治的になるのが難しい、とは言え、ある世代のミュージシャンがふたつも戦争を経てきて、経済の破綻を目にして、それについてクソ1曲も書かないなんて、信じ難いよ」と言っていたが、この意見に関して半分は同意できるが、異論もある。パンク・ロックがテレビのCMで使用され、ビート詩人たちのポートレイトが広告になる現代において、そして、60年代の遺産とはウッドストックではなくてシリコンバレーだったという説が有力な時代において、戦後カウンター・カルチャーの神話がそれを原体験していない世代にとってどれほど説得力を持つというのだろう。
それでも、カール・マルクス・シアターでのライヴ経験を持つ誇り高きウェールズ人(マニックス)の洞察力は衰えていないと僕は思った。彼は「現実に気付いて、内面的な考えをリアリスティックなものにしなきゃいけないんだ。だからこそ、これまでになく夢見ることが重要になってる」と話しているが、それこそ僕にはエスケイピズムというタームで説明されているいまの若い世代の音楽の背後にある衝動ではないかと思えてくる。彼らは真実を見たいがために、目の前の現実(と思われている世界)から逃避しているとも言えるからだ。これは目新しい話ではないが、音楽文化においてはつねに重要な一手となっている。レイヴァーが当局の目を盗んでパーティへと辿り着くように、逃避とはときにリスクを承知でメインストリームの文化に背を向けることであり、それは出発の合図かもしれないのだ。
それからもうひとつ、これはいま書きかけの自分のコラム(forgotten punk)でも触れようと思っている話題だけれど、アニマル・コレクティヴ以降のインディ・ミュージックを特徴づけていることのひとつに、白と黒との衝突(もしくは混合)の喪失があるように感じている。要するにブラック・ミュージックの要素がほとんどない、あったとしてもずいぶん希薄になっている。白い社会における黒い体験がどれほどカウンター・カルチャーの神話に貢献してきたのかは、歴史を少しでも紐解けばわかる話なので割愛するが、オバマが大領となったこの社会における黒への共振に関して、つまり白と黒の二項対立に何らかの変化が起きたとしても不思議ではない。また、かつてルー・リードは「俺は黒人になりたい」と歌ったものだが、たとえばいまのジェイ・Zを見ているインディ・キッズが同じような気持ちになれるのかも疑問でもある。
そして、そうなったときに彼らが新たな真実を求めてさらに外側へと、さらに遠くへと目を向けたとしても理解できない話ではない。日本人はそれを昔からやっている。自分たち自身から離れるように遠くにあるアメリカやヨーロッパへと思いを飛ばし、さらに遠くのジャマイカやブラジルへと漂泊し、つまり融合的に物事を吸収したように、彼らはいまドイツやアジアやアフリカといった彼らにとっての遠方への密会に飢えているように思える。東洋思想と接触した『森の生活』の作者で知られる19世紀の作家ソローのように、逃げることで真実を見ようとしているのかもしれないし、インディ・キッズの気まぐれの異国趣味か、さもなければぶっ飛んでいるだけなのかもしれない。正直、まだわからないが、言葉よりも先に音が出ている。意味よりも先に声が出ているのだ。もうしばらくはつき合ってみようと思う。
アニマル・コレクティヴが主宰する〈ポウ・トラックス〉からリリースされたプリンス・ラーマのデビュー・アルバム『シャドウ・テンプル』は、ドイツのポポル・ヴーやアモン・デュールを経由してインドへと流れ着く。ヒンズー教から名前(ラーマ)を引用したこの3人組は、深いサイケデリアを彷徨いながら、アフリカ系アメリカ人が発明したロックンロールのリズムをギャング・ギャング・ダンスとも共通する原始主義的なトライバリズムへと変換する。
ロックにおけるインドへの接近は60年代にもあった。しかし、ジミ・ヘンドリックスの『アクシス:ホールド・アズ・ラヴ』があくまでブルース・ベースの音楽だったのに対して、プリンス・ラーマのリズムや深いリヴァーブのかかった女性ヴォーカルにはロバート・ジョンソンのかけらすらない。少なくとも60年代のクリシェではないのだ。とはいえ、あまりにもドロドロで、アフリカ系アメリカ人のセンスがもたらした音楽に長く親しんできた耳にはそれなりの違和感があるのも事実だ......が、逆に言えば、彼らはそれだけ現在におけるカウンター......とまではいかないかもしれないけれど、時代のノイズとなっていると言える。まだ小さなノイズだが、ノイズがないところに未来はない。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE