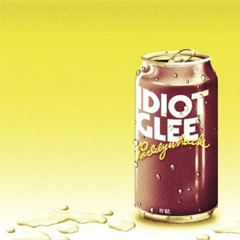MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Idiot Glee- Paddywhack
本人は「ポスト・ドゥワップ」と言っているようだし、『ガーディアン』は「ピアノ・ポップ・ウェイヴ」と苦しい名状を与えていて、しかし音を聴くかぎりでは両者が「チルウェイヴ」という言葉を避けているのがありありとうかがわれる。実際のところは『パーソン・ピッチ』から大いに影響を受けたベッドルーム・ポップ。ドゥワップなど50年代のブラック・ミュージックやモータウンといったレトロな音楽スタイルを参照しているが、とろとろとしたリヴァーブをきかせるプロダクションといい、寄せては返すコーラス・ループといい、パンダ・ベア的な方法論と現実逃避的な企図を含んでいて、これをチルウェイヴと呼ばないわけにはいかない。
ケンタッキー育ちの青年ジェイムス・フライリーのプロジェクト、イディオット・グリーのデビュー・フル・アルバム。ジェイムスにはクラシック・ピアノの素養があり、ソロ・ピアノのカセット・テープもリリースしているようだが、彼のメロディ・センスとリズムへの独特の感度が、ピアノ演奏においていかなる効果を生んでいるのか非常に興味がある。メロディとリズム。このシンプルな要素を洗練させることで、彼の音楽は一種の中毒性を生み出しているとさえ思う。
一聴したところモーニング・ベンダースと近い部分を抉っているようにも思われるが、こちらのほうが機能性の高い音である。音として気持ちよく、身体的な効果が期待できる。足し算でも引き算でもない、もともとピースが限られた積み木を、組んだりこわしたりするような、ミニマルな音使い。神経にやさしく、しかしそれだけで頭の働きを麻痺させそうな力を持っている。たとえば"ドント・ゴー・アウト・トゥナイト"のスネアとコーラスが響きあう空白の多い音作り。ベースとキックは渾然一体としていて、スローだがパーカッシヴな心地よさを生み出している。
にぶく、ゆるく、西日のような色彩を感じさせるリヴァービーな音像は、つづく"オール・パックト・アップ"に引き継がれ、発展する。これこそは『パーソン・ピッチ』である。歌ものとしてはフリート・フォクシーズや、フォスターの歌曲などを思わせるアメリカン・フォークロアのスタイルだが、バック・トラックやコーラスのループ、奇妙な残響感、トロピカルでも土俗的でもエキゾチックでもありかつ世界のどこでもないという、あのパンダ・ベアの手つきをすみずみに感じる。
ほどよくまどろんでいると"トラブル・アット・ザ・ダンスホール"のダビーなサイケ・ナンバーがおもむろにはじまる。グロッケンやピアノはオルガンに取って代わられ、ヴォーカル・スタイルもややワイルド、コントラストのついたトラックである。この曲の挿入で作品に奥行きがつく。またサイケデリックなムードがこれを境に色濃くなってもいて、構成も巧みなようだ。しばらく後に出てくる"エフ・オー・イー"のジョナサン・リッチマンを彷彿させるドゥワップもとてもよくて、あのヴィンテージ感に比してリズム・トラックがまったくオートマチックな打ち込み音をはじき出しているのがたまらない。
"ウェルカム・バック"の、安っぽいリズム・パターンもとてもきいている。リズムの有り無し、抜き差し。あってなさそうに思われるリズム感覚が、じつは替えのきかないほど楽曲の中に大きな比重を占めていることを、このいくつかの楽曲が証している。
ラストはベースと4声のコーラスがシンプルに締める。牧歌的なラインと"イン・ザ・サディスト・ガーデン"というタイトルのミスマッチ、そしてアップライトのようなややちゃちな響きのピアノの後奏が奇妙な後味を残す。旧きよきアメリカ......を擬した、いや、鏡映しにした、存在しない世界。イディオット・グリーのレトロ・ポップは、懐古趣味というよりは、このようにリアルを描かないことによって別世界をひらく、そしてそこに浸って帰ってこれなくするためのまじないのようなものだ。
フリート・フォクシーズも、あるいはモーニング・ベンダースやザ・ドラムスなど、活気づくビーチ・ポップ・シーンが触れられない、音楽の闇のようなものに、彼は触れている。そしてそここそがジェイムスの逃避先。やわらかい光を持った、闇のビーチ・ポップ。5回聴けば骨抜きになってしまうはずだ。最後に多くのメディアに倣って、彼ジェイムスがモルモン教徒として育ったことを注記しておくが、筆者にはそれと音との関係についてとくに指摘できる知識はない。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE