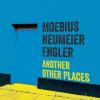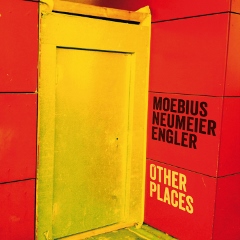MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Qluster- Rufen

三田 格 Nov 28,2011 UP
Kではじまるクラスターからコンラッド・シュニッツラーが抜けてCではじまるクラスターになり、さらにメビウスの代わりにオンネン・ボックが参加してQではじまるクラスターに。あはは。ボックはレデリウスがメタル・ボウルなどの演奏で参加していたクリスチャン・キュービック(裏アンビエントP102)の人脈からフック・アップされたようで、ツァイトクラッツァー・アンサンブルの一員として活動するサウンド・インスタレイションの若手。
CとQは並行して活動を続けるらしく、それはつまり、レデリウスから溢れ出る創作意欲をメビウスだけでは受け止めきれないということなのか、いずれにしろレデリウスとクリント・イーストウッドはいまや暴走老人の域に達していることはたしか。2011年にレデリウス・ミュージックから配信されたコラボレイションの数は......とにかく多い(ちなみに寡作とはいえ、09年にリリースされたメビウスのソロ作『クラム』の評価もかなりのもの)。
Qではじまるクラスターも、デビュー作『フラーゲン』は東日本大震災の直後にリリースされ、年内にはライヴ・アルバム『ルーフェン』も間に合うというハイ・ペースぶり。モーガン・フィッシャーとのジョイント・アルバム『ネヴァーレス』や、とくにティム・ストーリーとの『インランディッシュ』で印象付けられたように、ここ数年、ニュー・エイジ色が強くなっていたレデリウスの嗜好をそのまま反映していたスタジオ作に対し、ライヴ・ワークでは緊張感を増した実験性が回復し、完成度では圧倒的にこちらを取りたい。あるいはニュー・エイジとサウンド・インスタレイションは、つい最近までは似ても似つかぬものだったのに、アンビエントという概念によってそれらは奇妙な融合を成し遂げ、低俗とアカデミズムはあっさりと横断されていくと聴くこともできるか。一部でミュージック・コンクレートとイージー・リスニングの境界が失われつつあるように、ロマンとアンチ・ロマンがせめぎ合うというのが時代の要請なのだろう(?)。
ニュー・エイジというキーワードの復活にはOPNもひと役買っているところがあるとは思うけれど、2011年のみならずアンビエント・ミュージック全体でもベスト10内には必ず入ってしまうに違いないアリオ・ダイ&ツァイトの3作目『イル・ジャルディーノ・エルメノイティコ(解釈学的庭)』から半年ほど後にリリースされたダイのソロ18作目にもニュー・エイジとの危ない橋を渡ろうとする傾向は聴き取れる。ツァイトとのコラボレイションでは華やかで明るく、人生への祝福に満ちたファンタジーが基調をなしていたのに対し、『ハニーサックル』では同じように慈しみと類まれなる穏やかさを感じさせながら、どこかに抑制された情念や漠然とした不安を潜ませている。「悪い予感のかけら」とでもいうのだろうか、作風の落ち着かない人なので、近作との関連性や反動といったものから生まれたものではないと思うものの、『イル・ジャルディーノ・エルメノイティコ』ほど誰彼にでも薦めたいものではなく、この感じが必要な人に上手く伝わればいいなと思うだけである(こんな書き方ではとても無理だろうけれど......)。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE