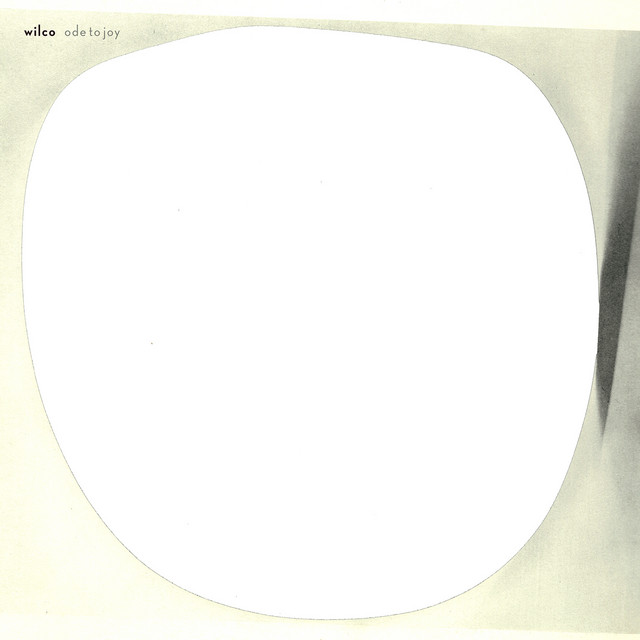MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Turntable Films- Yellow Yesterday
ボン・イヴェール(というかジャスティン・ヴァーノン)を見るために今年は珍しく真面目にグラミー賞を見ていたのだけれど、いざ受賞して本人が出てくると、それはやはりどこか妙な光景だった。ヒゲ面の普通の、いや、地味めの青年が述べたスピーチで印象的だったのは、「自分はこの会場に縁のないようなミュージシャンでも素晴らしい才能があるひとたちを知っているから、彼らに感謝を述べたい」という部分と、「ウィスコンシンのオー・クレアのみんなに感謝」した部分だった。『リーマン・ショック以降のUSインディ』で書いたことの続きとして述べるならば、それは現代のアメリカで市井に生きる人びとのネットワークの充実がグラミー賞のような権威の場で、しかし権威とは無縁のまま可視化された瞬間だった。
京都を拠点とするターンテーブル・フィルムズのフォーク・ロックは、間違いなく昨今のUSインディにおけるフォークやカントリーの充実とシンクロによって生み出されたものだ。しかしたとえば、バンドの最大の影響元であるウィルコが宿命的に追っているような重さや痛切さはここにはない。土臭さもない。むしろ洒脱さや軽やかさこそが魅力となっているこのデビュー作を聴いていて僕が思い至ったのは、シンクロしているのは音楽性よりも、経済とは別の場所で豊かであろうとするアティチュードそのものではないかという考えだ。
とはいえ、ターンテーブル・フィルムズの音楽はアメリカのフォークやカントリー、ブルーズからの直接的な影響を受けている。デビュー作となる『イエロー・イエスタデイ』にもそれはしっかりと刻まれていて、何よりもアコースティック・ギターの音の響きが非常に丁寧に鳴らされているし、鍵盤打楽器やフルートを使った音色の多彩さにしてもそうだろう。しかしながら、USインディといってもヴァンパイア・ウィークエンド辺りを連想させるような軽妙なポップネスや、クラウトロック調の"アニマルズ・オリーブス"のサイケデリアやダンサブルな"ゴースト・ダンス"を聴いていると、ここには影響元から少し距離を置こうと腐心した跡が見受けられるように思えるのだ。言い換えるならば、いまもアメリカのフォーク・ミュージックが背負う「アメリカの物語」から。結果として、ここにはたとえばフリート・フォクシーズの潔癖さを伴うコミューナルなフォークとはまた別の文脈にある、京都の若者が鳴らすポップスが存在している。
つまり、これは自分たちのことを「ターンテーブル」「映画」と名づけたバンドがそのアイデンティティを確立した作品だ。海の向こうで生まれた豊かな文化と物語を、あくまで自分たちの生活する場所で味わうこと。アメリカの若い世代が発掘したカントリーやフォークを自分たちの時代を背景として更新したように、ターンテーブル・フィルムズは海外で発見した音楽をその豊かさを損なわないままに、しかし遠慮せずに翻訳する。何しろ「恋をしなくちゃ」という言葉で始まる本作には、期待や不安、苛立ちや退屈といった日常の些末な感情が表れては消えていく。それらには洒落た言葉と音がつけられ、全編がクリアな発音の英語詞でもって甘いヴォーカルで歌われる。「(夏のドラッグの)効き目の切れた今日に、僕らは終わってしまったね」"サマー・ドラッグ"......たとえばそんな風に呟かれる夏の終わりの感傷。そのあくまで清廉とした佇まいは、大阪の雑然とした街に慣れている僕としては......いやきっとそうでなくても、京都の街の瀟洒さが産み落としたものだと思える。アメリカを経由した、京都訛りのフォーク・ミュージックである。ボン・イヴェールが自らの孤独をウィスコンシンの冬の風景に託したように、ターンテーブル・フィルムズはこの国で生きる青年たちの日常を鴨川沿いの風に乗せている。
70%の20代が現状に満足していると言われても、30%どころかつねに1%ぐらいの感覚で世のなかとズレて隅っこで生きている僕のような人間には正直まったくピンとこないわけで、だから自分にとっては、たぶんに取るに足らない普通の青年たちの日常を精一杯の輝きを乗せて歌っているという点で、ターンテーブル・フィルムズは「自己充足」なんて矮小な価値観を軽やかに後にしているように感じられる。ここでは想像力と好奇心は海の遥か向こうまで広がり、だけど心はいま目の前ではじまりそうな恋に向かって動いている。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE