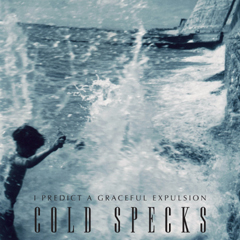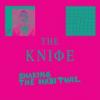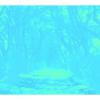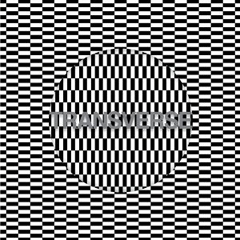MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Cold Specks- I Predict a Graceful Expulsion
夢を見ることさえ虚しく思えるこの時代に、それでも夢の世界を自由に、あるいは華麗に歩いて見せたのが、仮にビーチ・ハウスによるドリーミー・ソウルだったとすれば、コールド・スペックスは、数十年前にソウル・ミュージックが見た夢、その甘い記憶に耳を澄ませながら、沸き起こる余韻のいっさいを保留して、ささくれだった荒野を颯爽と、それも堂々と歩いている。素晴らしいモダン・ソウルの登場だ。ある時代を、しかもその時代のユースとされる世代が、同時代から消去された時代遅れなスタイルで生きること。それは二度と戻らない人生において、ある重要な季節を異邦人として生きることと言えよう。『ガーディアン』曰く、「過去100年のうちのどの時点で録音されたものだと言われても信じてしまいそうな」、なるほどたしかに同時代性の薄いオールドスクール・ソウルであるが、単なる懐古趣味とは言わせない気合、「私は誇りを持ってこのスタイルを選んでいるの」という迫力のようなものがある。
『ピッチフォーク』によれば、コールド・スペックスを名乗るAl Spxは、現在24歳の女性シンガー/ソングライター(かつギタリスト)であり、「デモ音源が放つ強烈な印象」によって、今年早々に〈Mute〉と契約している。今月29日発売、エレクトロニック・ミュージックにおける"浮女子"特集を組んだ本誌紙版『vol.6』。そこに登場する先端的なアーティストとほぼ同年代であるが、彼女は彼女の道を行っている。そこでは、ビル・キャラハン(a.k.a. スモッグ)めいたミニマルなインディ・フォークが丁寧に紡がれている。あるいは、アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズのようなディープ・ソウルが、優美な弦アレンジとともに夜を照らしている。バンドはときに、エレクトリック編成とエモーショナルなコーラスによって、アーケード・ファイヤーを彷彿するロックの高揚感を打ち出してもいる。ホーン・アレンジも情熱の花を咲かせている。そして、ほぼすべての曲において、ゴスペルの祝福が舞い降りている。
大げさではなく、『I Predict a Graceful Expulsion』は、モダン・ソウル・ミュージックの偉大なる1年となった2008年の火照りを少し思い出させてくれる。TV・オン・ザ・レディオの『Dear Science』、そして、ボン・イヴェールの『For Emma, Forever Ago』から譲り受けたような、情熱の手触りによって。惜しむらくは......アルバムに収録された約半分の曲が、オーヴァー・アレンジメントの装飾性に微妙に絡み取られている点である。これは作者に敬意を欠いた言い方だろうか? もちろん、インディのシーンから出発してさらに大きな世界を目指す過程において、すでに実績を積んだ人物たちと協働するのは、悪いことではないと思う。多くの人に会う前に、最低限の外装、身だしなみ、その清潔さに気を使うのは、むしろ自然なことだ。「メイシー・グレイのウィスパー版」なんて評が出るくらい洗練されたヴェルヴェット・ソウル、ないしはインディ・ゴスペルというべき本作の完成度は、リード・ギター以外のほとんどのサウンド・プロダクションに大きく関与したというジム・アンダーソン抜きには成し得なかったものだろう。
だが、このポスト・インターネットの時代にあって、聴衆を広く集めるひとつの手段は、(矛盾するようだが)聴衆の一部を想定から捨てることでもあるのではないか。「売りたくてウズウズしている音楽」には、やはりどこか類型的な出力があり、仮にアーティストが古いイメージのリスナー像を想定しているとすれば、敏感なリスナーにはすぐバレてしまう。「この音楽は自分に向けられたものではない」と。私が言うのではあまりにも生意気だが、ポップ・ミュージックの短くも長い歴史は、そんな聴き手を相当数、すでに育てているはずである。事実、ナイトメア・ロックの"Hector"などをジ・XXと比較する評論家さえ、いるのだ。無名の段階で〈Mute〉とサインするような逸材だ、いるかもわからない不特定の聴衆に目配せをする前に、もっと小規模で親密なリスナーを信頼してもいい。『I Predict a Graceful Expulsion』には、少しだけ勇気が足りていない。日本語で書いても伝わらないのはわかっているが、それでも書く。あなたの素顔、装飾の裏側、そのほころびがもっと見たい。
竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE