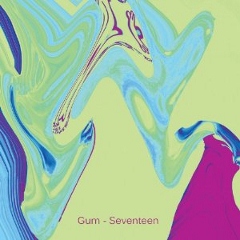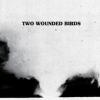MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Gum- Seventeen
マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの新作を不思議な思いで聴いた。あまりにも変わらないままのマイブラだったが、ではかりそめの新しさを狙ってエレクトロニックにしてみました、アンビエントをやってみました、ビートに凝ってみました、といった変化を見せたとして誰が納得しただろうかと考えてみると、やはりこれしかない。"オンリー・トゥモロウ"は最適解だ。というか、「10年1作」(22年ぶりだが)のような時間を生きる彼らにとって、「変化」ということほど軽薄な概念はないのかもしれない。
ロックという価値観において「変わらない」ことはとても両義的な意味を持つ。若く、既成の価値の枠組みを揺さぶるようなエネルギーをその本懐と考えるなら、変化や進歩のないものは基本的には謗りを受けるだろう。だが、ただほいほいとフォームを変えるのではファッションでしかないということになる。『mbv』には、昔の焼き直しという印象ではなく、そのフォームの古びなさ強靭さをあらためて確認させられたように感じた。変わらなさにおいてひとつの徹底と説得力を持っている。というか、ケヴィン・シールズの音がいまだ完成への途上を歩むものであり、またそれが跨ぎ越された跡もとくに見つからないという意味においては、まだその道の先駆であるとも言える。彼らのフォームは生きた形式ともいうべき、奇跡的な矛盾として存在している。
だから、マイブラとはバンドであると同時にジャンルでもある。作り手の多くは自分の音楽にタグ付けされることを嫌うものだが、この界隈ばかりはどうだろうか。そのようなことに頓着せず、フォロワーであるとかないとかいう意識もはじめからとくにないような、迷いのない後続を生みつづけている。例を挙げればキリがないが、たとえば2008年、パンダ・ライオットのデビュー作はよく売れていた。リリースはその前年だったが、じっくりと途絶えることなく、3年くらいは売れつづけたと思う。そのころ勤めていたレコード屋では店頭で音をかけるたびに問い合わせを受け、そのまま買っていくというお客さんも多かった。在庫を切らすと「いまかけている開封品でいいから買っていく」なんて言われた。
いまガムをかけたなら、同じようなことが起こるのではないかと思う。それは5年といわずその何倍ものあいだ更新のないシーンの存在と、更新の意味をナンセンスなものにしてしまうほど愛でられている音の存在を意味している。どうしてわれわれはこうした音がかかると一種の思考停止状態に陥ってしまうのだろうか――ドリーミーなファズ・ポップ、ディストーションのきいたメランコリック・ポップ、いろいろな言い方で間接的に語ることはできるが、要はマイ・ブラッディ・ヴァレンタインだ。リヴァービーな音響を持ったバンド・サウンド、フィードバック・ノイズ、中性的なウィスパー・ヴォイス、あるいは男女ヴォーカルの気だるげな絡み、メランコリックでミディアム・スローな楽曲、こうした音に対してほとんど脊髄反射的に反応してしまうという経験があるならば、ガムもまた抗しがたい力でもってその耳と心に押し入ってくるだろう。
もちろんライドの疾走感、スローダイヴの蒼みがかった叙情性も十分に発露されている。シューゲイザーと名のつく作品群の上に存在する、優れて美しい2次創作、そのように言うのがしっくりくるだろうか。新しい音楽観を提示する、シーンを牽引する新騎手、といった意識で作品を世に問うているのではなく、そのあり方は同人作家のように控えめなものだ。だが彼らに脚光が集まった背景には、デビューEPがヤックからの賞賛を受けたり、日本でもとくに支持の厚いシューゲイズ・ポップ・バンド、リンゴ・デススターのサポートを行ったりしているほか、この界隈ばかりでなく、当時折からのローファイ再燃の機運やジャングリー・ポップの盛り上がり、チルウェイヴ前後のドリーミーなサイケ・ポップへの注目のなかでジャンル外へと大きく波及していった重要バンド、ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートからの賛辞まで得ているというような経緯があるようだ。彼らのような活動をするバンドはUSに多いが、ガムはUKから出てきたバンドであることも頼もしい。そして今作のプロデュースに関わるというロリー・アットウェルは、テスト・アイシクルズでの活躍のほか、いままさに活動の旬を迎えているパーマ・ヴァイオレッツや、ザ・ヴァクシーンズ、ヴェロニカ・フォールズなどUKの良質なインディ・バンドを手がけてきたプロデューサーでもある。おそらくはガムにとってもプラスとなるディレクションがなされているのではないだろうか。
まだまだ情報の少ないバンドでありながら日本盤(日本企画編集盤)まで出てしまうというのは、こうしたアーティスト群、そしてそのファン層が日本でもいかに厚いかということを物語っている。彼らの何かと細やかなセンサーがコレだと推している点からしても注意したいバンドである。無論、あり方や精神性においてマイブラそのものとはまったく違う。だが、好みに合わせて好みの音を再組織するセンスや手腕において彼らが抜きん出ていることは疑いない。二十数年もの時間とおびただしいフォロワーたちの末端で、『セヴンティーン』というタイトルのパラレル・ワールドを描いているようにも思われる。二次創作(絵や映像とは単純に比較できないが)には二次創作の楽しみかたがあるのだ。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE