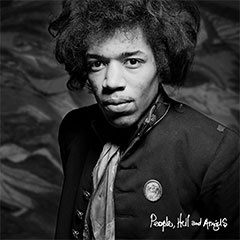MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Stephan Mathieu- Un Coeur Simle
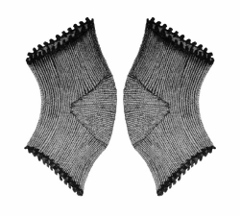
ステファン・マシューの新作『アン・クール・シーミレ』(〈バスカル〉)は、ここ数年に渡る彼の音響的実験、探求、そして作曲意識が「アルバム作品」として統合・昇華されている極めて重要な作品である。その意味では2004年の傑作『ザ・サッド・マック』(〈ヘッズ〉)以来、といえるだろう。
ステファン・マシューは、2004年の『ザ・サッド・マック』において、デジタル・エラーを意図的に用いることで未知のサウンドを生成する、00年代初頭の「DSP美学」を総括した。デジタル・グリッチ、エレクトロアコースティック、アンビエント/ドローンなど、さまざまな手法がアルバムのなかで、ひとつの大きな(繊細な)流れを生み出していた。それは確かに「完成形」であった。ゆえに『ザ・サッド・マック』以降の彼は『ザ・サッド・マック』のなかにすでに内包されていたドローン/アンビエント、フィールド・レコーディング的なサウンドを、多くのコラボレーション・ワークを行うことで、より深い場所へと潜航するように創作を続けていったように思う。
たとえば、06年リリースのヤネク・シェーフとの共作『ヒドゥン・ネーム』(〈クロニカ〉)。『ヒドゥン・ネーム』においては、古びた楽器や音源などが見事に加工され、過去へ遡行するような音響を作り上げていた。中世の記憶が、古びた洋館から芳香とともにたちがあるようなアンビエンス、音響......。09年のテイラー・デュプリーとの共作『トランスクリプションズ』(〈スペック〉)においても、「アナログ・レコードの元祖と言われる古いワックス・シリンダーと78rpmレコード」を素材に用いながら、過去の記憶が音響に溶けだしていくようなドローン・アンビエント作品を生みだしていた。
つまり、00年代中盤以降のステファン・マシューは、記憶と歴史のなかで打ち捨てられたような楽器や音盤をリサイクルすることで、過去と現在の記憶が溶けだすようなドローン作品を模索/創作していったのである。その彼の探求の最初の「成果」が2011年、ソロ作品としてリリースされた『ア・スタティック・プレイス』(〈12k〉)と『リメイン』(〈ライン〉)だ。また、2012年発表のカロ・ミカレフとの競演盤『レディオランド(パノラミカ)』(〈ライン〉)を加えてもいいだろう。
これらの作品は、総じて圧倒的に美しく洗練されたドローン/アンビエントな音響作品である。そしてこの「美しさ」はまさに反動ギリギリともいえる。しかし、ステファン・マシューはむしろ過激なまでに洗練されることで、果実が腐る直前のような強烈な甘さを音響に内包させたのではないか。
ではなぜ、ステファン・マシューはそのような洗練を追求したのか。それは、彼が本質的に、いわゆる「サウンド・アーティスト」というよりも、むしろ古典的な意味での「作曲家」だからではないか。それほどまでに、ステファン・マシューのドローンは弦楽曲のように聴こえるし、そこに彼ならではの和声や響きがある。ふたつ以上の音が重なり合い、絡まり、音と音のあいだから和声が生まれる。それは旋律のない旋律がもたらす恍惚。その音の重なりから生まれる響きに耳を澄ますと、多くの作曲家がそうであるように、ステファン・マシューもまた自分の響きに対するはっきりとした美意識があることがわかる。美を経由しない作曲家はありえない。彼の成熟は作曲家ゆえの要求がもたらしたものである。
そして、新作『アン・クール・シーミレ』は、「作曲家」としての美=意識が隅々にまで行き渡っている傑作である。本作もワックス・シリンダーや78回転レコードをコンピューター上でエディットする手法が用いられている。昨年の傑作EP『コーダ』(〈12k〉)を経由した本作の音響は、近作にみなぎっていた過剰な美しさに加え、枯れた美の質感すら獲得している。まずは、1曲め「メゾン」のこなごなになったレコード盤のような音響の素晴らしさに、耳をそばだてていただきたい。
さらに重要な点は、最初に書いたように「アルバム」として、ひとつのテーマ/コンセプトが全楽曲、構成に通奏低音のように響いている点にある。本作のアルバム・タイトルは、ギュスターヴ・フローベールの同名小説から取られている。この小説は、19世紀のフランスにおいて、愛を喪失し、信心深い女中の人生を描いたものだが、この作品においても不幸のなかの救いを希求する「崇高さ」を生成しているように思えた。
アルバム中、もっとも心揺さぶられるのは6曲め"ドゥヴニール・スール"である。突如、古いレコードからのサンプリングと思われる女性による歌曲が、ほぼそのまま流れるのだ。歌声にノイズがレイヤーされ、過去と現在の境界線が融解する。これまで音響のなかに溶け出していた「音楽」が突如、不意に実体化する鮮烈な驚き。まるでミサ曲のような「崇高さ」が、古い素朴な歌曲に宿っている。つづく7曲め"フェリシテ"で、なんとアコースティック・ギターのアルペジオが聴こえてくる。ステファン・マシューのアルバムで、このような音が聴けるとは! そしてラスト8曲め"トレース"は15分に及ぶ音響作品。この曲で静かに幕が下りる。幽霊のように不意に実体化した音が、また再び、アンビエントなドローンへと溶け出していく......、そんな見事な構成である。
『ア・スタティック・プレイス』と『リメイン』を経た、この『アン・クール・シーミレ』は、『ザ・サッド・マック』以降、やっと発表された「アルバム作品」のように思えた。『ザ・サッド・マック』には、DSP美学の終焉とデジタル以降の環境のなかで生きるモノたちの「喪失」というテーマや物語が静かに込められていた。そして本作にもまた、ある物語とテーマが込められている。それは何か? もちろん、想像でしかないが、喪失し、忘れられた過去を蘇生し、音として生成し、いまこの瞬間に弔うことではないかとも思う。
記憶が、夢のように溶けあっていく感覚。音響による過去と現在の(記憶の)交錯=融解。それは「アルバム」を聴くことから生まれるイマジネーションの生成でもある。本作は、知覚と記憶の深い部分に作用する作品のように思えた。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE