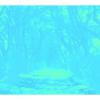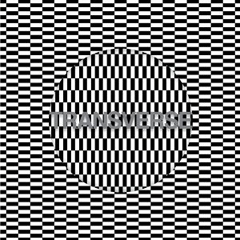MOST READ
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- レア盤落札・情報
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス
- Cornelius - 夢中夢 -Dream In Dream-
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- Jlin - Akoma | ジェイリン
Home > Reviews > Album Reviews > The Knife- Shaking the Habitual

レオス・カラックス監督の13年ぶりとなる長編作品『ホーリー・モーターズ』(2012)で、主人公のオスカー(ドニ・ラヴァン)は厳密な時間管理のもと、リムジンの車内で衣装やメイクによって自身を作り変え、異なる人生を次々と演じていく。この映画の始点には、「自分自身でいることの疲労、自分自身であり続けることの疲れ」と「新たに自分を作り出す必要」というふたつの感情があったことを、カラックスは明らかにしている(https://www.outsideintokyo.jp/j/interview/leoscarax/index.html)。そしてまた、映画監督としての自分、あるいは夫や父としての自分など、相手や置かれた立場によって役割を演じ変えることについても語っている。「それらは人生の演技の一部なのだと思います。しかしそうした演技を止めたとき、いちばん疲労感を持つのではないかと思うのです。映画なのか恋愛なのか分かりませんが、どこかそこに行けば、自分自身が何なのかを見つけることができるとされている場所があるはずです。ですからすべての人々がこのように演技をしているときと、そして自分自身が誰なのかを知ろうと努力をしているときとの間を、旅しつづけているのではないでしょうか」。オスカーが思春期の娘を持つ父を演じるシーンにおいて、彼が娘に言い放つ「お前の罰は、お前がお前自身として生きることだ」という台詞は、カラックスのアイデンティティに対するそういった複雑な感情が書かせたものだろう。そしてこの台詞は、『ホーリー・モーターズ』の核心のひとつに迫っている、非常に重要な言葉でもある。
スウェーデン、ストックホルム出身のカリン・ドレイヤーとオラフ・ドレイヤーの姉弟からなるエレクトロ・デュオ、ザ・ナイフも、「アイデンティティ」というアイディアに対して慎重な距離を保っている。それが極端に表れているのは、彼/彼女たち自身のヴィジュアル・イメージの扱い方だろう。ザ・ナイフは自分たちのイメージを慎重に取り扱っているようにも、巧妙に取り繕っているようにも、あるいは弄んでいるようにも見える。前作『サイレント・シャウト』(2006)のリリースに伴う取材に際して、2人は真っ黒い仮面(長いくちばしを持った鳥のような形状をしている)を決して外さなかったという。そして、7年ぶりとなるフル・アルバム『シェイキング・ザ・ハビチュアル』のリリースに際しては、対面での取材をまったく行なっていない。代わりにメディアにばらまかれたのは、ふたりの顔が判然としない写真や、体操選手とそのコーチのようなコスプレをしたイメージ、パーカーのフードを被り、京劇の化粧を簡素にしたような白塗りの上に黒いマスクをした写真など、てんでバラバラなイメージばかりである。スカイプを介して行われたガーディアン紙のインタビューで、カリンは「異なる役柄を試してみることは常に楽しいことよ」と語っている。彼女はジュディス・バトラーの「わたしたちは常に女装している」という言葉を引用しながら問いかけている。「それは"真正性"に関係しているわ。自分が本当の自分自身である時間なんて本当にあるのかしら? 私たちはつねにすでに、何かしらの役割を演じているの。ギターを持って自分の感情について歌っている男たちだって、"そういうことをする"人間の役柄を演じているんだわ」。
ザ・ナイフの試みてきたことは、オロフによればクィア理論の実践であり、人々が「真正」だと感じる音と正反対の音――すなわち、どこから来たのかわからない、出自を知りえないような音の探求であった。そして、その音とはシンセサイズドされた音や声なのではないか、と。ジェンダーやセクシュアリティの問題へと直截に切り込んでいる、多分に政治的なこの『シェイキング・ザ・ハビチュアル』というダブル・アルバムは、彼らの作品のなかでももっともとっちらかった作品であるとともに、ザ・ナイフが試みてきたそういった音の実験のひとつの到達点であるように思える。"ア・トゥース・フォー・アン・アイ"や"ウィズアウト・ユー・マイ・ライフ・ウッド・ビー・ボアリング"、"レイジング・ラング"では、どこのものとも知れぬトライバルなパーカッションが鳴り響く一方で、19分にも及ぶ"オールド・ドリームズ・ウェイティング・フォー・リアライズド"や約10分の"フラッキング・フルーイド・インジェクション"においては、声や電子音による長大でおどろおどろしいドローンが展開される。8分以上の曲が6曲もある一方で、1分にも満たない曲もある。全編にわたってカリンのヴォーカルは奇妙に捻じ曲げられ、ピッチは激しく上下にシフトさせられ、ビートを構成するキックやパーカッション、ベースの音は気味悪く歪んでいる。まるで、『サイレント・シャウト』のゴシックでインダストリアルな感覚が増幅されすぎたために引き起こされたフィードバック・ノイズが通奏低音として鳴っているかのようだ。『シェイキング・ザ・ハビチュアル』の不快とも言えるおどろおどろしく歪んだ電子音に95分間どっぷりと浸かっていると、次第に感覚が麻痺しだし、快い忘我と陶酔に襲われる。そこでは、この音楽が"真性"かどうか、ザ・ナイフのふたりがいったいどんな容姿をしているのかは問題ではなくなってくる。快と不快、美醜、真贋といった価値づけは混乱し、転倒をきたす。
先のインタヴューでオロフは「音楽の歴史は特権的な白人男性が書いてきた」とまで言っている。ザ・ナイフはそうした音楽の「正史」に対し、はっきりと反旗を翻している(ちなみに、オロフは出演者のうち、男性が半数以上を占める夜間のイヴェントやフェスには出演しない)。男装する老女や緊縛されるクィアが登場するヴィデオが衝撃的な"フル・オブ・ファイア"で、つんのめるようなビートがループするなか、カリンは歪んだ声で問いかける。「ときどき、わたしは解決が困難な問題(problem)を抱える/あなたのストーリーはどんなもの?/それが私の意見/問題(question)と回答には長大な時間がかかりうる/ストーリーはここに/あなたの意見はなに?」「全ての男たちと、男のお偉方は誤ったストーリーを語っている」「さあ、ジェンダーについて話そう、ベイビー/私とあなたについて話そう」と。
"慣習を揺さぶること"と題されたこの作品においてザ・ナイフは、シンセイサイズドされたダークなエレクトロニック・サウンドによって、"自分が自分自身として生きる罰"を科す運命論者たちに果敢に挑戦し、旧弊な慣習を切り裂いている。それはじつに痛烈な一撃である。
天野龍太郎
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE