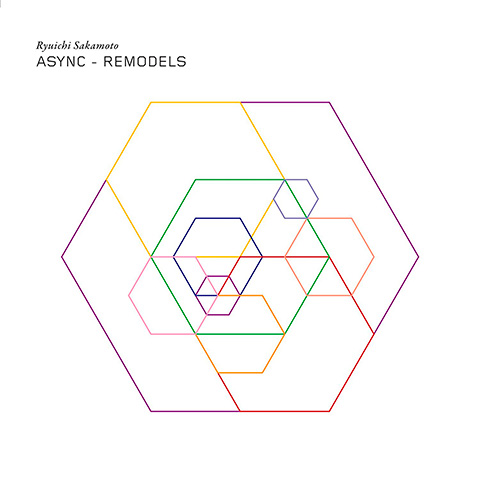MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ryuichi Sakamoto + Taylor Deupree- Disappearance

坂本龍一とテイラー・デュプリーのデュオ・アルバムである。そう書くだけで、とても重要な出来事に思えてくる。カールステン・ニコライ、クリスチャン・フェネス、クリストファー・ウィリッツなど、エレクトロニカ/電子音響において、00年代を通じてエレクトロニカ・アーティストとコラボレーションを繰り広げてきた坂本龍一にとって、最後のピースとでも言うべき人物がこのテイラー・デュプリーであった。
もっともデュプリーは坂本龍一の『キャズム』(2004)のリミックス盤『ブリコラージュ』への参加、坂本は、〈12k〉からリリースされたソロアンダーダの楽曲"コラール(ルック・フォー・ミー・ヒア)"(2009)のリミックスなど、00年代を通じて単発的な仕事の交流はあった。そのうえ一般リスナーの間にも坂本とデュプリーの交流は伝わっていたし、ファンは、いつの日が完全なコラボレーションが実現するだろうと思っていたはず。
そんな10年以上に及ぶ邂逅を経て、この夏、遂に発表されたふたりのデュオ・アルバム『ディスアピアランス』を聴き、わたしは、ある重要な変化を聴きとることになった。ひとつは坂本龍一のピアノの音色の変化、もうひとつはデュプリーの音響の変化である。
このアルバムにおいて、坂本のピアノは単音の美しさが際立っているように思えた。坂本龍一のピアノ(の和声)は、もはや「サカモトコード」とでも言ってもいいほどに独自の感覚が横溢しているが、この作品においてはまるで硬質な音の粒/点のように響いているのだ。エレクトロニクスのレイヤーにおいては、ピアノは、和声よりも、単音のほうが美しく響くといわんばかりに、である。近年、坂本龍一はプリペアド奏法を駆使するなど、インプロヴァイザー的な演奏が増えているのだが、このデュプリーとの演奏(この作品の元はふたりのリハーサル音源だという)において、坂本龍一はどこかプリペアド的な響きを、鍵盤上のピアノの響きに持ち込んでいるように思えた。その硬く、そして柔らかく、透明で、同時にくすんだピアノの、単音、の響きは、美しい。
テイラー・デュプリーの音響にも、ある変化があった。デュプリーのソロ最新作『フェイント』(2012)に満ちていた午睡のまどろみのようなサウンドだけではなく、硬い木々が水の中でぶつかるような、もしくは氷とガラスの光の反響のような音響がトラック全体に密やかに(あるいは大胆に?)鳴り響いているのである。世界の静寂に耳を澄ますと、さまざまな音/響のざわめきが耳の前に立ちはだかってくる、そのように感じられる音響だ。柔らかさだけではなく、微かな緊張が蠢いている。個人的には近年のデュプリー・ワークスのなかでもベストだと思う。
そして、アルバム最後の楽曲"カール・トゥ・ミー"において、青葉市子の「心音」がこの音響空間に導入される。まるで比較的早めのBPMのビートのようなその鼓動は、クリスタルな坂本のピアノと深遠/繊細なデュプリーの音響の空間の中心に、しなやかに侵入してくる。人と人から、人と人と人の関係へ。2人から3人へ。異質な他人が、バラバラのまま存在し、距離を保ったまま、調和を実現する瞬間の安らぎ(不協和ですらも、だ)。異質であることが、排除に結びつかない理想的な音楽の共有空間。ザワメキと沈黙。持続と円環。世界の音と人の心臓の音。まさにエレクトロニカ・フィールドに導入されたジョン・ケージ美学を音響化したかのような楽曲=音響=演奏である。
わたしは、このアルバム名を見たとき、坂本龍一の最初の録音作品である坂本龍一+土取利行『ディスアポイントメント・ハテルマ』を思い出した。現在、世界的な作曲家ともいえる坂本龍一は、そのレコード・デビュー時から即興演奏家でもあったとはいえないか。近年、海外のエレクトロニカ・アーティストとのコラボレーションからも、その即興演奏家としての息吹を聴きとれるだろう。わたしには『ディスアピアランス』と『ディアポイント・ハテルマ』は見事に円環をなしているように思えてならない。フリー・インプロヴィゼーションから電子音楽に。電子音楽から電子音響へ。本作は、インプロヴァイザーとしての坂本龍一、電子音楽家としての坂本龍一という、坂本のビハインド・ザ・マスクが垣間見える作品でもある。
同時に、デュプリーや00年代エレクトロニカが、(結果として)「ケージ美学」を導入していくことで生成したアンビエント/ドローンな音響空間の、そのほとんど最後の響きのように思えた。それは心地よさに耽溺するだけではなく、沈黙の果てにある緊張感をも内包するに至ったから、とは言い過ぎだろうか。
そう、このアルバムを最後にドローン/アンビエントは、再び冥界に入っていく。わたしたちは、そろそろ「美学」ではなく、アンビエントの先にある本当の沈黙を聴かなければならない時期に差し掛かっているのではないか。だからこそ、密やかな音のザワメキに満ちたこのアルバムに封じ込められた「沈黙」の、そのむこう側にそっと耳を澄ましたい。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE